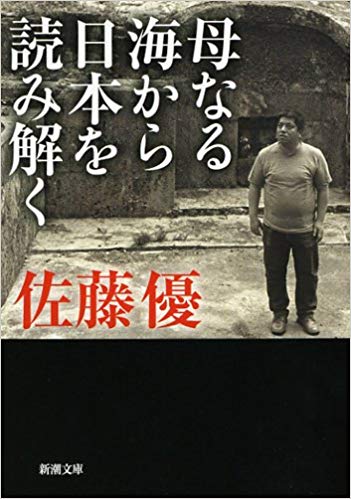
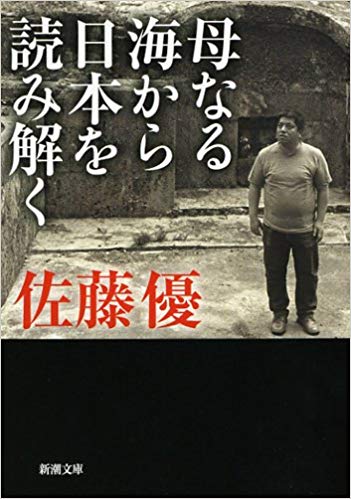
「はじめに」で著者が言っている。本書は極めて内面的な本だと。
実際そのとおりだった。著者の母は沖縄久米島の出身だという。沖縄戦で命からがらの目に遭い、上京して東京出身の方と結婚した。そして生まれたのが著者だ。著者は成長期を通じてさいたま市で育った。沖縄を知らずに。
外交官として長い期間活躍した著者は、北方領土返還交渉の過程で検察に逮捕される。512日にわたった勾留期間。その間の孤独は著者を内側に向かわせた。そして、著者はさまざまな本を取り寄せ、自らを顧みる。そして勉強する。数多く読んだ本の中で、著者は沖縄に伝わる伝承をまとめた『おもろそうし』に揺さぶられる。それは著者が自身のルーツを見つめなおす契機になった。そうして著者は、自らのルーツを探りながら沖縄を考察する。その結果が本書だ。
考察を重ねる中、著者が得た気づき。それは久米島を中心に世界を俯瞰する視点だ。もともと、外交官の職柄として、地球規模で物事を考える習慣は身についていた。その極意とは、地球は球であること。球である以上、本来ならばどこを中心としても地表は見渡せるはず。それは東京でもモスクワでも北方領土でも変わらない。ならば久米島でも同じ。これこそグローバリズム。著者は『おもろそうし』からグローバルな視点を会得する。
自身で分析しているとおり、著者は外交官としての北方領土交渉を通して、自らの内にあるナショナリズムに気づく。自分が日本人という深い自覚。その自覚は獄中生活でより研ぎ澄まされ、『おもろそうし』によって自身のルーツ沖縄への探究心に結びつく。それと著者が会得した久米島を中心とした視点を組み合わせ、の久米島から世界を見るとの着想となったのが本書だ。
本書が描くのは久米島の視点から見た沖縄史だ。ある程度の時間軸に沿いつつ、随所に久米島や琉球の民俗を考察しつつ、本書は進み行く。正直にいうと、沖縄、琉球の文化民俗に興味のない向きには本書はとっつきにくいだろう。なぜなら「はじめに」で著者が言うとおり、本書は著者が己の内面に眠るルーツを探す本だからだ。ルーツ探しとは血脈をたどるだけの話ではない。むしろ、久米島の民俗の歴史を深く掘り下げながら、久米島の視点で文化的なルーツを探る旅だ。そのため、琉球の歴史や文化を知らないと、本書の記述は理解できにくい。私も本書を読み終えるのにかなりの時間をかけてしまった。
ニライカナイやユタ、キジムナーの存在。天命思想による支配者の交代を受け入れる文化。著者によれば琉球をヤマトと分けるのが天命思想の有る無しだという。日本の天皇家は一つの血族でつづいている。断続が疑われた継体天皇への王位継承も、著者は同じ天皇家とみなしている。そしてヤマトは同じ天孫族による皇統が続いて来たとみなしている。
それに比べると、琉球には統一された一族による支配を正当化する考えが薄い。尚氏にしても第一尚氏から第二尚氏の間には断絶がある。第二尚氏の創始者は、尚氏とは全く関係のない離島からやってきて頭角を現した金丸なる人物だという。そればかりか、その王朝交代がさほどの抵抗もなく受け入れられる。天命が第一尚氏から去ったと見るや、人々は素直に支配者を変え、離島からやって来た人物の支配に服する。それが著者の言う天命思想だ。血脈が支配者の条件ではなく、天命こそが支配者の条件。
久米島もそう。久米島は長年、琉球から独立した王国を保っていた。そんな久米島にも本島から按司がやって来て尚氏の支配に組み入れられる。その当時、久米島を統治していたのは「堂のひや」と呼ばれる人物。彼には人望もあったらしい。だが、すんなりと按司に支配権を譲る。だが、また本島から違う按司が攻め立てて来た時、「堂のひや」は、逃げようとする前の按司から託された子をあっさりと殺す。そして攻め立てて来た按司に従う。天命が前の按司から去り、次の按司に移ったと見たからだ。
こういう割り切り方が、ヤマトにはとうとう根付かなかった。琉球は違う。支配者の正当性を割り切って考えられる。第一尚氏から第二尚氏への王朝の交替を受け入れる。さらに、明や清に朝貢しながら薩摩藩にもに朝貢するという、特異な外交関係も許容できる。琉球仕置で明治政府の傘下に組み入れられ、悲惨な沖縄戦の戦場とされ、アメリカ統治の時代を経過し、地域の名前が琉球から沖縄へ変わって行く間に支配者は次々と変わっていった。それらのどれをも、前の支配者の持つ天命が尽き、次の支配者に天命が降ったと受け入れることでやり過ごす。それが天命思想。
本書を読むと、この前に読んだ『本音で語る沖縄史』では取り上げられなかった文化の伝承を知ることができる。また、本書は本島ではなく、久米島からの史観だ。だからより大きな琉球の歴史の流れをとらえられる。「堂のひや」など、久米島についてのエピソードの数々は本島から見た歴史では抜け落ちてしまう。本書は私にとって『本音で語る沖縄史』を補ってくれる本となった。本書と前書の両方に共通していることがある。それは沖縄戦の描写がほとんどないことだ。類似する本が多数発行されており、経験者でもないため語るのを遠慮したということか。
ただし、本書が沖縄戦を描写していないことは、日本軍から米軍に天命が交替した、日本軍から天命が去り、米軍に天命が降ったと誤解してはならない。沖縄の方々にとって沖縄戦の経験を天命思想で片付けられたらたまったものではない。そう消化できるものではないはず。それを諾々と受け入れることもしないだろう。今なお基地が集中することも天命の定めるところと粛々と受け入れてもいないだろう。沖縄の基地の割合は本土に住む私から見てもあまりに不公平だ。厚木横田ライン上に住んでいて、騒音に悩まされる私としては、沖縄の基地問題は、天命思想で片付けて済むものではないと思う。
著者もそうした見方を採っていない。それどころか著者も基地問題については不公平と考えているようだ。外交官として国際政治のバランスを冷徹に見ている著者なら、地政のバランスから沖縄に基地が集中するのは仕方がないとの立場を採ると思い込んでしまう。だが、そうでもないようだ。著者は沖縄独立の可能性も俎上に上げ、冷静に沖縄の独立の可能性を分析する。著者の見立てによれば、国際政治のバランス上、沖縄は中国に接近するほかはない。そして、中国に接近することで、今より過酷な現実に直面するという。だから著者の結論では沖縄は日本に属していた方が現実を乗り切るのに適しているという。そして、基地を沖縄に集中させる事には反対だそうだ。沖縄の米軍基地をグアムや硫黄島、日本本土に移転させる案はどの程度実現性があるのか。本書ではそこまで踏み込んでいないものの、著者の立場は理解した。
久米島を真ん中に置いて地球を見ると、沖縄の地政上の現実がより具体的に迫ってくる。天命思想の下、波乱の数世紀を乗り越えてきた沖縄は、これからもいろいろな出来事に見舞われる事だろう。日本人としてどこまで親身になって考えるか。本書で繰り返し引用される仲村善の説によるなら、琉球民族も元は同じ大和民族に属するという。日本人も当事者として沖縄を考える時期に来ていると思う。
‘2017/06/29-2017/07/14




