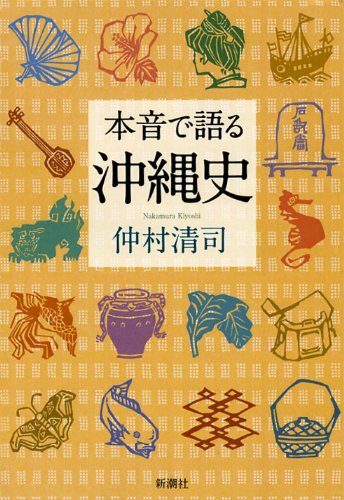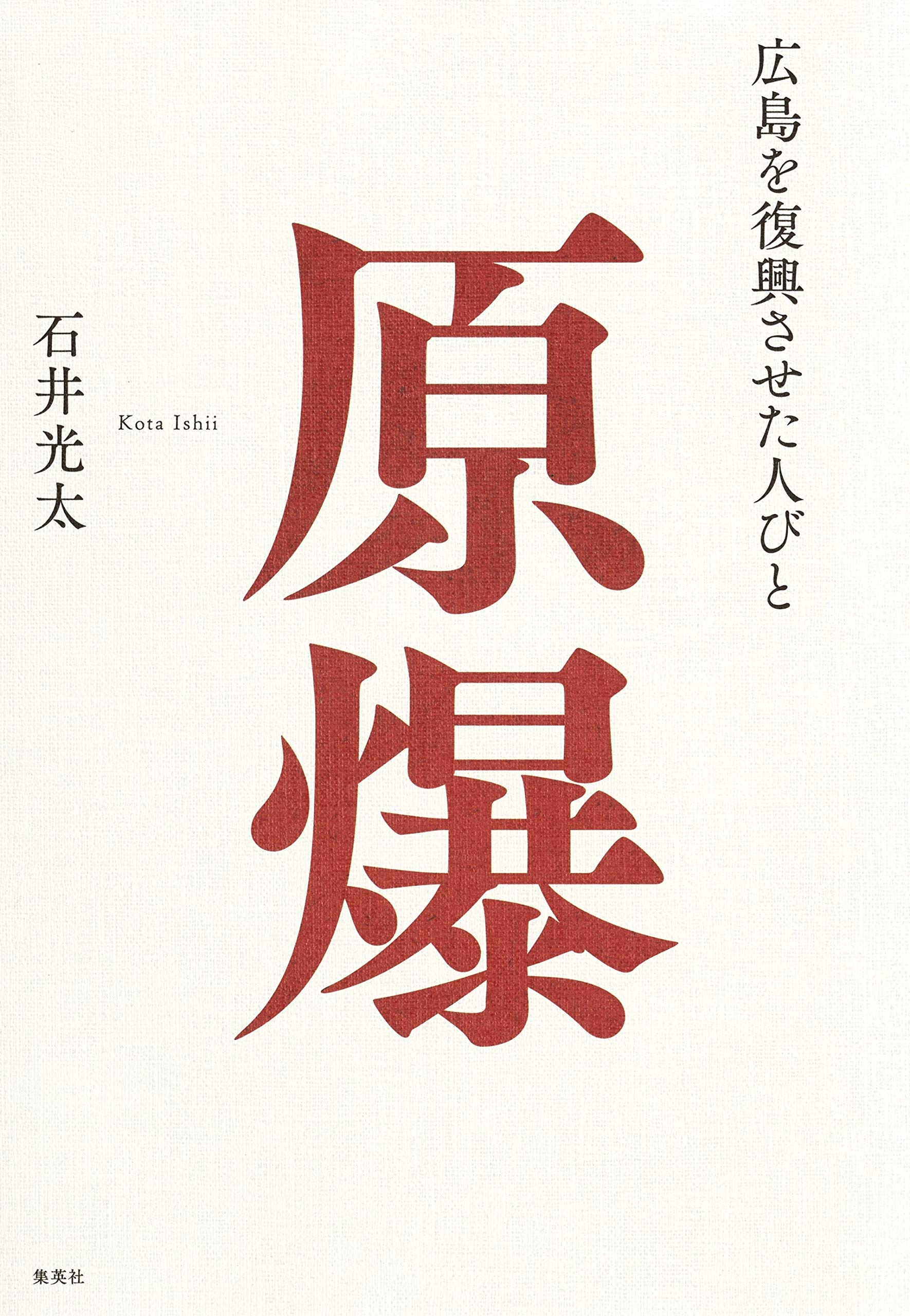
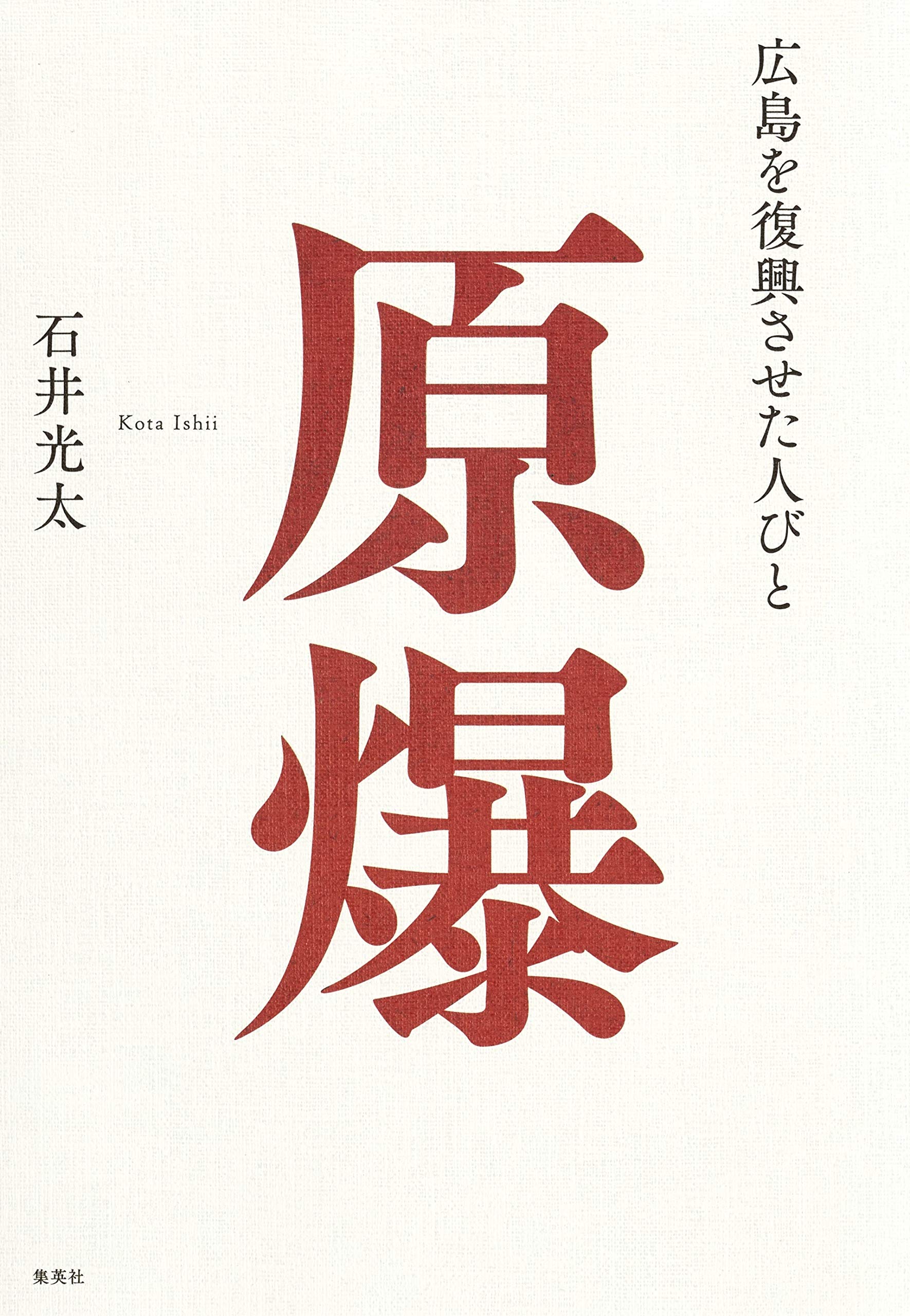
広島平和記念資料館を私は今までに三度訪れたことがある。1995年、1997年、2013年。
それぞれの訪問のこともよく覚えている。中でも初めて訪れた時の印象は強烈に刻まれている。
投下から五十年目の前日、8/5の朝を原爆ドームの前にテントを立てて野宿で迎えた私。その後に訪れたのが初訪問だ。
翌朝、8/6の投下時刻には、他の大勢の方々とともに原爆ドームの前でダイ・インに参加したことも懐かしい。
平和記念資料館を訪れると、東西に分かれたそれぞれの棟をつなぐ渡り廊下のガラス窓を通して平和記念公園が一望できる。完全に計算された配置は機能的で洗練されている。
洗練された公園の整備は、このあたりが原爆によって更地にされたからこそ実現した。資料館の中を訪れると、無残で悲惨という言葉しか絞り出せない被曝の資料の数々が私たちの胸を打つ。それらは、一瞬でなぎはらわれた荒野に残された痛ましいモノたちだ。
資料館、広島平和記念公園、平和大通り。この三つを含む地域は、川の対岸の原爆ドームや相生橋、元安橋と合わせて、平和都市広島を象徴している。
被曝で75年は草木も生えぬ、と言われた焼け野原の広島。その都市を復興させ、平和の尊さを世界と未来に伝え続けるシンボルとして整備を行ったのは誰か。膨大な資料館の展示品は、そもそも誰が最初に集めたのか。
本書はそうした巨大な事業に関わった四人の物語だ。
資料館に展示された膨大な展示物の中から、最も印象に残る物は、人によっていろいろだろう。
その中でも、実際に被爆し、亡くなった方が被爆当時に身に付けていた服は、実物そのものであるだけに、来館者の心に強く刻まれるに違いない。
でも考えてみてほしい。その展示物とは、着ていた方の肉親にとっては、亡くなった方の唯一の形見である場合も多いのだ。
遺族にとっては、亡くなった息子や娘を思い出すよすがとなる遺品。そうしたかけがえのない遺品が資料館には陳列されている。この事実に今の私たちはもっと意識を向けるべきだろう。
ただ単に歴史の証として展示されているのではない、ということに。
本書の主役は、膨大な被曝の収集物を集め、初代の平和資料館館長に就任した長岡省吾さん、原爆市長と称された浜井信三市長、広島の平和都市として都市計画を設計し、出身である広島に報いた丹下健三さん、そして自らが被爆者でありながらその被曝の思いを世界に発信し続けた高橋昭博さんの、四人だ。
被爆後のあたり一面の焼け野原に公園を設計し、整備し、シンボルを創り出す。
私のように都市計画を知らない素人には、人も家もないため、かえって楽じゃないかなどと考える。
だが、そうではない。
原爆の惨禍からかろうじて生き延びた人々は家を失っている。生き延びた彼らは、これからも生きるために家を確保しなければならない。ありあわせの材料をかき集め、バラックの家を建てる。
誰もいない荒れ地には、都市計画も道路計画も無意味だ。所有権も借地権も証明する書類は全て灰になり、証明する人もいない。あり合わせの材料で建てられたバラックも、被曝した人々が長らく住み続ける間に居住権が発生し、市当局はますます都市整備がやりにくくなる。
浜井市長が当選し、広島市の復興に向けて立ち上がった当時の昭和22年の広島は、そんな混乱の時期だった。
平和公園などを立案する以前に、現実に市民の最低限の生活をどうするか、という目先の仕事で精いっぱいの時期。
復員などで人が増えるにつれ、無秩序が市を覆い始めていた。そのような都市をどうやって平和都市として蘇らせるのか。それは、市政の先頭に立つ浜井市長の手腕にかかってくる。
浜井市長はもともと東大を出ながら結核で広島に帰郷し、広島市役所に奉職せざるをえなかったという。いわば挫折の経歴を持った方だ。
原爆の投下当時は配給課長として、被爆市民にいかに食料や衣料を提供するかの困難な課題に立ち向かった人物だ。戦後、その功績が認められ助役に、そして市長に推される。
原爆市長として十六年の間、市長を務める中で、粘り強く都市計画をやり遂げた功績は不朽だ。その困難な市政を遂行するにあたり、浜井市長が育んできた経験や人生観が大きく影響したことは間違いないだろう。
そして、丹下健三さん。
世界的な建築家として著名な方である。
広島平和記念資料館が実質的な建築家としてのデビュー作だそうだ。
デビューまでにも、丹下氏は幾度も挫折に遭遇し、それを乗り越えてきた。特に、死を前にした父を見舞おうと広島に向かう途中、尾道まで来たところで原爆が投下されたこと。父はすでに八月二日に亡くなっていたこと。五日から六日にかけての今治空襲で母を亡くしたこと。
原爆投下の前後に起こったこれらの出来事は、丹下さんの一生を通して、原点となり続けたに違いない。
高校時代を過ごした丹下さんの広島への想いが、平和大通りの横軸と、平和祈念資料館、慰霊碑、原爆ドームを通す縦軸への構想を生み出す原動力になったと思うと、平和記念公園を見る目も変わる。
丹下さんは、平和祈念公園を手がける前にも復興計画についてのコンペ募集があり、その時に挫折を経験していた。
さらに平和祈念公園ができた後も、平和のシンボルとなった公園を巡ってはさまざまな人々の思惑や暗躍が入り混じる。
本書を読んだきっかけに丹下さんのことをウィキペディアで調べると、手掛けた代表作のリストに私ですら知っている建物の実に多いことか。入ったことがある施設だけでも二十カ所近い。あらためて丹下氏に興味を持った。
長岡省吾さんの人生も実に陰影が深い。
若い頃に満州で過ごし、そこで現地の陸軍特務機関に入ったことで、一生をその経歴につきまとわれることになる。
鉱物に興味をもち、在野の研究者として活動した後、内地に戻る。在野の研究者として名が通っていたため、広島文理大学の地質学講師に職を得るが、研究者としては経歴が弱かったことが災いして不遇の日々を送る。
被爆後、経歴と興味から被爆遺物の収集を開始した長岡さんは、原爆の研究も開始する。
その努力は、後に初代の資料館館長に推されることで報われる。ところが経歴の不足が足を引っ張り、それ以上の待遇が長岡さんに与えられることはなかった。冷遇され続けた長岡さんは、個人で原爆研究を続けるためにUCAAにも籍を置く。だか、そこでも論文の署名が末尾に置かれるなど、長岡さんの不遇には同情するほかはない。
平和資料館の展示内容が、国や政府の思惑によってで原子力の平和利用の展示が追加されるなど、長岡さんの思いは裏切られ続ける。
長岡さん自身がUCAA活動によって市や資料館との関係が疎遠になったり、出征していた長岡さんの子息が戻ってきて対立したり、と長岡さんと資料館の関係は長年、良好とは言い難かった。
長岡さんの経歴には不明な点が多く、ウィキペディアにも独立の項目はない。
本書で著者が一番苦労した点は、長岡さんの経歴を調べることにあったようだ。長岡さんもまた、戦争に人生を狂わされた一人であることがわかる。
高橋さんは、資料館の展示でも著名な「異形のツメ」の持ち主だ。
投下の瞬間、屋外の作業に従事させられていた大勢の中学生が熱線をモロに浴びた。高橋さんもその一人。
死ぬまでの何十年の間、異形のツメは生え続けた。反核の活動者として、広島市の職員として、後には資料館の館長にもなった高橋さんの記憶に被曝の体験が残っている間。
被爆のケロイドとどのように向かい合い、葛藤をどのように乗り越えたのか。
長岡さんの後継者として目をかけられたが、長岡さんのように被爆資料と向き合うことができず、苦痛のあまり、一度は後継者にと目をかけながらも袂を分かった高橋さん。
被爆の瞬間を70キロ離れた場所で迎えた長岡さんと、1.5キロの至近で浴びた高橋さんには被爆物への思いの桁が違うのだろう。
高橋さんは、原爆ドームの保存を決断した浜井市長やそれに賛同した丹下さんの力も得て、原爆ドームの保存運動に市の担当者として貢献する。
なお、高橋さんは結婚したが子孫を残せなかったという。それは被爆の影響が大きいのだろうが、かわりに原爆ドームという平和のシンボルを残せたことで、わずかにでも心が安らいだのなら良いのだが。
著者は高橋さんの奥様にもインタビューを行っている。まさに奥さまが語った言葉が高橋さんの思いを代弁していることだろう。
本書は、かたちあるものを残すことの困難と、残すことができた建造物がいかに人類に永く影響を与えられるか、を示している。
私は今まで、人工の建造物に対しては山や滝を見るよりも思い入れが少なかったが、本書を読んで思いが変わったように思う。
本書には、高橋さんの体験だけでなく、資料館に陳列された遺品の持ち主の遺族のインタビューもかなりの数が挿入されている。読んでいて涙が出そうになる。
資料館では説明パネルの枠の幅から、遺品の背後にある被爆者の思いの全てが汲み取りにくい。
だが、著者はきちんと遺族を訪ね、インタビューを行ったのだろう。言葉の1つ1つにあの日の血と肉が流れているようで痛ましい。肉親をなくした悲しみが文章から吹きこぼれ、私に迫ってくる。
著者の取材は丁寧で、文体も端正。
私が知らなかった資料館の展示に一時、原子力の平和利用があったことや、浜井市長が一度落選した経緯、反核・非核の運動の紆余曲折など、押さえるべきところを押さえた内容はお見事だ。
そして、20代の初めにヒロシマを訪れ、ヒロシマから影響を受けながら、とうとう本書のような作品を書こうともしなかった私自身が本書から受けた感銘は深い。
著者の作品を読むのは本書が初めてだが、他の作品も読んでみたいと思った。
本書は広島を描いたノンフィクションとして、私の中では最高峰に位置する。
‘2019/9/4-2019/9/4