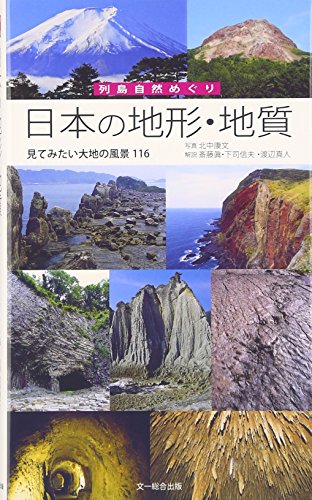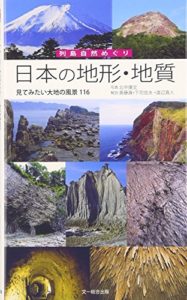本書を読んだのは沖縄へ向かう機中だ。私にとっては九カ月ぶりの沖縄、前回の旅は沖縄戦と琉球文化を知る旅だった。ただ、二十二年ぶりの沖縄だったため、各訪問先のごとの思い出を作るのに精一杯だった。その時のブログは以下のリンクに書いた通り。今回は家族との旅を楽しむつもり。戦跡も巡るが、美ら海水族館やビーチにもいく。
・家族で沖縄 2018/3/26
・家族で沖縄 2018/3/27
・家族で沖縄 2018/3/28
前回の旅で触れることのできた琉球の文化はほんの一部。沖縄にはもっと奥深いところに旅人の心を揺り動かす何かがあるはず。そう思い、今回は沖縄の文化について事前に予習することにした。
本の内容が現実にリンクした時、読書の醍醐味は実感となる。この実感は、おととしに家族で訪れた長崎で味わった。浦上天主堂が一部の遺構を残して撤去された経緯を描いた本< ナガサキ 消えたもう一つの「原爆ドーム」 >を読んだ翌日、長崎の街を歩いた時に感じた思い。本に描かれた天主堂の遺構や再建された天主堂をこの目で見たときに感じた感動は、読書家としての私自身の生き方に誤りはないと確信させた。
本書は実に面白かった。そして本書の内容が私の沖縄の旅にリンクした。だからこそ思い出に残った。
第一章の「沖縄そば」がすでにそうだった。前回の私の沖縄旅の目的の一つは、沖縄そばの神髄を知ることにあった。そのことは先に紹介したブログに書いたとおり。私が旅の途中で食べたのは豊見城にある「名嘉地そば」さんだ。それはとてもおいしかった。だが、革命的な発見を思わせるほどでもなかった。私が知っている沖縄そばとは、本土で食べるものだった。本土で食べる沖縄そばは、本当に沖縄そば本来の味なのだろうか。その探究心に駆られて訪れた「名嘉地そば」さんは、本土で食べる沖縄そばをおいしくした味だった。だが、それでは私の沖縄そばの本質を知りたい欲求を満たせない。私の知らない沖縄そばがあるのでは、と疑っていた。
東南アジアから台湾をへて沖縄、そして日本。その円弧上に沿って北上するうちに、麺文化は食べる麺からすする麺へと姿を変えて行く。そう書いたのは著者だ。それは確かに瞠目すべき発見に違いない。ところが、著者が発見はした事実とはそれだけにとどまらない。著者は沖縄そばが本土に影響されつつある現状をも発見する。そして著者は、沖縄そばが次第に食べるそばから啜るそばに変わってゆきつつあるのでは、と懸念する。その事実は、ずいぶん前から沖縄に足を運んできた著者だからこそ気づけたのだろう。おそらく著者の発見とは、食文化を語る上でずいぶんと貴重なものだと思う。
著者は沖縄そばを知るため、那覇から食べ歩きを始める。その探求はファミリーマートで売られている沖縄そばにまで及ぶ。本書で紹介されているファミリーマートの沖縄そばは私も目撃した。だが、本書を読んでいたためか食指は動かなかった。
著書の探究は那覇では実を結ばなかった。だから著者は国道58号線を北上しながら食べる沖縄そばを求める。そして、普天間にある三角食堂と、名護の八重食堂で著者は食べる沖縄そばに巡り合う。両者ともに那覇ではなく、郊外で見つかったところが興味深い。著者は、沖縄そばの中に那覇そばというカテゴリーがあるのでは、と結論を出す。それもまた興味深い。なぜならば、Wikipediaからの知識では、沖縄そばは那覇で生まれ、発展したはずだから。
ちなみに今回の沖縄の旅において、私は糖質オフダイエット中だったのであまり沖縄そばを食べなかった。しかし、知念岬の近くにある南城市地域物産交流館で食べた野菜そばはとてもおいしかった。
著者の啜るそばと食べるそばの切り分けは興味深い。おそらく的を射た指摘なのだろう。ただ著者は、啜るそばに変わったからと言って沖縄そばがまずくなったのではなく、むしろ全体のレベルは上がっているという。
私が知りたい沖縄そば。それは食べるそばを指すのだろうか。であれば、多分まだお目にかかったことがないはず。私が本土で食べたことのある、そして前回と今回の旅で食べた沖縄そばとは、本土向けにアレンジされた啜るそばではないか。ということは、私はまだ沖縄そばを知らない。多分、食べる沖縄そばを味わえた時、ようやく私は沖縄そばの世界の入り口に立てるのだろう。それまでは沖縄そばについて蘊蓄を披露するのはよしたい。
なお、本章の補足としてシーブンについての考察も載っており、これも興味深かった。シーブンとは沖縄の定食屋で出されるサイドメニューのことだという。メニューに載っている料理を注文すると、サービスでサイドメニューがドドんと出される。その量の多さは、料理に込められたサービス精神の表れだ。私はまだシーブンを知らない。前回も今回も定食屋には入らなかったから。さらに私は、ホテルや観光地の食事しか沖縄料理をしらない。だから、沖縄料理を語る愚は避けなければ、と自戒した。
第二章「カチャーシー」も、本書を読んですぐ、旅の中で経験したことの一つだ。
カチャーシーとは何か。それは琉球の踊りだ。阿波おどりや盆踊りのようなものと思えばいい。だが、それらの踊りとは明らかに違う、琉球に独自の振りがあるのだという。本書にはこう書かれている。「なお、不慣れな本土の人間が踊ると、たいていは阿波踊りになる。」(71ページ)
著者が栄町市場のカメおばぁにカチャーシーを習う。そして、カチャーシーが何かを悟る。沖縄ではめでたいことがあるとすぐにその場でカチャーシーを皆で踊り狂うという。
本書を読んだ後、私はカチャーシーが何かを体験する。それは国際通りでのことだ。妻が以前の旅で訪れたという波照間https://hateruma.jcc-okinawa.net/という店に入った(実は妻の勘違いで、違う店だったのだが)。このお店で食べた料理はおいしかったが、それ以上に島唄三線のライブがあり、私の中で印象に残っている。島唄三線のライブが終わりに近づくと、座敷で飲み食いしていた客が何人もランダムにステージに上げられ、皆で踊る。私は幸いなのか残念なのか、ステージに連れていかれなかったため、カチャーシーを踊る経験は積めなかった。だが、これがカチャーシーか、と目の前で見聞きできたのは大きい。本書を読んでいた私は、目の前の楽しげな騒ぎがカチャーシーであることを理解できた。
本章は本書の中でも核心ともいえる。なぜなら、沖縄病について考察されているからだ。著者はその中で本土と沖縄の根本の違いについても鋭く触れている。
沖縄病について触れた文章を引用する。
「沖縄病という病は、基本的に片思いだから、その人の沖縄への思いだけが空まわりする。しかしどこか嬉しい。片思いとは、そういうものだ。かつて僕自身、かなり重い沖縄病を患っていたから、そのあたりの感覚はよくわかる。
沖縄病に罹った人たちの一部は、移住を決意する。沖縄に移り住む・・・それは簡単なことではない。若者が沖縄に仕事を見つけて移るのならまだしも、本土生活の基盤があった人にとっては大変な覚悟である。人生のターニングポイント・・・と考える人もいる。そこまで沖縄への思いが増幅される。」(64P)
著者は自らが経験したカチャーシーを語り、まだ沖縄の人になりきれていない自分を悟る。それは八重山商工が甲子園に出た時のことだ。試合に勝った後、自然とカチャーシーがスタンドで沸き起こる。ところが著者はその場にいながら腰が上がらなかったのだという。それでも著者は悟る。
「カチャーシーとは踊りではなく、嬉しさを示す手段なのだ。」(88P)
著者はカメおばぁからカチャーシーを教えられながら、笑顔がないことを注意される。カチャーシーとは喜びの表現だからだ。そしてうれしさとは自然に出てくるものでないと駄目だ。観察者として傍観するのではなく、主導者として表現しなければならない。そこに沖縄と本土の違いがある。著者は沖縄と本土の違いを考える。ところが核心をつこうとしてつけていない。著者自身が自身の本土から来た者としてのアイデンティティと沖縄に染まる理想を紐づけようとして苦心している様が本章からはよく分かる。だから本章は本書でも核となるのだ。
第三章「LCC」は、沖縄の航空事情について語る。今回の沖縄の旅でも私たちはスカイマークを使った。それだけに、著者の言いたいことが理解できた。東京都心部から成田空港へのアクセス時間や、成田から那覇へのLCCの発着の時間。LCCの誕生が沖縄本島へのアクセスだけでなく石垣島や宮古島への往来を楽にしたこと。沖縄へしょっちゅう行き来するという著者だからこそ書ける考察に満ちていたのが本章だ。
第四章「琉球王国と県庁」は、本書の中でも若干異質だ。少なくとも、本書のタイトルが表わすゆるさとは違う。硬派な内容で埋められている。基地問題と沖縄。地上戦と沖縄。本土の沖縄。米軍と沖縄。どれほど沖縄が観光で栄えようとも、それらの問題を忘れ去るわけにはいかない。そうした矛盾の中で沖縄はどう生きてきたのか。そして、これからどう生きようとするのか。それを著者は探っていく。本章からは、被害者としての沖縄だけではなく、したたかな沖縄の姿も見えてくる。
著者は沖縄を取り上げるライターとして、観光本も手掛けているそうだ。著者は観光地沖縄を扱いながらも、被害者としての沖縄を忘れていいのか、と自らに問う。また、同時に米軍基地の存在が沖縄に利益を与えている現状もきちんと踏まえる。理想と現実の両者を見つめながら、沖縄は生きていかなければならない。基地がいい、悪いといった単純な二元論に陥っていないところが評価できる。
「沖縄は戦争の犠牲になった。しかし、本土の人々が、加害者意識に縁どられた視線をいくら向けてくれても、沖縄の人が豊かになるわけではなかった。沖縄の人々がほしいのは、同情ではなく、島が生きていく方法論だった。」(147P)
この文は、基地の反対運動に奔走する運動家への問題提起になっている。沖縄=善、本土=悪という視点にこだわっていては導き出すのもむずかしいだろう。本書が朝日文庫に収められており、親会社が朝日新聞社である事を考えると興味深い。
今回の沖縄旅行の三日目の朝、私は県庁前あたりをうろついた。その前の夜は北谷のアメリカンビレッジにも訪れた。初日はひめゆりの塔やアブチラガマで戦地に立った。本章は、そうした私の経験にリンクした。この章も本書では見逃せない。
第五章「波照間島」もまた味わい深い章だ。波照間島という日本最南端の島。その地を「離島の離島」という言葉で描き出しつつ、そこを訪れる訪問者の心境を探ってゆく。著者の友人で「ウルトラマン研究序説」を編集した人物がいるという。その人物は結局自死の道を選んだそうだ。そして自死する前に波照間島をいく度も訪れていたとか。そして一人で凧を挙げていたことが紹介される。著者はその友人を感傷的に振り返る。離島の離島は果たして人生の終着駅になりうるのだろうか。
今回の旅では波照間島には行かなかった。が、那覇で訪れた居酒屋の名前が波照間だったこともあり、本書と私の旅のリンクは続く。
第六章「農連市場」は、再開発の波によって姿を消した農連市場の姿をカメラマンの阿部稔哉氏が写真に収めている。再開発された農連市場の横を通ったのは、旅行の二日目、美ら海水族館へと向かう時。外観もすでに新しい姿だったので、本書に収められたような姿はみられなかった。だが、旅の三日目に市場本通りとむつみ橋商店街を少し歩いた。両方ともに昔ながらの庶民的な雰囲気に満ちていた。おそらく在りし日の農連市場もこのような場所だったのでは、と推測できたように思う。
第七章「コザ」は、今や寂れてしまったコザを仲村清司氏が文章に著している。コザは沖縄市にあり、嘉手納基地の足元にある。日本返還前にコザ暴動がおこった場所でもある。そのコザはかつては米兵で大賑わいだったらしいが、今は閑散としているという。その歴史や今の現状をルポルタージュの風味で描いたのが本章だ。
旅の二日目の夜、沖縄在住の友人の一家と北谷のアメリカンビレッジで夕食を一緒に過ごした。アメリカン・ビレッジは繁盛しており、沖縄でも成功したショッピングセンターとして評価が高いようだ。訪れた私も家族もアメリカン・ヴィレッジの活気を楽しんだ。アメリカンのはビレッジはコザからそう離れていない。
私は夕食の場で友人にコザの今がどうなのか聞いた。すると、まだ夜のコザは華やかだと言って夜の様子を写真で見せてくれた。米兵が多数たむろする歓楽街として、コザは今も機能しているようだ。ただし、女性が行く場所ではないとか。
それは仲村氏が取材した後、コザが盛り返したためなのか。それとも仲村氏のルポのタイミングがたまたま寂れていた時間帯だったのか。私には分からない。だが、北谷アメリカンヴィレッジがこれだけにぎわっていることは確かだ。コザの賑わいがそっくり北谷に移っただけなのかもしれないし、そもそもコザを訪れたことのない私には判断できない。どちらにせよ、私は今までの三度の沖縄旅行でコザに行ったことがない。次回、沖縄を訪れたあかつきにはコザを訪れようと思う。友人の一家もコザの近くに住んでいることだし。
第八章「沖縄通い者がすすめる週末沖縄」
第九章「在住者がすすめる週末沖縄」の両章はタイトルそのままの内容だ。それほどページ数は多くない。だが、ガイドマップには載っていない情報なので面白いかもしれない。むしろ、著者の視点ではない沖縄が紹介されており、ためになる情報だ。本書の他の情報と同じく。
‘2018/03/26-2018/03/26