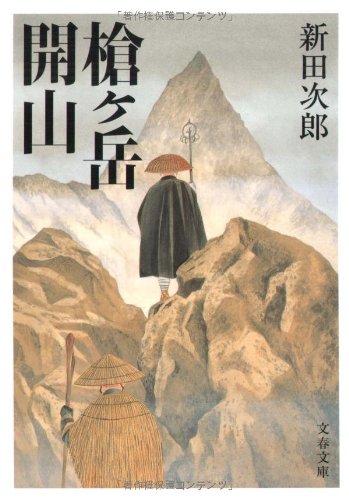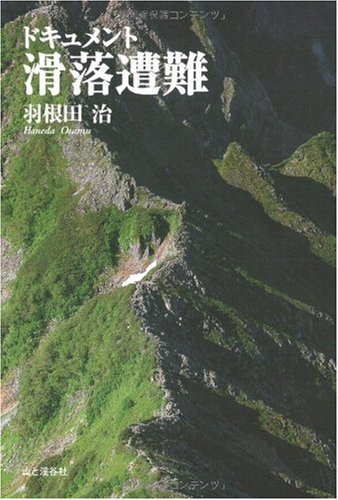
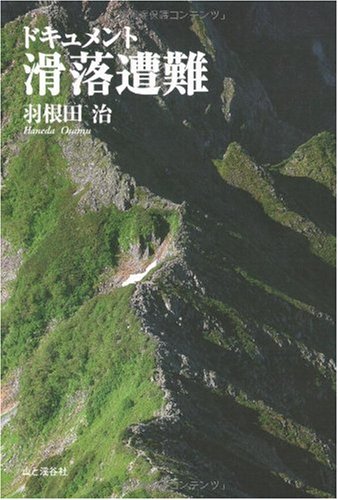
ここ数年、滝に関心を持ち、ひとりであちこちの滝を訪れている。ここ二年は山登りのパーティーに参加し、あちこちの山へ登るようになってきた。
そのパーティーのリーダーによる硬軟を取り混ぜた見事なリーダーシップに、私自身も経営者として学ぶところが多い。
私の場合、独りで移動するにあたってはかなりむちゃもしている。体力にはある程度の自信があり、パーティーでの移動とはちがって速度を緩める理由がないためだ。実際、一人の行動では標準タイムよりもペースが速い傾向にある。
それは過信だ。その過信が事故を招きかねないと肝に銘じている。そのため、山はあまり一人では登らず、なるべくパーティーで訪れるようにしている。
実際、本書を読む一年前には、独りで相模原の早戸大滝をアタックし、遭難しかけたことがある。
それがどれほどの危険な状況だったのかは、正直なところ、まだ甘く見ていた。本書を読むまでは。
本書を読むと、私のその時の経験は、実は相当に危険な状況だったのではないか、と思うようになった。
本書を読んだことで、そうした無謀な行動は控えなくては、と思うようになった。
また、遭難の事例を通じ、人々の山への熱意がより感じられた。それによって私に残された命がある限りは、できるだけ多くの山に訪れたいと意識するきっかけにもなった。
本書は、六例の遭難事例が載っている。また、それに加えて埼玉県警山岳救助隊の報告としてさまざまな遭難の事例がドキュメントとして収められている。
まず富士山。私自身は、まだ富士山に登ったことがない。しかも冬山に関してはスキーであちこちを訪れた程度であり、山登りを目的に置いたことはない。
スキーで訪れた際に、雪山の視野の悪さは充分すぎるほど知っているし、あえて雪山を目指そうとする意欲はない。
とはいえ、実際に雪山での滑落がどれほど想像を絶するものかは、本書の記述から感じ取れる。おそらく、スキー場の急斜面よりももっと強烈な斜面を転げ落ちていったのだろう。
夏山でもよく目にするのが、登山道の脇にありえない角度で斜面が口を開けている光景だ。あの斜面を転がり落ちたらどういうことになるか。想像するだけで恐ろしい。
本書で書かれている通り、そもそも止まることすら不可能になるのだろう。
ここで取り上げられた方は500メートルを滑落したと言う。そのスピードがどれほど強烈だったのか。
本編では教訓として富士山の冬山トレイルであれば、さほど難易度が高くないという錯覚と、下準備の不足を指摘している。また、登山届が未提出だったことや、救急療法に関する知識の不足というところも教訓として上がっている。
これらの教訓は、私にとって耳の痛い内容を含んでおり、私がもし無謀な思い付きを実行していたら間違いなく糾弾の対象となることだろう。ちょっとやばいと思った。
続いての事例は、北アルプスの北穂高岳だ。こちらは山のベテランがガレ場から滑落し、膝を強打したというものだ。
本書に載っている事例の中では最もケガとしては軽いが、膝の打撲がひどくて下山できず、ヘリコプターを呼ぶ羽目になったという。
ヘリコプターを呼んだことによる救出のための費用は相当かさみ、その額なんと440,000円だという。
山岳保険に加入していたため、実際の費用は抑えられたそうだが、山岳保険に入っていない私の身に置き換えてみると、これはまずいと痛感した。
また、ストックの重要性にも触れられているが、私はまだ持っていない。これもまずい。
続いては、大峰山脈・釈迦ケ岳の事例だ。
練馬区の登山グループ17名が、新宿から大峰山系の釈迦ケ岳に向かっていたところ、続けて2件の事故を起こしてしまう。そのうちの1人は、首の骨を折って即死するという痛ましい事故だ。
当日の天気は地元の人に言わせれば山に行くべきではない程度の雨脚だったという。一方でパーティーのリーダーであるベテランの引率者は小雨だったという。
出発時間も早いほうがよかったという批判があり、そのリーダーは時間には問題なかったと言い張っている。つまり平行線だ。
責任逃れと切って捨てることもできるが、実際の状況はその場にいた方しかわからない。ただ、それで人が死んでしまったとすれば大問題だ。
著者は大峰山の自然を守ろう会の方の意見を紹介している。事故が起きたあたりは、修験道の修行場であり仏の聖域でもある。そのような場所に人が入るべきではないと言う意見は、登山そのものへの問題提起だ。
決して登山自体が悪いわけではないと断った上で、いわゆる昨今流行している登山ツアーのあり方について一石を投じる。ここで事故が起こったコースは、二つの日本百名山に登れることから、登頂数が稼げるコースとしても人気があったという。こうした登頂数を稼ぐ考え方に問題の根がある、と。これは私自身も肝に銘じなければならない。
続いては赤城山・黒檜山だ。
数日前に訪れたばかりの冬山を急遽、一人で登ることになった遭難者の五十代女性。
数日前に訪れていたことによって冒険心を起こしてしまったのか、違う道を行ってしまった。登山届がでておらず、単独行だったので足取りも推測するしかない状態だが、迷った揚げ句に体力を消耗し、最後は滑落して動けなくなって凍死したということらしい。
自らの経験への過信と、何かあった時に備えた装備の不足とリスクマネジメントの欠如がもたらした事例だ。
ちょっと知っているから、と芽生えた冒険心に誘われるまま、違う道に分け入ってしまう。これは似たような行動をしがちな私にとって、厳に教訓としなければなるまい。
続いては、北アルプス・西穂高岳独標の事例だ。
登山には着実なステップアップの過程がある。まず近所の小さな山から始め、やがて千メートル級の山、二千メートル級の山、さらには冬山、そして単独行といったような。
その道のりは長くもどかしい。それが嫌だから着実なステップを踏まずに次々と難易度の高い山に挑戦し、そして大ケガを負う。
そんな人がいる中、本編で事故にあった方は着実で堅実なステップアップをこなしてきた方だ。準備も多すぎるほど詰め込むタイプで、事故には遭いにくいタイプ。
ところが、山荘からすぐ近くの独標へ向かう途中で滑落してしまう。そこから一気に400メートルを滑り落ちてしまう。
奇跡的に命は取り止めた後、ほんのわずかだが、つながった携帯電話を頼りに、切れ切れに遭難の一報も出すことができた。
重すぎるザックがバランスを崩した原因となったが、そのザックがクッションになり、さらにザックの中には連絡手段や遭難時の備えが入っていたことが功を奏した。
なによりも、この方が生きて社会復帰してやる、との強い意志を持っていたことが、生き延びた原因だという。これもいざとなった場合に覚えておかねばなるまい。
続いては、南アルプス・北岳の遭難事例がとり上げられる。
この編で語るのは滑落した当人ではなく、それを間近で目撃し、救助にも携わった方だ。
この時期の北岳にはキタダケソウという可憐な花が咲き乱れ、それを目当てに訪れる人も多いのだとか。だが、六月末とはいえまだ雪渓は残っている状態。そこをアイゼンやピッケルもなしで向かおうとする無謀な行為から、このような事故が起こる。夏山とはいえ、準備は万端にする。思い込みだけで気軽に訪れることの危険を本編はよく伝えている。
最後は、埼玉県警山岳救助隊があちこちの事例を挙げている。
ここであがっている山はそれ程の高峰ではない。
それでも、ちょっとした道迷いや油断によって転落は起こりうる。
高峰に登ろうとする際は心の準備に余念がないが、低山だとかえって気楽な気持ちで向かってしまうため、事前に山に行ったことを教えずに向かってしまうことはありそうだ。そうなると遭難の事実も分からず、救助隊も組織されない。
そうやって死んでいった人の多さを、本編は語っている。
多分、私がもっとも当事者になりそうなのが、ここで取り上げられた数々の事例だろう。
こうして本書を読み終えてみると山の怖さが迫ってくる。
本書を読む少し前、私は十数人のパーティーの一員として至仏山に登った。
そこから見下ろす尾瀬は格別だったが、雲の動きがみるみるうちに尾瀬の眺望を覆い隠してしまい、それとともに気温がぐっと下がったことも印象に残っている。これが山の怖さの一端なのだろう。
私はまだ自分が山の本当の怖さを知らないと思っている。また、私は自分の無鉄砲な欠点を自覚しているため、独りで無謀な登山はしないように心がけている。
だが、その一方で私は一人で滝を巡りに行くことが多い。多分、私にとって危険なのは滝をアタックしてアクシデントに遭遇した場合だろう。
滝に向かう時、おうおうにして私は身軽だ。遭難時のことなど何も考えていない。
冒頭に書いた早戸大滝の手前であわや遭難しかけた事など、まさに命を危険にさらした瞬間だったといえる。
早戸大滝は今までもなんどもチャレンジし、その度に引き返す勇気は発揮できている。
この引き返す勇気を今後も忘れないためにも、本書はためになった。
‘2019/9/9-2019/9/10