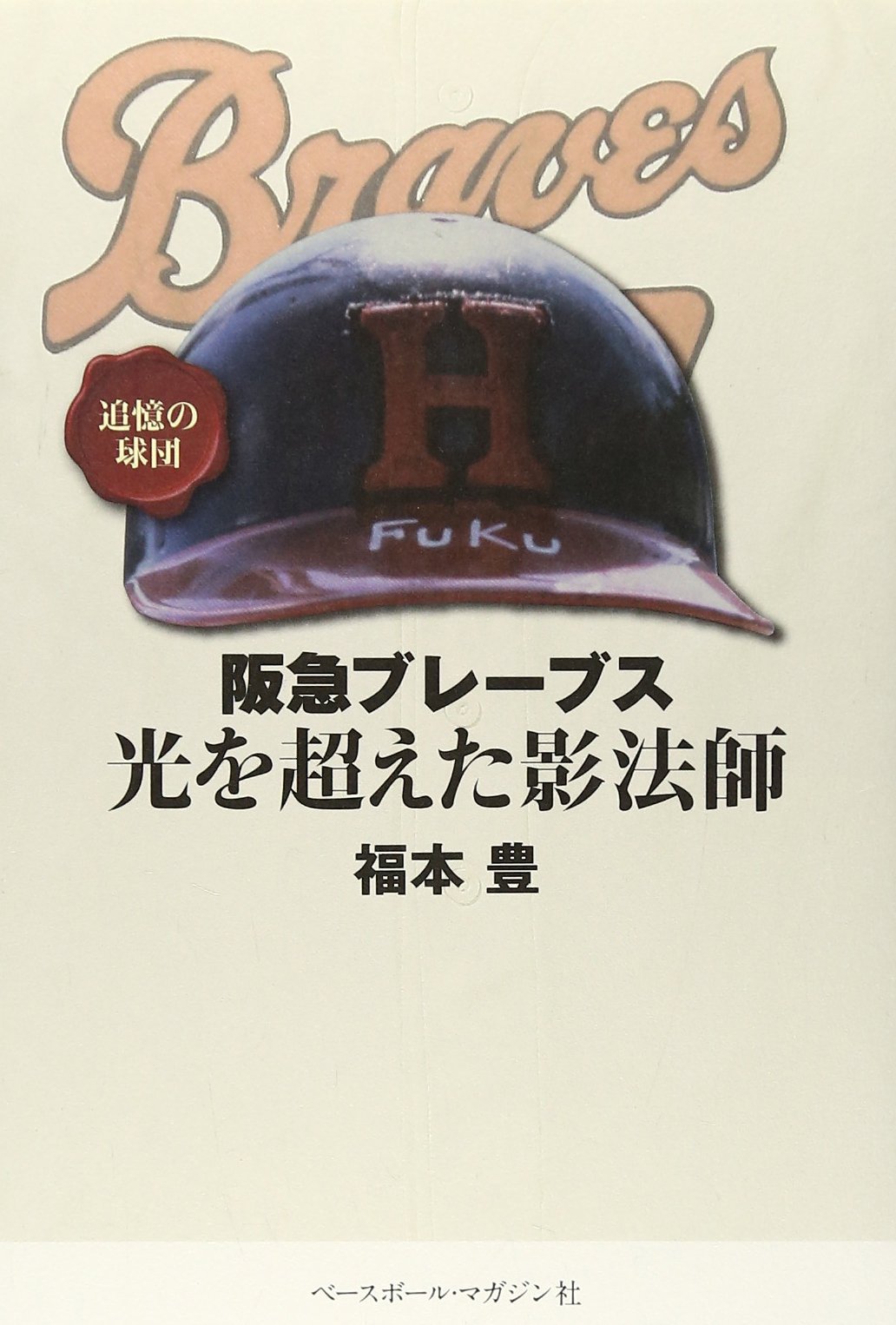
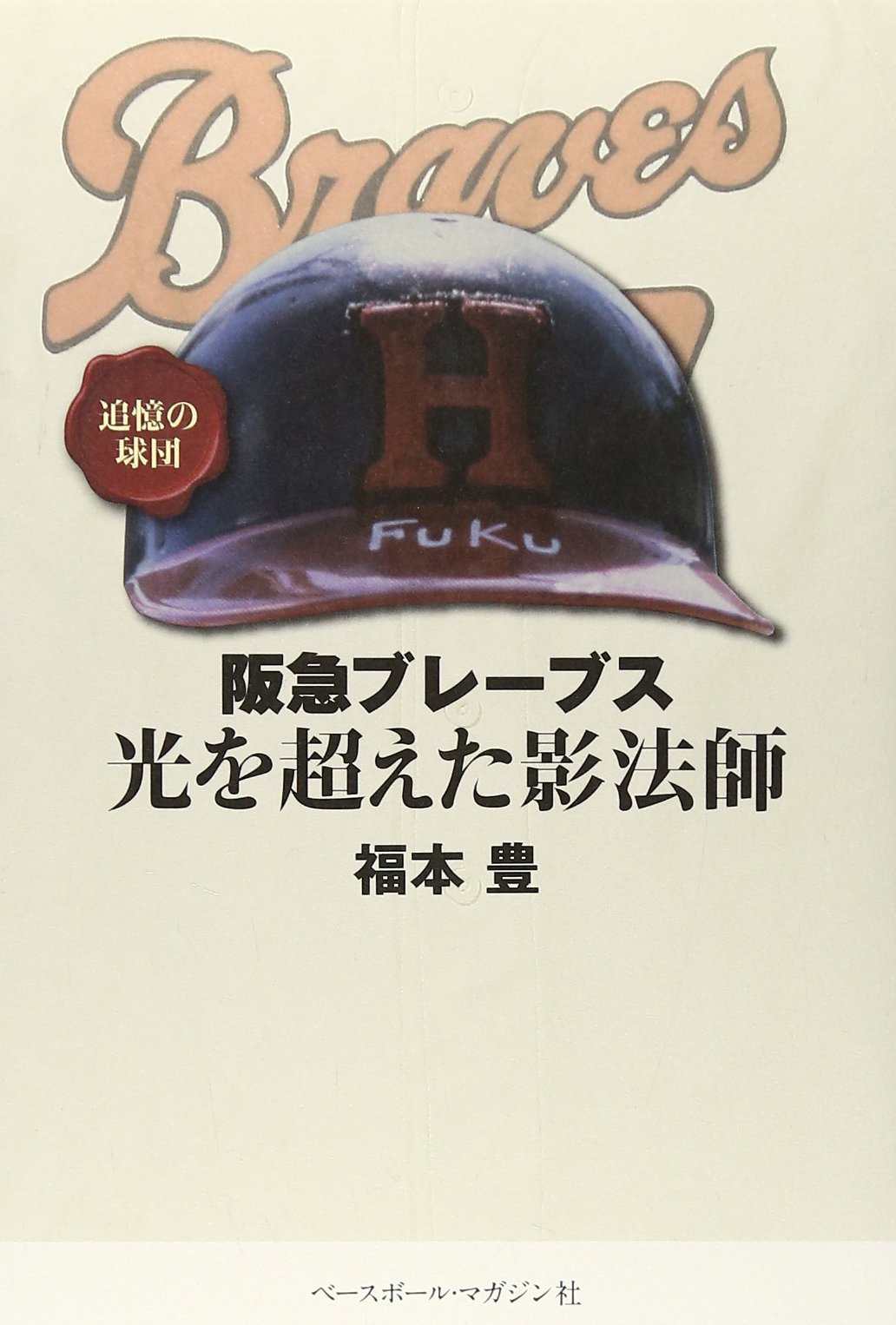
西宮で育った私にとって、阪急ブレーブスはなじみ深い球団だ。
私の実家は甲子園球場からすぐ近くだが、当時、阪急戦を見に西宮球場に行く方が多かった。阪神の主催ゲームはなかなかチケットが取れなかったためだろう。
よく父と西宮球場の阪急戦を観に行ったことを覚えている。
西宮球場や西宮北口駅のあたりは、当時も今も西宮市の中心だ。家族と買い物にしょっちゅう訪れていた。
そのため、子供の頃の私の心象には、西宮球場付近の光景がしっかりと刻まれている。
ニチイ界隈の賑わう様子。西宮北口駅のダイアモンド・クロッシングを通り過ぎる電車が叩く音。そして西宮球場で開催される阪急戦の雰囲気。
時期はちょうど1984年ごろだったと思う。
それから35年以上が過ぎた。
いまや西宮北口駅の周辺は阪神・淡路大地震を境にすっかり変わってしまった。ニチイもダイアモンド・クロッシングも西宮球場も姿を消した。
もちろん、本書で取り上げられる阪急ブレーブスも。
すぐ近くの甲子園球場で行われる阪神戦の熱気とは裏腹に、阪急戦の雰囲気は寂しいものだった。
1984年、阪急ブレーブスは球団の歴史上で、最後のパ・リーグ優勝を成し遂げた。
昭和40年代から続いた黄金期の最後の輝き。
本書の著者である福本豊選手。山田久志、簑田浩二、加藤英司、ブーマー・ウェルズと言った球史に残る名選手の数々。上田監督が率いたチームには、今井雄太郎、佐藤義則、山沖之彦という忘れがたい名投手たちもいた。弓岡敬二郎や南牟礼豊蔵といった選手の活躍も忘れてはなるまい。
こうした球史に名を残す選手を擁しながら、西宮球場で行われるナイターの試合には、いつもわずかな観客しかいなかった。
甲子園球場のにぎやかな応援風景とあまりにも違う西宮球場の寂しさ。それは小学生の私にとても強い印象を残した。
今日、阪急ブレーブスの栄華をしのぼうと思ったら、阪急西宮ガーデンズの5階のギャラリーを訪れると良い。
そこに飾られた幾つものトロフィーや銅像、優勝ペナント、著者を初めとした野球殿堂に選ばれた13選手をかたどったレリーフからは、球団の歴史の片鱗が輝いている。
だが、私が実家に帰省し、阪急西宮ガーデンズに訪れるたび、このギャラリー内のブレーブスの記念コーナーが縮小されているように思える。
阪急西宮ガーデンズが出来た当初、記念コーナーはギャラリーのかなりのスペースを占めていたように思う。
スペースの縮小は、阪急グループにとっての阪急ブレーブスの地位が低下していることをそのまま表している。
著者はこの現状も含め、阪急ブレーブスが忘れられることを危惧したのだろう。それが本書を著した動機だったと思われる。
かつてあれほど強かったにもかかわらず、強さと人気が比例しなかった球団。黄金期を迎える前は灰色の球団と言われ続け、黄金期を迎えても阪神タイガースには人気の面ではるかに及ばなかった球団。
本書は著者がブレーブスに入団する時点から始まる。悲運の名将と呼ばれた西本監督の下、黄金期への地固めをするブレーブス。
著者と著者の同期である加藤英司選手が、プロ生活の水に慣れていく様子が書かれる。
著者が入団する前年に、阪急ブレーブスは創立32年目にして初優勝を果たした。
当時は米田哲也投手、足立光宏投手、梶本隆夫投手が健在で、野手もスペンサー、長池選手といった選手がしのぎを削っていた。
そうそうたる選手層に加わったのが著者と加藤選手、そして山田投手。
そこで揉まれながら、著者は走攻守に存在感を発揮して行く。
著者が入った年、ブレーブスはパ・リーグを2連覇し、最初の黄金時代を迎える。
著者の成績に比例してブレーブスは強くなっていく。だが、V9中の巨人にはどうしても勝てない。そんな挫折と充実の日々が描かれる。
ブレーブスの選手層は、大橋選手、大熊選手、島谷選手といった選手の入団によってさらに厚くなる。
それまでパ・リーグといえば、南海ホークスか西鉄ライオンズ、大毎オリオンズの三強だった。そこに、黄金期を迎えたブレーブスが割り込む。
他の強豪チームに引けを取らない力を蓄えたブレーブスは、1967年から1984年までの18シーズンにパ・リーグを10度制し、3度日本一になっている。その間にはパ・リーグ3連覇を二度果たした。2度目の3連覇ではその勢いのまま、セ・リーグのチームを破り、三年連続で日本一の美酒を味わう偉業を成し遂げている。
昭和五十年代に限っていえば、ブレーブスは日本プロ野球でも最強のチームだったと思う。さらにいえば、わが国の野球史を見渡しても屈指のチームだったと言える。
著者はそのチームに欠かせない一番打者として、華々しい野球人生を送った。
二塁打数、安打数、盗塁数など著者の築き上げた成績は、いまも日本プロ野球史に燦然と輝き続けている。通算1065盗塁に至っては、当分の間、迫る選手すら現れないことだろう。
山田投手が日本シリーズで王選手に逆転スリーランを打たれたシーンや、昭和53年の日本シリーズがヤクルトの大杉選手のホームランをファウルだと主張した上田監督によって1時間19分の間、中断したシーン。
阪急ブレーブスが球史に残したエピソードは今もプロ野球の記憶に残り続けている。
それなのに、阪急は身売りされてしまう。
「9月上旬、南海ホークスがダイエーへの球団譲渡を発表した。かねてから噂になっていたので、僕はそれほど驚かなかった。86年以降の阪急ブレーブスは、念願だった年間100万人の観客動員を続けていた。身売りされた南海は、一度たりとも大台へ届かなかった。ブレーブスのナインにとって、南海ホークスの消滅は、対岸の火事にしか見えなかった。」(190ページ)
著者が危惧するように、売却と同時にブレーブスの歴史は記憶の彼方に遠ざかろうとしている。
冒頭に書いた通り、当の阪急グループからも記念コーナーの縮小という仕打ちを受け、ブレーブスの栄光はますます元の灰色に色あせてつつある。
阪急グループについては、宝塚ファミリーランドの跡地の扱いや、宝塚歌劇団の内部運営など、私の中でいいたい事はまだまだある。
著者はあとがきで宝塚歌劇のファンになった事を書いている。ベルばらブームによって宝塚歌劇団が息をふきかえした時期、くしくも阪急ブレーブスも黄金期を迎えた。
だが、その後の両者に訪れた運命はくっきりと分かれた。痛々しいほどに。
宝塚歌劇は東京に進出し、今では公演の千秋楽は宝塚大劇場、続いて有楽町の宝塚劇場の順に行われるという。要は公演のトリを東京に奪われているのだ。
東京という華やかな日本の中心に進出することに成功し、徐々にそちらに軸足を移しつつあるように見える歌劇団。
その一方で日本シリーズで三連覇したにもかかわらず、そして、徐々に観客数の向上が見られたにもかかわらず、身売りされた阪急ブレーブス。
人気のないパ・リーグで存続し続ける限り、日本の中心どころか、関西の人気球団にもなれないと判断した経営サイドに切り捨てられた悲運の球団。
たしかに、同じ西宮市に球団は二つも要らなかったかもしれない。
阪急ブレーブスが阪神タイガースの人気を凌駕することは、未来永劫なかったのかも知れない。
それでも、県庁所在地でもない一都市の西宮市民としては、二つのプロ野球球団を持てる奇跡に満足していた。そして、いつかは今津線シリーズが開かれることを待ち望んでいられた。
私は今もなお、ブレーブスを売却した判断は拙速だったと思う。
阪神間で育った私から見て、小林一三翁の打ち立てた電鉄経営の基本を打ち捨て、中央へとなびく今の阪急グループには魅力を感じない。
東京で仕事をする私から見ると、東京で無理に存在感を出そうとする今の阪急グループからは、ある種の痛々しさすら覚える。
たしかに経営は大切だ。赤字を垂れ流す球団を持ち続け、関西でも奥まった宝塚の地に遊園地と劇団を持っているだけでは、グループに発展の余地はないと考える心情もわかる。
だが、中央への進出に血道を上げる姿は、東京に住むものから見ると痛々しい。
それよりは、関西を地盤とし、球団と歌劇団と遊園地を維持し続けた方がはるかに気品が保てたのではないだろうか。東京一極集中の弊害が言われる今だからこそ。
それでこそ阪急、それでこそ逸翁の薫陶が行き渡った企業だと愛せたものを。
私のように歌劇団の運営の歪みを知る者にとっては、順調に思える歌劇団の経営すら、無理に無理を重ねているようにしか見えない。
著者があとがきに書いた歌劇団への愛着も、阪急ブレーブスという家を喪った痛みの裏返しであるように思う。
著者が本当に言いたいこと。それは、阪急グループに歴史を大切にしてほしい、ということではないだろうか。
タイトルにある影法師がブレーブスだとして、ブレーブスが超えた光とは何か。そのタイトルにこそ、著者の願いが込められているはずだ。
‘2019/5/22-2019/5/22






