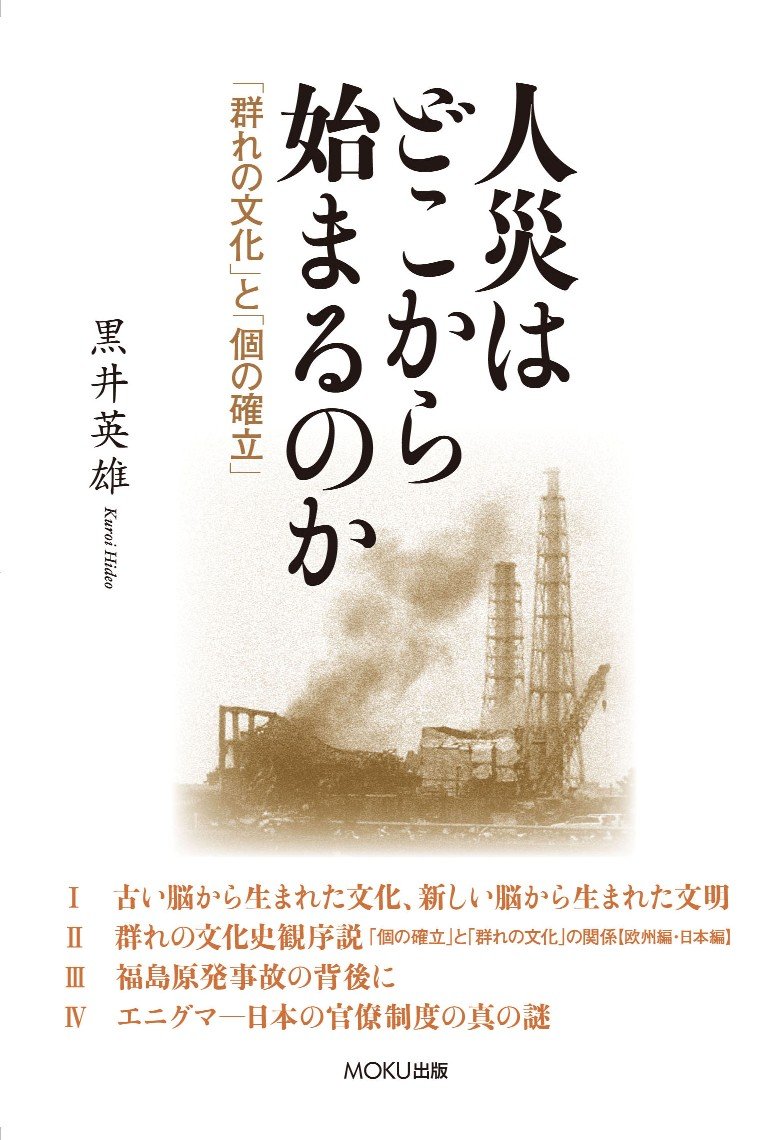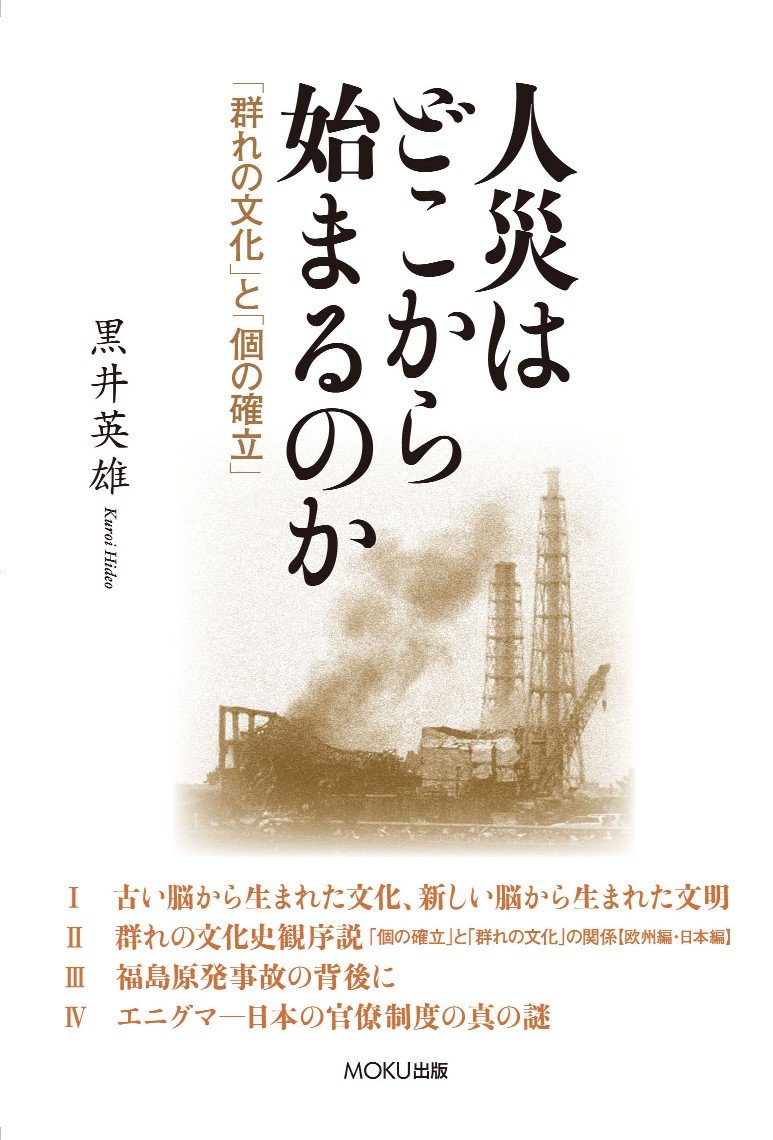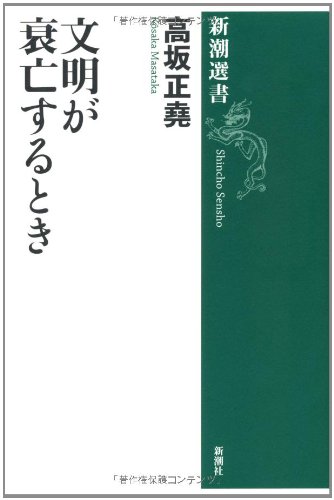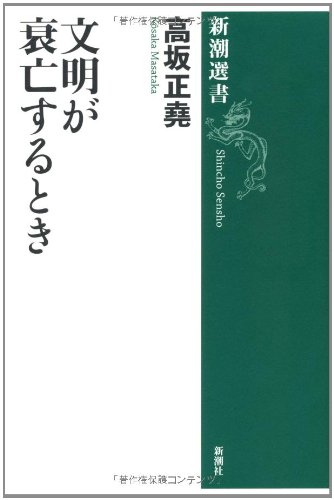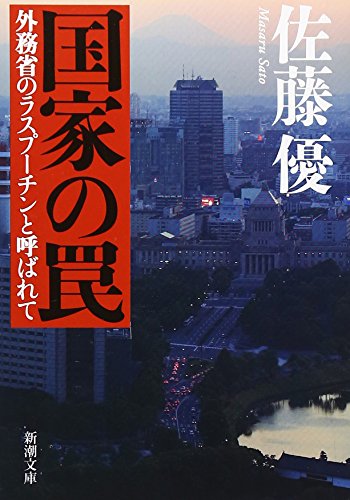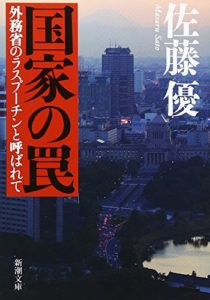私はあまり経済系の小説は読まない。
本書は、淡路島の兵庫県立淡路景観園芸学校のイベントに仕事で参加した際、「お好きにお持ち帰りください」コーナーで手にとったものだ。以来、二、三年積ん読になっていた。
そのため、本書については私の中には何の知識もなかった。著者の作品ももちろん初めて読む。
だが、本書は、とても読み応えのある一冊だった。
大手銀行同士の合併に際し、財務省に対する便宜を図ってもらうために贈収賄があったのではないか。その疑惑が、東京地検特捜部の捜査対象だった。そんな中、財務省の官僚である大貫が謎の死を遂げた。
その大貫を検事として取り調べていた後鳥羽は、贈収賄の実態についてさらなる調査を進める。汚職疑惑から明らかになる謎とは。それが本書の大まかなあらすじだ。
官僚や検事としての生き方、そして身の処し方。外部から見た時、どちらもさほど違いがないように思える。もちろん、当事者にとってみればそれはナンセンスな視点のはず。
私のような技術者でさえ、関わる職種によって職務の内容が大きく違うのは当たり前だ。技術者だからなべて同じと思われては困る。検事と官僚を同じ枠でくくることも同じ誤りに違いない。
ただ、一つだけ言えることがある。それは、誰もが目の前の任務に専念し、目の前の難問を解決しようと仕事に取り組んでいることだ。
後鳥羽には家族もいる。大貫にも家族がいる。
だが、肥大した利権と権力にまみれた世界は、家族の憩いや願いなど一顧だにしない。彼らのささやかな平和を一蹴するかのように、陰険な手が危害を加えてくる。圧力や妨害が当たり前の任務を遂行する彼らを駆り立てるものは何だろうか。
私自身の考えや生き方は、本書に登場する男たちの多くとは少しだけ異なっている。だからこそ、本書の世界観は新鮮だった。もちろん、このような小説は今までに何度も読んだことがある。ただ、それは私が何も分かっていない若い頃。
今の私は経営者である。ある程度自由が効くワークスタイルで働けている。今の私のワークスタイルは、検事や官僚のような生き方とは離れてしまった。
だが、私は本書に出てくる男たちの働き方を全て否定しようとは思わない。
仕事に熱を入れる彼らの姿は美しい。
日本の高度経済成長期に、本書に出てくるような男たちが黙々と仕事をしたからこそ、日本は世界史上でも稀な復興を成し遂げた。それは分かっているし、私が先人の成果の上で暮らしていることも理解している。
著者は彼らの姿を硬質で冷静な筆致で描く。
銀行員は規模を追い求める。銀行を大きくするためなら手段は問わない。
政治家は愛想よく振る舞い、日本を導く大志を語る。その裏で権力抗争に明け暮れる。
官僚は今を生きることに必死の国民や次の選挙に気もそぞろの政治家とは違い、数十年先を見据えた国家の大計のためと建前を振りかざす。
検事は権力の悪を暴く名目の元、疑惑に向けて捜査を怠らない。
誰もがそれぞれの仮面をかぶり、その仮面に宿命づけられた任務を遂行する。そして長年、仮面を被り続けているうちに、それが習性となってはがれなくなった仮面に気づく。
それを自覚しながら、それぞれの信条に殉じて任務に向かう。
著者はこうした人々を客観的に、そしてバランスよく描いていく。
捜査する後鳥羽は、大貫が改革派議員と勉強会を開いていた事実を知る。彼は何かを探していた。それが、大貫と大貫を追うように死んだ改革派議員が殺された原因ではないか。後鳥羽はそう当たりをつけ、調査を進める。
やがて彼の家族や彼自身にも危害が及ぶ中、彼は大貫が追っていた対象とそれが指し示す事実に行き当たる。
その何かはここでは詳細に書かない方が賢明だろう。本書を読む方の興味を殺いでしまう。
だが、それは決して荒唐無稽な陰謀論の産物ではない。
とても説得力があるし、それがなぜ大貫の命を奪ったのかも理解できる。
ちょうど私が初めて新聞を読み始めた頃、当時の新聞の一面には二つの品物が連呼されていた。牛肉とオレンジ。
今の日本をさして、財政の危機を指摘する論は頻繁に見かける。財政の支出に占める国債の利息の割合や、収入を国債に頼っている現状。
体力を顧みない国債の乱発は、やがて日本を破綻させる。そのような悲観的な論を唱える論者は多い。
だが本書を読めば、財務省が国債の乱発に余裕をかましていられるのかに得心が行く。私の勉強不足なのかもしれないが、今までに本書に書かれたような切り口で日本の財政を切り取った論を見かけたことがなかった。
おそらく私は、勉強不足で半可通の代表だろう。大貫が見つけた問題意識を今まで考えたことすらなかった。そうした半可通が官僚や政治家の思い描く未来とは逆の、的を外した論をSNSなどで書き散らしている。
官僚や検事はそうした浮ついた論とは一線を画し、目の前の大義に向けて能力を発揮せんとしている。
本書を読み、官僚や検事を駆り立てるものが何かについておぼろげながら理解できたように思う。
改めて今、インターネットで国債の状態を見てみた。すると、国債は相変わらず同じ状況が続いているようだ。
今、日本の財政が破綻したら果たしてどうなるのだろうか。いや、そもそも破綻することはないような気がする。
このような重要なことを知らずに、失われた30年などとドヤ顔で語っていたとすれば笑止千万だ。私は自らの無知に心から反省するとともに、本書を読んで襟を正す思いになった。
‘2020/04/18-2020/04/20