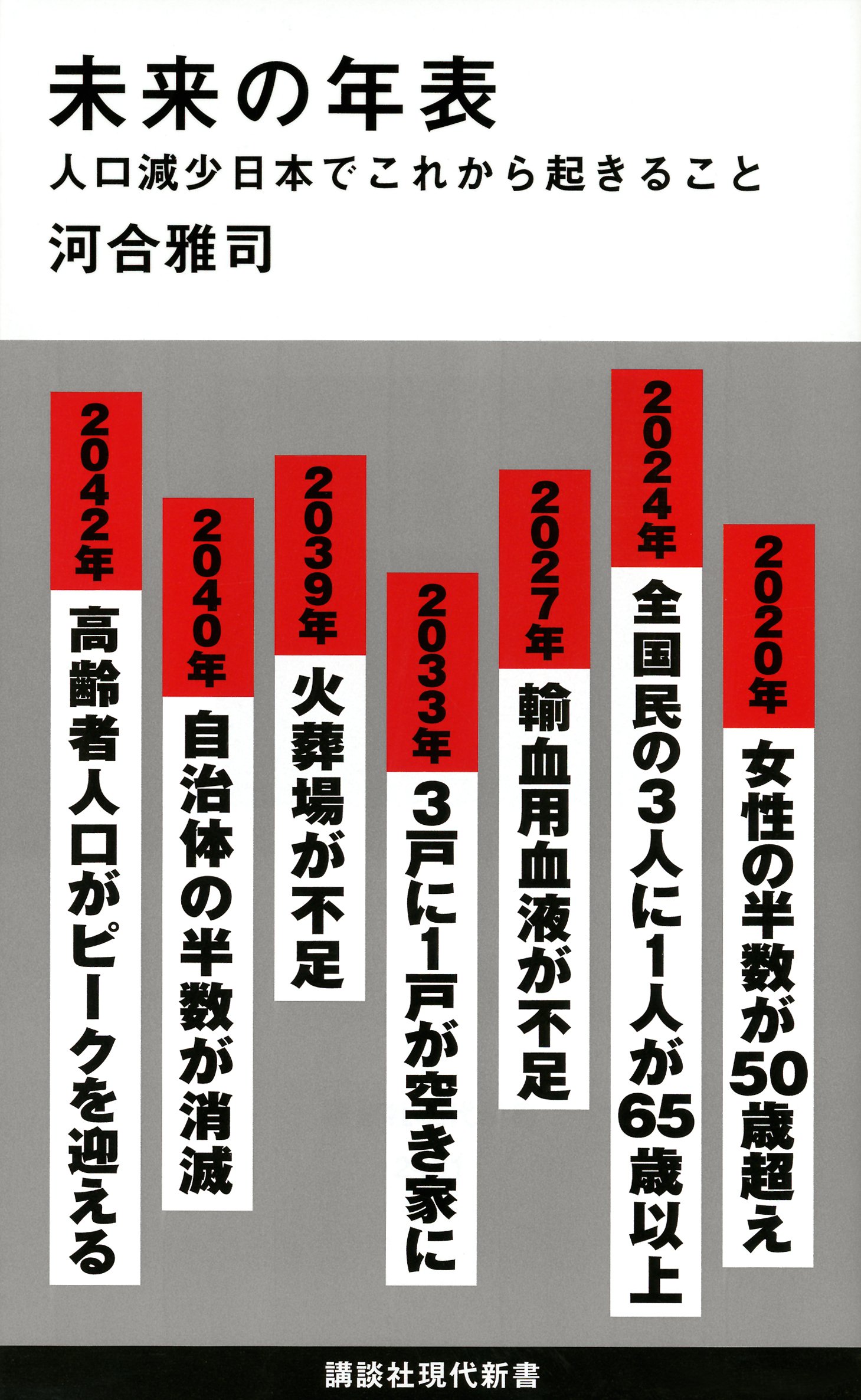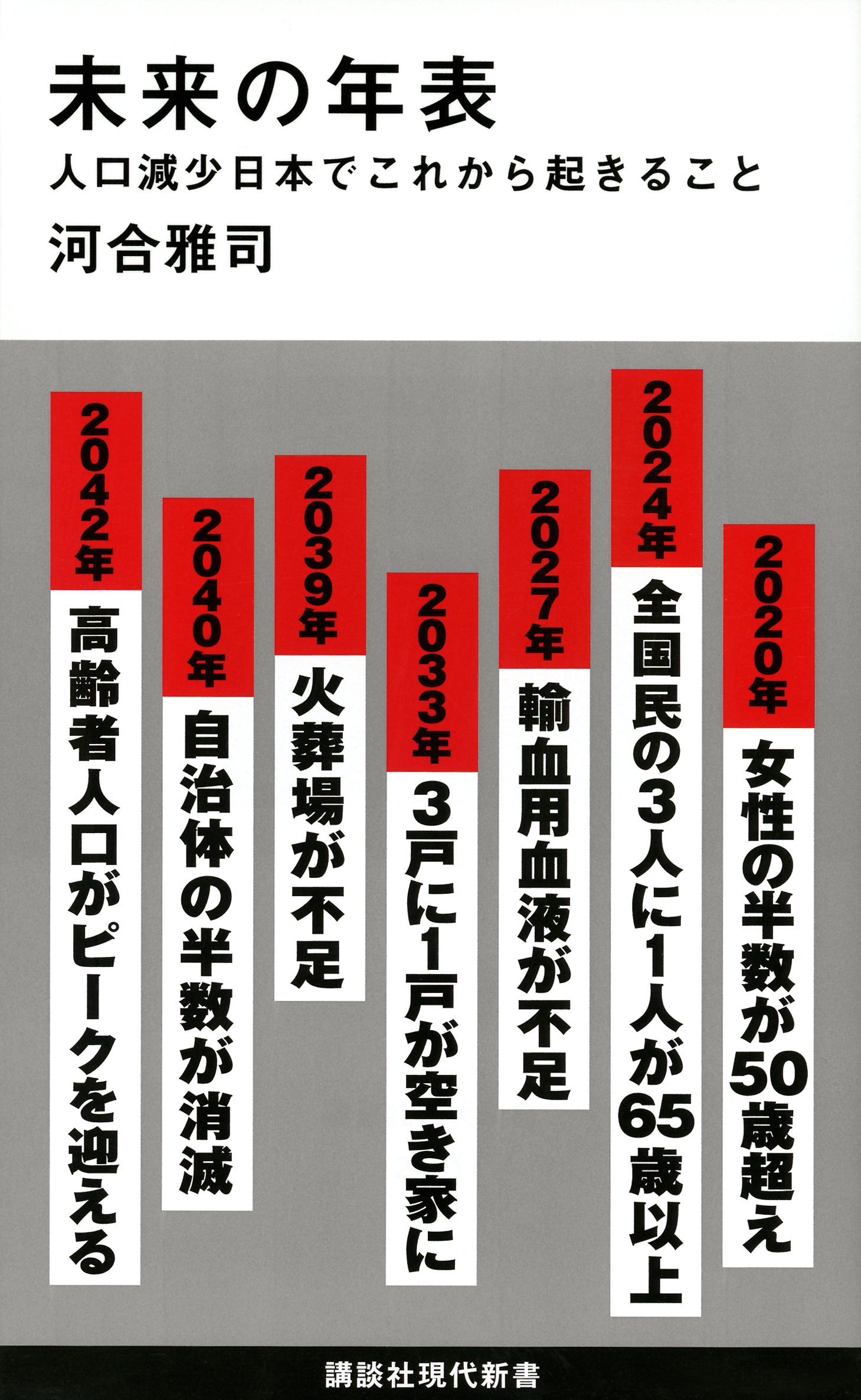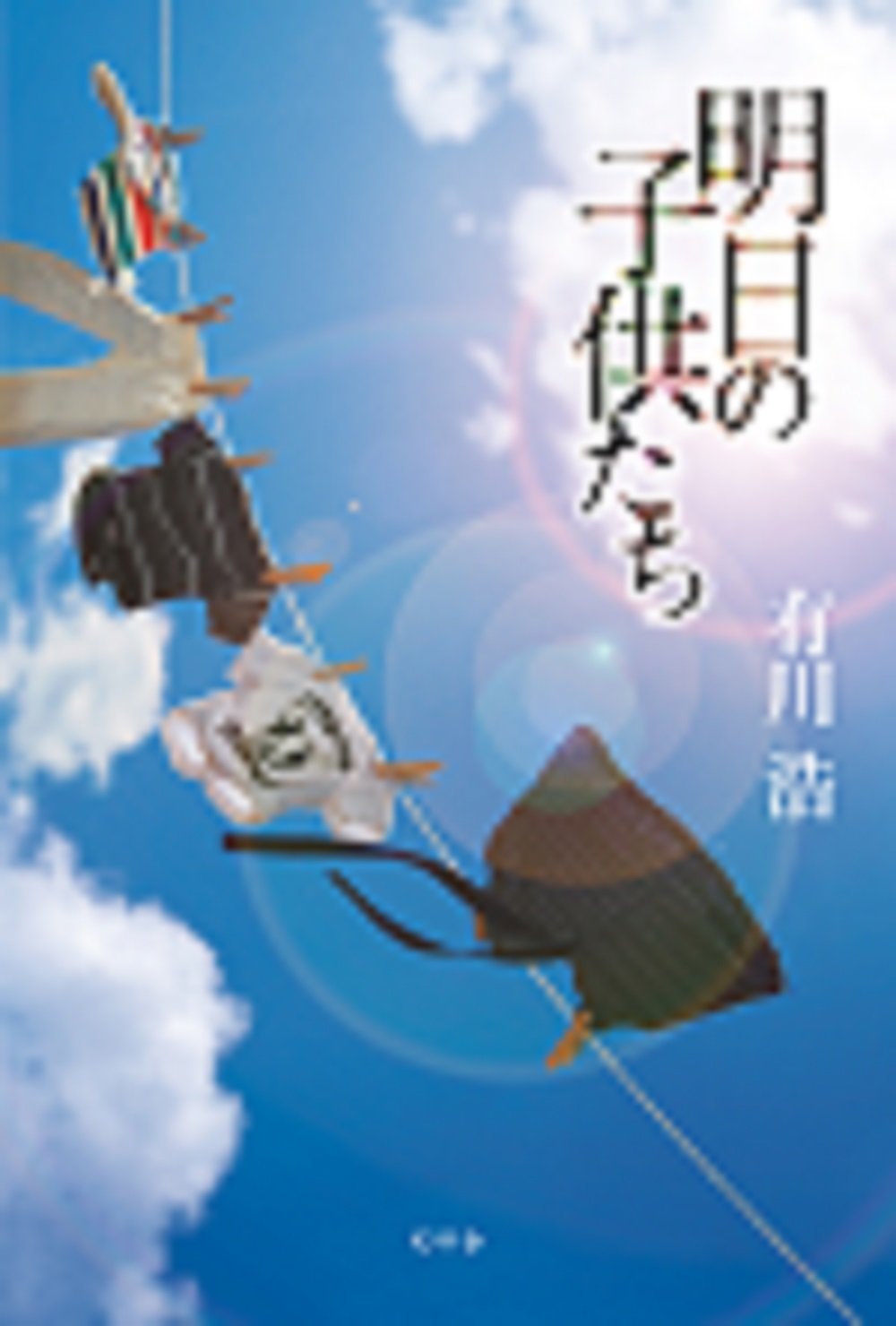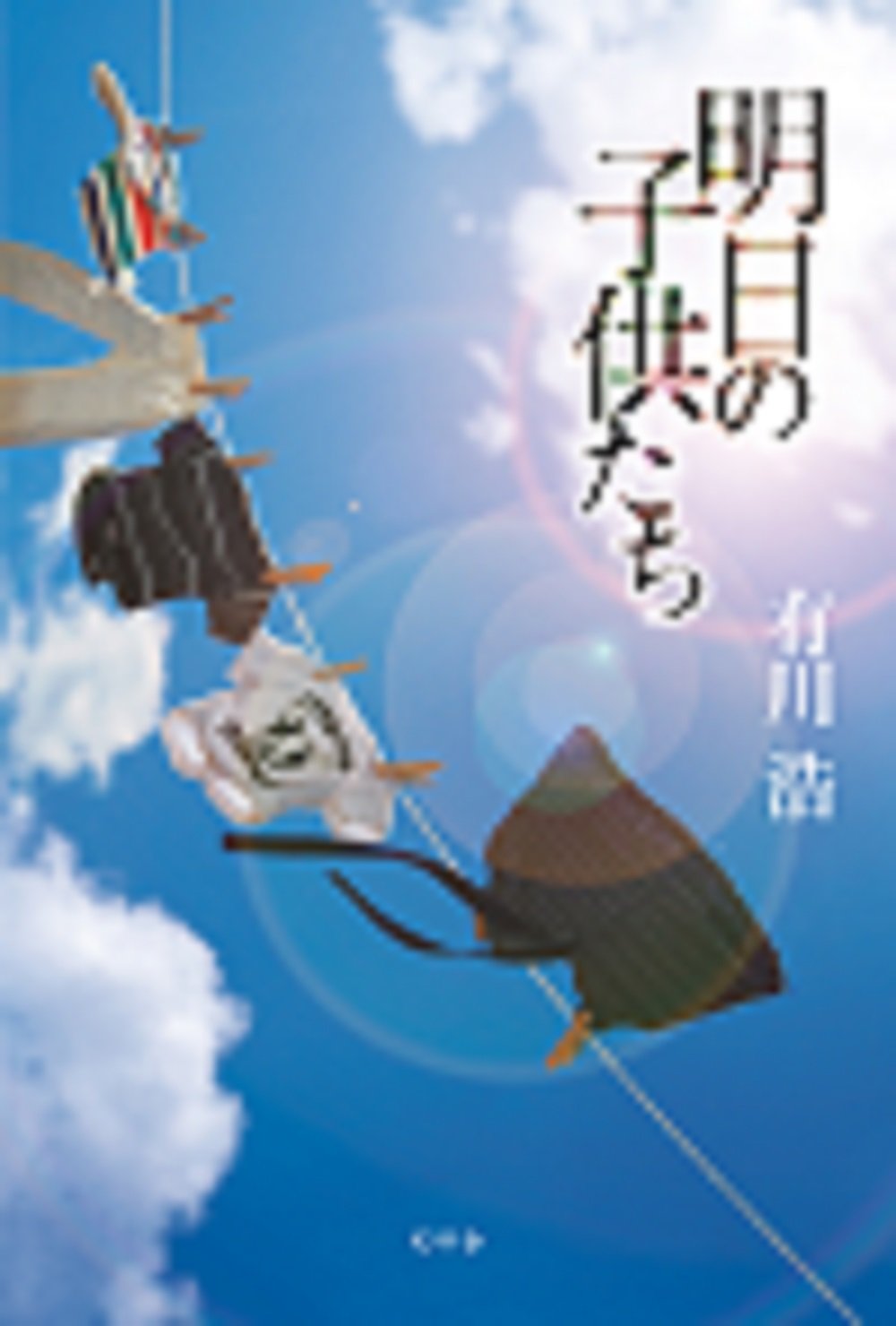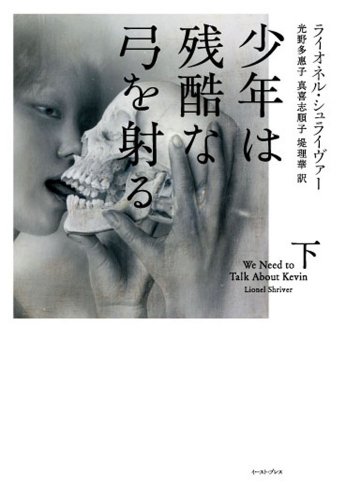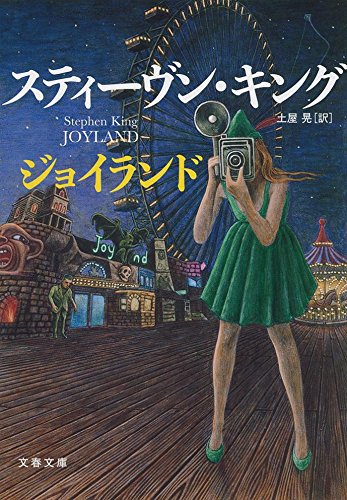『教場』で文名を高めた著者。
短編のわずかな紙数の中に伏線を張り巡らせ、人の心の機微を描きながら、意外な結末を盛り込む手腕には驚かされた。
本書もまた、それに近い雰囲気を感じる短編集だ。
本書に収められた七つの短編の全てで、著者は人の心の暗い部分の裏を読み、冷静に描く。人の心の暗い部分とは、人の裏をかこう、人よりも優位に立とうとする人のサガだ。
そうした競争心理が寄り集まり、混沌としてしまっているのが今の社会だ。
相手に負けまい、出し抜かれまい。その思いはあちこちで軋轢を生み出す。
そもそも、人は集まればストレスを感じる生き物だ。娯楽や宗教の集まりであれば、ストレスを打ち消すだけの代償があるが、ほとんどの集まりはそうではない。
思いが異なる人々が集まった場合、本能として競争心理が生まれてしまうのかもしれない。
上に挙げた『教場』は、警察学校での閉じられた環境だった。その特殊な環境が物語を面白くしていた。
そして本書だ。本書によって、著者は一般の社会のあらゆる場面でも同じように秀逸な物語が書けることを証明したと思う。
「波形の声」
学校の子供達の関係はまさに悪意の塊。いじめが横行し、弱い子どもには先生の見えない場所でありとあらゆる嫌がらせが襲いかかる。
小学校と『教場』で舞台となった警察学校。ともに同じ「学校」の文字が含まれる。だが、その二つは全く違う。
本編に登場する生徒は、警察官の卵よりも幼い小学生たちだ。そうした小学生たちは無垢であり、高度な悪意は発揮するだけの高度な知能は発展途上だ。だが、教師の意のままにならないことは同じ。子どもたちは自由に振る舞い、大人たちを出し抜こうとする。先生たちは子どもたちを統制するためにあらゆる思惑を働かせる。
そんな中、一つの事件が起こる。先生たちはその問題をどう処理し、先生としての役割をはたすのか。
「宿敵」
高校野球のライバル同士が甲子園出場をかけて争ってから数十年。
今ではすっかり老年になった二人が、近くに住む者同士になる。かつてのライバル関係を引きずってお互いの見栄を張り合う毎日。どちらが先に運転免許証を返上し、どちらが先に車の事故を起こすのか。
家族を巻き込んだ意地の張り合いは、どのような結末にいたるのか。
本編は、ミステリーや謎解きと言うより人が持つ心の弱さを描いている。誰にも共感できるユーモアすら感じられる。
こうした物語が書ける著者の引き出しの多さが感じられる。とても面白い一編だ。
「わけありの街」
都会へ送り出した大切な息子を強盗に殺されてしまった母親。
犯人を探してほしいと何度も警察署に訴えにくるが、警察も持て余すばかり。
子供のことを思うあまり、母親は息子が住んでいた部屋を借りようとする。
一人でビラを撒き、頻繁に警察に相談に行く彼女の努力にもかかわらず、犯人は依然として見つからない。
だが、彼女がある思惑に基づいて行動していたことが、本編の最後になって明かされる。
そういう意外な動機は、盲点となって世の中のあちこちに潜んでいる。それを見つけだし、したたかに利用した彼女への驚きとともに本編は幕を閉じる。
人の心や社会のひだは、私たちの想像以上に複雑で奥が深いことを教えてくれる一編だ。
「暗闇の蚊」
モスキートの音は年齢を経過するごとに聞こえなくなると言う。あえてモスキート音を立てることで、若い人をその場から追い払う手法があるし、実際にそうした対策を打っている繁華街もあるという。
その現象に着目し、それをうまく人々の暮らしの中に悪巧みとして組み込んだのが本編だ。
獣医師の母から折に触れてペットの治療や知識を伝授され、テストされている中学生の息子。
彼が好意を持つ対象が熟女と言うのも気をてらった設定だが、その設定をうまくモスキート音に結びつけたところに本編の面白みがあると思う。
「黒白の暦」
長年の会社でのライバル関係と目されている二人の女性。今やベテランの部長と次長のポジションに就いているが、一人が顧客への対応を間違えてしまう。
会社内の微妙な人間関係の中に起きたささいな出来事が、会社の中のバランスを揺るがす。
だが、そうした中で相手を気遣うちょっとした振る舞いが明らかになり、それと同時に本編の意味合いが一度に変わる。
後味の爽やかな本編もなかなか面白い。
「準備室」
普段から、パワー・ハラスメントにとられかねない言動をまき散らしている県庁職員。
県庁から来たその職員にビクビクしている村役場の職員たち。
その関係性は、大人の中の世界だからこそかろうじて維持される。
だが、職場見学で子どもたちがやってきた時、そのバランスは不安定になる。お互いの体面を悪し様に傷つけずに、どのように大人はバランスを保とうとするのか。
仕事の建前と家庭のはざまに立つ社会人の悲哀。それを感じるのが本編だ。
「ハガニアの霧」
成功した実業家。その息子はニートで閉じこもっている。そんな息子を認めまいと辛辣なことをいう親。
そんなある日、息子が誘拐される。
その身代金として偶然にも見つかった幻の絵。この絵を犯人は誰も取り上げることができないよう、海の底に沈めるように指示する。
果たしてその絵の行方や息子の命はどうなるのか。
本書の中ではもっともミステリーらしい短編が本編だ。
‘2020/08/13-2020/08/13