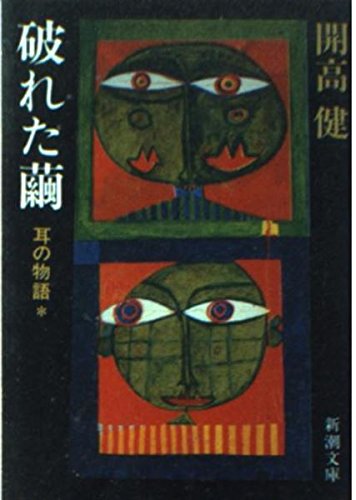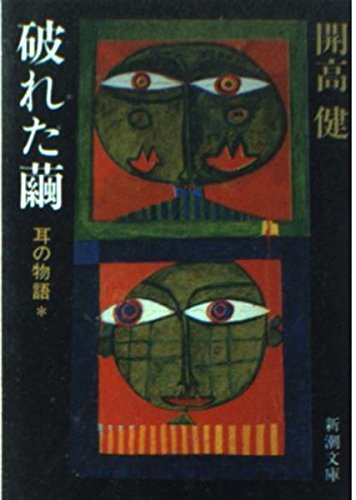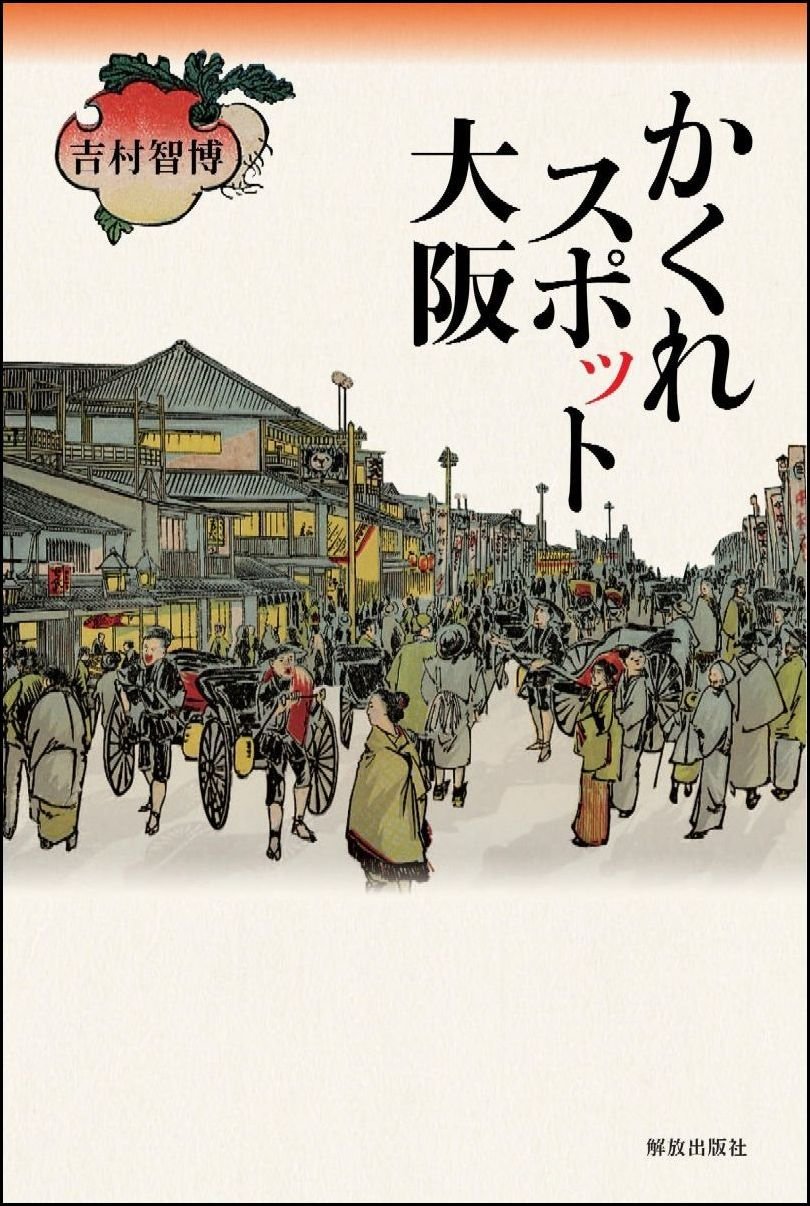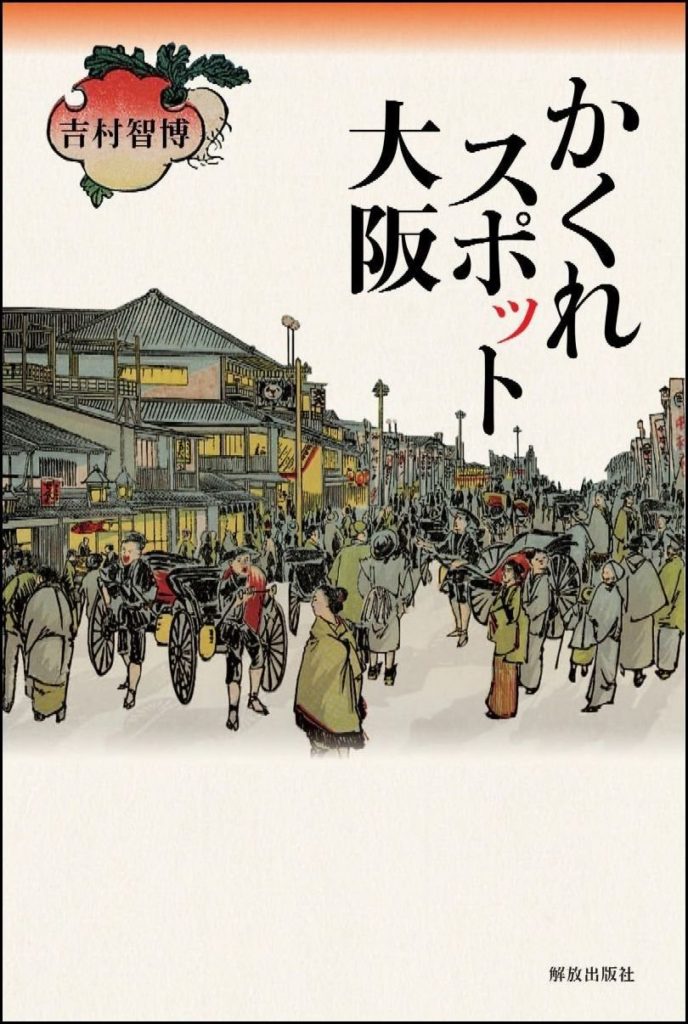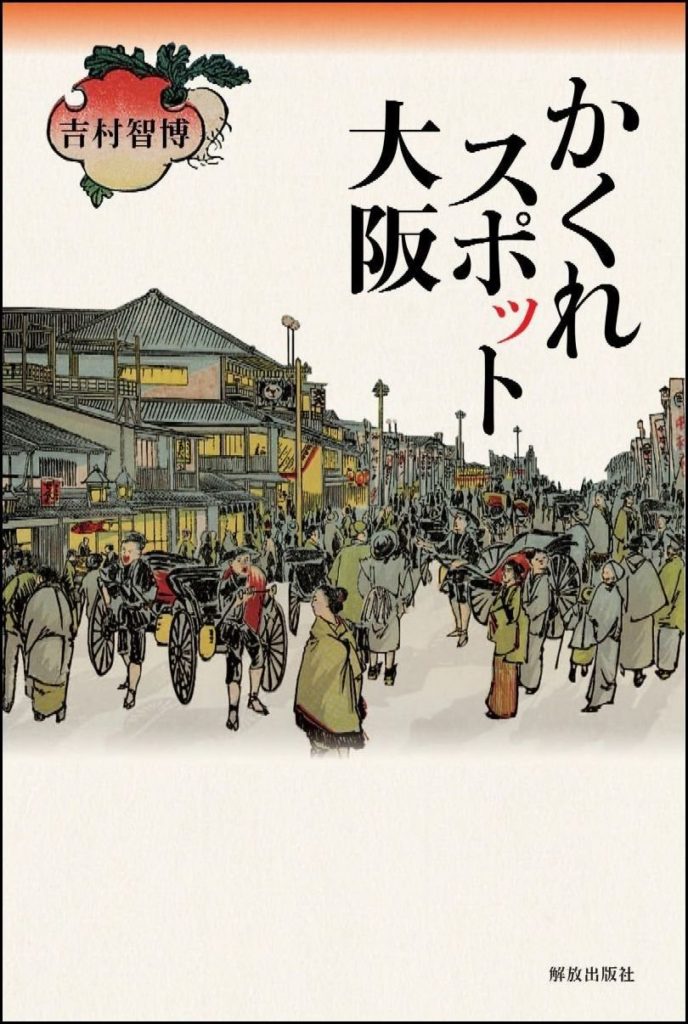
本書は大阪人権博物館ことリバティおおさかで購入した。リバティおおさかを訪れたのは、私の記憶が確かならば二度目のはず。前回の訪問は私がまだ学生の頃だった。あれから二十三年がたち、それなりに社会経験を積んだ私。だが、リバティおおさかとその近辺の風景から受けたこの度の印象は当分消えないだろう。
今回、リバティおおさかを訪れる前に南海汐見橋線の沿線を歩いた。汐見橋駅、芦原橋駅、木津川駅。これらの駅にはだいぶ以前にも訪れたことがある。その時はただひなびた田舎駅、という印象しか受けなかった。だが、久々に訪れた私の目に映ったのはまったく違うイメージだ。特に木津川駅から発せられていた荒廃のメッセージは非日常の極み。その強烈さは私に大いなる印象を刻みこんだ。
今の私は東京で暮らしている。都心も頻繁に訪れる。世界一ともいえる乗降客数を誇る新宿駅を筆頭に活気に満ちた駅の数々。それらの駅は頻繁に改築され、ゴールがないかのように洗練され続けている。私はまた、駅鉄と称して各地の駅をめぐっている。各地の駅を見て来て思うのは、過疎に悩む駅もそれなりの素朴さを身にまとっていることだ。寂れていてもそれが周囲の自然と調和していれば好感はもてる。私にとって駅とはその地の玄関口であり、その地の雰囲気を体現する存在なのだから。
だが、不遜と言ってよいほど見捨てられた木津川駅の風景。それは私の眼には異形の存在と映った。駅前には浮浪者がねぐらを確保しており、がれきが駅の出入り口のすぐ前に積まれている。寂れた工場があたりを覆い、疎外されたような粗末な民家が並ぶ。金網で意味ありげに囲われたスペースが駅前にあり、その空間が無言の圧迫感を与えてくる。乗降客はおらず、駅前には商店が皆無。住民すら通りがからぬ凍った街並み。
その衝撃も覚めやらぬまま、続いて訪れたのが近くの浪速神社。境内に何人もの浮浪者がねぐらを確保していた。ここは果たして神域なのだろうか、という疑問が私の心を通り過ぎる。あるいは神社とは歴史的にそうしたねぐらがない方へ場所を供する役割を果たしていたのかもしれない。私はたかだか四十五年の年齢しか刻んでいないので、神社の歴史には明るくない。だが、一つだけ言えるのは、私は他の神社で同じような光景を目にしたことがないことだ。かつての日本各地のドヤ街が、昨今は訪日外国人の宿として活気を帯びているという。その風潮からも取り残され、その活気から完全に見放されているようにみえる神社。私は続けざまの衝撃から立ち直れないまま、リバティおおさかを訪れた。
リバティおおさかは、二十三年前とは展示を一新していた。もちろん、前もって訪問者がアップしたブログでその事は知っていた。橋下元大阪市長が展示内容の見直しを指示したことも。事前に得た知識のまま、入ってすぐの「いのちを大切に」というメッセージに満ちた展示を見る。その内容が賛否両論の的になるのもわかる気がする。おそらくリバティおおさかの担当者も迷ったことだろう。差別を語るにはまず人は平等という思想を示す意図は分かる。だが、なぜ入ってすぐにあるのかが理解できない。
だが、奥に進むと被差別部落の歴史が豊富な資料やパネルで展示されている。その内容は人権博物館の名に恥じない。事前の情報から懸念していたような、あからさまな反日の精神を感じる事もない。在日朝鮮人や沖縄の人々が受けた差別。ハンセン病患者やいじめの被害者が被った不条理な扱い。館内にあるのは、差別に苦しめられた人々の苦しみの歴史だ。そうした人々は、統治のために設けられた階級という制度の犠牲者でもある。権力の都合によって社会の闇を押しつけられた煩悶の歴史。そこには、人間の闇の側面が反論を許さぬほど立ちこめている。
リバティおおさかの展示には、差別の問題について考えさせられる切実な何かがあると思う。確かに同和利権や逆差別、結果の平等を求めるあまり、行き過ぎてしまった運動はある。それらの団体が声高に訴える主張をうのみにしてはならない。だが、これからの未来に、同じような不幸な歴史を繰り返してはならないこともまた事実。私たちが次代の若者に伝えるべき知識は、リバティおおさかの中に蓄えられている。
知識を身につけるには、膨大なパネルの展示だけでは理解しきれない。さらなる勉強が必要だ。私はそう思い、ミュージアムショップに多数並べられている本を吟味した。そして本書を選んだ。ミュージアムショップにはもっとコアでディープな本も並んでいた。だが、旅行中の身としては、軽めなガイド本の体裁の本書が精いっぱい。
なお、「エレクトラ」のレビューにも書いた通り、私は被差別部落の現状には関心がある。だが、人と部落の関連には興味がない。言い換えれば、個人の出自が被差別部落にあるかどうかは全く興味がない。多分、実力が全てのビジネスの世界に長くいるからだろう。ビジネスの現場に相手の出自など関係ないのだから。
さて、本書は大阪のあちこちをエリア編とトピックス編に分けて取り上げる。エリア編では、大阪のあちこちを地区別に取り上げる。「道頓堀」「千日前」「日本橋筋」「釜ヶ崎」「新世界・飛田」「百済・平野」「北浜・太融寺」「天神橋筋」「舟場・北野」「中津」「京橋・大阪城公園」だ。そしてそれらの地に埋もれつつあるかつての部落の痕跡を紹介するのが本書の主旨だ。
私の大学の卒論は大阪の交通の変遷だった。なので、大阪の歴史には親しんできたつもり。だが、正直に言って本書に挙げられた各地域のうち、被差別部落との連想で覚えていたのは「釜ヶ崎」「新世界・飛田」ぐらいしかない。本書に挙げられた他の場所は私にとってはまったく思いもよらなかった。
だが、よく考えると芸能・興行系のそもそもの起源は河原者が関わっていたという。そう考えれば、道頓堀と千日前といった現代でも芸能・興行のメッカは、部落の痕跡が残されていてもおかしくない。また、千日前といえば私が大学生の頃によく呑み、よく歩き回った地だ。国内でも最悪の犠牲者数を出した千日デパート火災でも知られている。法善寺横丁も近隣の名所としてよく知られているが、そもそも千日前とは法善寺と今はない竹林寺がともに千日回向を行っていたことから名づけられたという。回向が行われたということは、死をつかさどる人々が生活していたことを示している。
あと、本書を読んで最も驚いたこと。それは日本橋筋がかつては大阪随一のスラム街だったことだ。電器店やサブカルショップが立ち並ぶ今の日本橋からはとても想像がつかない。私は日本橋にも大学時代に何度も訪れている。だからこそ、余計に自分の無知を思い知らされた。だが、考えてみるとこのあたりの雑然とした感じは、まさにその名残と言えないだろうか。南海本線と日本橋筋の間には、妙に道幅の広い道路があるが、そこもスラム街の名残なのかもしれない。
それと百済・平野も本書では取り上げている。私はこのあたりについての土地勘は薄い。だが、百済という地名には渡来人の影響がうかがえる。つまり、その後裔となる方々に何らかの関連があるのかもしれない。本書によれば平野川沿いに被差別民が住まわされていたとのことだ。私も車でなんどか通ったことがあるが、歩いたことはまだない。今はずいぶん街並みが観光客を呼んでいるそうだし、一度訪れてみたいと思う。
本書で取り上げられた地の中で、日本橋筋についで意外に思ったのが北浜・太融寺だ。この界隈は船場や大阪城のおひざ元のはず。ところがここにも被差別の傷跡は残っていたのだ。本書によればその遺跡とは、被差別民の住居ではなく、解放運動の本拠がこのあたりに置かれていたということだ。太融寺や愛珠幼稚園なども、解放運動の中で重要な位置を占めているらしい。こういった意外な関連が見つかるのが本書のよいところだ。
天神橋筋が取り上げられているのもまた思いのほかだった。ところが、本書によると被差別部落とは都市の外縁に生まれるもの。南の外縁が釜ヶ崎や西浜部落だとすれば、北の縁が天神橋筋の北端であり、舟場・北野であり中津なのだという。このあたりには霊園や監獄跡、福祉施設などが点在しているのだという。私は本書を読むまでそうしたことをまったく知らなかった。特に、天六といえばわが母校、関西大学の天六校舎があった場所。私もなんどか訪れている。天六といえば日本で一番長い商店街で知られる。華やかな繁華街にも違う側面があったこと。それを本書は教えてくれる。
また、中津が取り上げられているが、あのあたりを歩くと少し場末な雰囲気が街を覆っているのも事実。そういえば本書を読むきっかけとなったリバティおおさかを訪れた翌々日、三宮で飲んだ。その酒の席で、現在の中津がシャッター通りになっていると聞いた。かつての場所の痕跡が払拭しきれていないのだろうか。なお、本書で取り上げられているからといって、今その地で住んでいる方が被差別の民の後裔でないことはもちろんだ。念のため。
京橋・大阪城公園が挙がっているのも想定の外だった。戦中は造兵工廠があった場であり、そもそも大坂の中心であり、部落とはつながりにくい。ところが、本書にも紹介されていたアパッチ族が戦後に暗躍したのはこのあたりのはず。だが、鶴橋や桃谷のいわゆるコリアンタウンが本書に取り上げられず、京橋や大阪城公園が取り上げられたのは意外に感じた。鶴橋や桃谷はいわゆる部落としての性格をもっていないのだろうか。これは少し興味がある。
さて、エリア編で各地の痕跡を取り上げた後、本書はトピックス編にうつる。エリア編にはリバティおおさかがあり、私がうらぶれた様子に衝撃を受けた旧渡辺村、つまり西浜部落は登場しない。だが、トピックス編で取り上げられる5つのトピックスのどれもが西浜部落を舞台としている。5つのトピックスとは「食肉文化と屠場」「有隣小学校と徳風小学校」「四カ所と七墓」「皮革業と銀行」「なにわの塔物語」だ。
食肉文化が部落のなりわいに関連していることはさまざまなルポで知っていた。リバティおおさかのミュージアムショップにも興味深い写真集が売られていた。私も屠場は一度は見ておかなければ、と思っている。生から死の切り替わりが生々しく営まれる場所。普段、肉食を嗜む身としては直面しなければならない現実。私たちは屠場で生から強制的な死を余儀なくされた生き物の肉を美味そうに食う。かつて、木津川や今宮に屠場があったらしい。だが、今はそうした施設は郊外に移ってしまっているらしい。著者は屠場の収入の実態を研究している。屠場の収入は市の財政にも好影響を与えたそうだ。著者の研究は徹底している。その視点で、BSEや食中毒などの食肉をめぐる問題が発生する度、屠場に責任の一端がかぶせられる状況にも苦言を呈する。
「有隣小学校と徳風小学校」では、学校に行けない児童を助けるための福祉施設の歴史が取り上げられている。本書にも何カ所かコラムが載せられている。そのコラムの主旨はかつて大阪で活動した篤志家を顕彰することにある。そうした篤志家の方々の努力が少しずつ大阪を良くしてきたのだ。この項で取り上げられている二つの小学校も彼らの努力の一つ。「四カ所と七墓」のように、大阪市の発展の歴史の中で開発されて消えてゆく存在もある。大阪がよい方向に発展してほしいと思うばかりだ。
「皮革業と銀行」は、かつての大阪が今とは違う発展を遂げていたことを取り上げており、興味深い。かつて西浜地区では皮革業が盛んに営まれていた。そして、その繁栄は、JR芦原橋駅周辺にはかなりの銀行の支店を集めるまでになっていたという。現在のみずほ銀行やりそな銀行の前身の銀行の支店もあったとか。本書には七店舗ほどが紹介されている。ところが、今の芦原橋駅周辺にはゆうちょ銀行が一つある程度で、ほとんどの銀行は撤退してしまったという。その理由は本書には書かれていなかった。だが、なぜいなくなったのかは、今後の大阪の都市計画を考える上で重要な切り口ではないだろうか。
「なにわの塔物語」もそうだ。かつて大阪にはナンバを中心にさまざまな塔が高さを競っていた。通天閣が当時の威容を今に伝え、気を吐いている。被差別の地であったからこそ、思い切った開発もできた。最先端の技術をしがらみなく試すには格好の場所だったのだろう。
だからこそ、冒頭に書いたような木津川駅周辺の状況はなんとかならないものか、と思うのだ。その意味で今後の大阪の都市計画を占う上で重要な「なにわ筋線構想」が南海汐見橋線から新大阪駅に伸びるのではなく、南海の難波駅から伸びる方針に変わってしまったことは痛い。もし汐見橋線が再開発されれば、この辺りの痛々しい風景は一新されるはずなのに。
私は大阪にはあらゆる意味で元気になって欲しいと願っている。だからこそ、このあたりの風景は一新して欲しい。もちろん、過去の歴史をなかったものにすることはできない。過去の悲しい歴史は語り継がなければなるまい。そのためにもリバティおおさかのような施設はある。でも、歴史を語り継ぐのと、今の寂れた状況を放置するのは同じではないはず。今回のリバティおおさかとその周辺の訪問とそこで購入した本書は、私に大阪の都市開発についてのあるべき姿を教えてくれた気がする。
著者は本書の続編も出しているようだ。そこでは本書のトピックス編の続きとしてさまざまな施設への考察を行っているらしい。今度、機会を見つけて読んでみようと思っている。
‘2018/07/09-2018/07/09