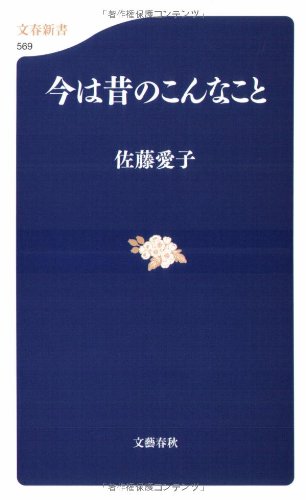新型コロナウィルスの発生は、世界中をパンデミックの渦に巻き込んでいる。
だが、人類にとって恐れるべき存在がコロナウィルスだけでないことは、言うまでもない。たとえば自然界には未知のウィルスが無数に潜み、人類に牙を剥く日を待っている。
人類が築き上げた文明を脅かすものは、人類を育んできた宇宙や地球である可能性もある。
それらが増長した人類に鉄槌を下す可能性は考えておかねば。
本書で取り扱うのは、そうした自然災害の数々だ。
来る、来ると警鐘が鳴らされ続けている大地震。東海地震に南海地震、首都圏直下地震、そして三陸地震。
これらの地震は、長きにわたって危険性が言われ続けている。過去の歴史を紐解くと発生する周期に規則性があり、そこから推測すると、必ずやってくる事は間違いない。
それなのに、少なくとも首都圏において、東日本大震災の教訓は忘れ去られているといっても過言ではない。地震は確実に首都圏を襲うはずなのにもかかわらず。
本書は日本の歴史をひもとき、その時代時代で日本を襲った天変地異をとり上げている。
天変地異といってもあらゆる出来事を網羅するわけではない。飢饉や火事といった人災に属する災害は除き、地震・台風・噴火・洪水などの自然災害に焦点を当てているのが本書の編集方針のようだ。
著者は、そうした天変地異が日本の歴史にどのような影響を与えたのかという視点で編んでいる。
例えば、江戸末期に各地で連動するかのように起こった大地震が、ペリー来航に揺れる江戸幕府に致命的な一撃を与えたこと。また、永仁鎌倉地震によって起こった混乱を契機に、専横を欲しいままにした平頼綱が時の執権北条貞時によって誅殺されたこと。
私たちが思っている以上に、天変地異は日本の歴史に影響を与えてきたのだ。
かつて平安の頃までは、天変地異は政争で敗れた人物の怨霊が引き起こしたたたりだとみなされていた。
太宰府に流された菅原道真の怨霊を鎮めるため、各地に天満宮が建立されたのは有名な話だ。
逆に、神風の故事で知られる弘安の大風は、日本を襲った元軍を一夜にして海中に沈め、日本に幸運をもたらした。
本書にはそういった出来事が人心をざわつかせ、神仏に頼らせた当時の人々の不安となったことも紹介している。
直接でも間接でも日本人の深層に天変地異が与えてきた影響は今の私たちにも確実に及んでいる。
本書は私の知らなかった天変地異についても取り上げてくれている。
例えば永祚元年(989年)に起こったという永祚の風はその一つだ。
台風は私たちにもおなじみの天災だ。だが、あまりにもしょっちゅう来るものだから、伊勢湾台風や室戸台風ぐらいのレベルの台風でないと真に恐れることはない。ここ数年も各地を大雨や台風が蹂躙しているというのに。それもまた、慣れというものなのだろう。
本書は、歴史上の洪水や台風の被害にも触れているため、台風の恐ろしさについても見聞を深めさせてくれる。
本書は七章で構成されている。
第一章は古代(奈良〜平安)
白鳳地震
天平河内大和地震
貞観地震
仁和地震
永祚の風
永長地震
第二章は中世(鎌倉〜室町〜安土桃山)
文治地震
弘安の大風
永仁鎌倉地震
正平地震
明応地震
天正地震
慶長伏見地震
第三章は近世I(江戸前期)
慶長東南海地震
慶長三陸地震津波
元禄関東大地震
宝永地震・富士山大噴火(亥の大変)
寛保江戸洪水
第四章は近世II(江戸後期)
天明浅間山大噴火
島原大変
シーボルト台風
京都地震
善光寺地震
第五章は近代I(幕末〜明治)
安政東南海地震
安政江戸地震
明治元年の暴風雨
磐梯山大噴火
濃尾地震
明治三陸大津波
第六章は近代II(大正〜昭和前期)
桜島大噴火
関東大震災
昭和三陸大津波
室戸台風
昭和東南海地震
三河地震
第七章は現代(戦後〜平成)
昭和南海地震
福井大地震
伊勢湾台風
日本海中部地震
阪神淡路大震災
東日本大震災
本書にはこれだけの天変地異が載っている。
分量も相当に分厚く、636ページというなかなかのボリュームだ。
本書を通して、日本の歴史を襲ってきたあまたの天変地異。
そこから学べるのは、東南海地震や南海地震三陸の大地震の周期が、歴史学者や地震学者のとなえる周期にぴたりと繰り返されていることだ。恐ろしいことに。
日本の歴史とは、天災の歴史だともいえる。
そうした地震や天変地異が奈良・平安・鎌倉・室町・安土桃山・江戸・幕末・明治・大正・昭和・平成の各時代に起きている。
今でこそ、明治以降は一世一元の制度になっている。だが、かつては災害のたびに改元されていたと言う。改元によっては吉事がきっかけだったことも当然あるだろうが、かなりの数の改元が災害をきっかけとして行われた。それはすなわち、日本に災害の数々が頻繁にあったことを示す証拠だ。
そして、天変地異は、時の為政者の権力を弱め、次の時代へと変わる兆しにもなっている。
本書は、各章ごとに災害史と同じぐらい、その時代の世相や出来事を網羅して描いていく。
これだけたくさんの災害に苦しめられてきたわが国。そこに生きる私たちは、本書から何を学ぶべきだろうか。
私は本書から学ぶべきは、理屈だけで災害が来ると考えてはならないという教訓だと思う。理屈ではなく心から災害がやって来るという覚悟。それが大切なのだと思う。
だが、それは本当に難しいことだ。阪神淡路大震災で激烈な揺れに襲われ、家が全壊する瞬間を体験した私ですら。
地震の可能性は、東南海地震、三陸地震、首都圏直下型地震だけでなく、日本全国に等しくあるはずだ。
ところが、私も含めて多くの人は地震の可能性を過小評価しているように思えてならない。
ちょうど阪神淡路大震災の前、関西の人々が地震に対して無警戒だったように。
本書にも、地震頻発地帯ではない場所での地震の被害が紹介されている。地震があまり来ないからといって油断してはならないのだ。
だからこそ、本書の末尾に阪神淡路大地震と東日本大震災が載っている事は本書の価値を高めている。
なぜならその被害の大きさを目にし、身をもって体感したかなりの数の人が存命だからだ。
阪神淡路大地震の被災者である私も同じ。東日本大震災でも震度5強を体験した。
また、福井大地震も、私の母親は実際に被害に遭い、九死に一生を得ており、かなりの数の存命者が要ると思われる。
さらに、阪神淡路大地震と東日本大震災については、鮮明な写真が多く残されている。
東日本大震災においてはおびただしい数の津波の動画がネット上にあげられている。
私たちはその凄まじさを動画の中で追認できる。
私たちはそうした情報と本書を組み合わせ、想像しなければならない。本書に載っているかつての災害のそれぞれが、動画や写真で確認できる程度と同じかそれ以上の激しさでわが国に爪痕を残したということを。
同時に、確実に起こるはずの将来の地震も、同じぐらいかそれ以上の激しさで私たちの命を危機にさらす、ということも。
今までにも三陸海岸は何度も津波の被害に遭ってきた。だが、人の弱さとして、大きな災害にあっても、喉元を過ぎれば熱さを忘れてしまう。そして古人が残した警告を無視して家を建ててしまう。便利さへの誘惑が地震の恐れを上回ってしまうのだ。
かつて津波が来たと言う警告を文明の力が克服すると過信して、今の暮らしの便利さを追求する。そして被害にあって悲しみに暮れる。
そうした悲劇を繰り返さないためにも、本書のような日本の災害史を網羅した本が必要なのだ。
ようやくコロナウィルスによって東京一極集中が減少に転じたというニュースはつい最近のことだ。だが、地震が及ぼすリスクが明らかであるにもかかわらず、コロナウィルスがなければ東京一極集中はなおも進行していたはず。
一極集中があらゆる意味で愚行の極みであることを、少しでも多くの人に知らしめなければならない。
本書は、そうした意味でも、常に手元に携えておいても良い位の書物だと思う。
‘2019/7/3-2019/7/4