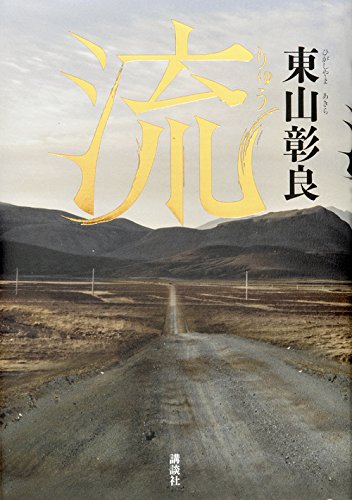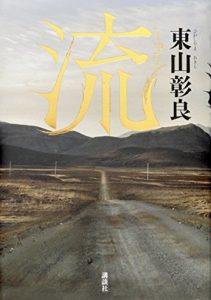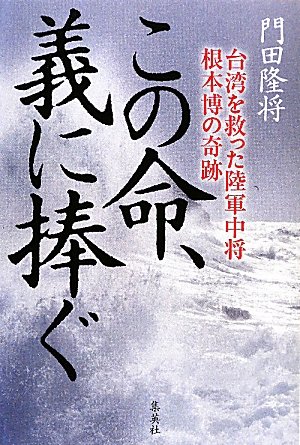
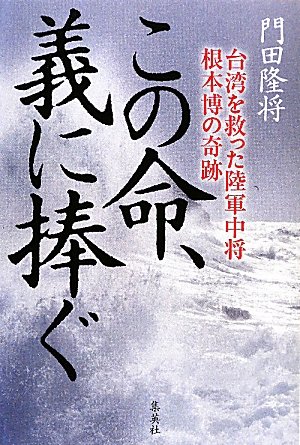
恥ずかしながら、私は本書を読む半年前まで根本博中将のことを知らなかった。
根本博中将とは、本書の主人公である。
しかも私は、根本博中将が晩年、私の家の近くに住んでいたことも知らずにいた。
私が根本博中将のことを初めて知ったのは、町田市が発行している「まちびと」というグラフ誌だ。2018年7月号の「まちびと」では、根本博中将が見開きで特集されていた。
https://www.city.machida.tokyo.jp/community/shimin/katsudou/machibito/machibito201807.html
「まちびと」では、根本中将の業績として終戦時の駐蒙軍司令官としてソ連の侵攻を退け、開拓民の多くを無事日本に帰還させたことが紹介されている。
だが、根本中将が国共内戦で台湾に追い詰められた国民党のために単身駆けつけたことや、台湾を共産党の支配から逃れるきっかけとなった古寧頭戦役の勝利が、根本中将の指揮にあることはほとんど触れていない。
ただ、本書の画像がキャプションとともに載せられ、根本中将が台湾の今にとって重要な役割を果たしたことが少しだけ紹介されるのみ。
本書が大きく取り上げるのは、その台湾での事績だ。
根本中将は台湾にとって何をした人物なのか。そしてなぜ、そのことが後世に伝わっていないのか。
本書の扉には、一対の花瓶の写真が載っている。一つは台北の中正紀念堂に展示されているもの。もう一つは蒋介石から根本中将にお礼として送られたという。その花瓶は日本のどこかにあるはずだ。だがそれが今、どこにあるかは著者は明かさない。
「根本に贈られたその花瓶は、六十年近くを経た現在も、ある場所に大事に保管されている。」(220p)。
この花瓶は全部で三対あったという。一対はイギリスに、もう一対は日本の皇室に、残りの一対の片方は蒋介石が持ち、もう片方は根本中将に贈ったという。
そこからも台湾がどれほどの感謝を根本中将に感じたのかが伺える。
そこまでの感謝を受けた理由。それこそ、根本中将が台湾に対して貢献した行いである。
今、台湾の地図を見ると、台湾の国土は中国大陸からすぐそばの金門島も含んでいる。そのため、台湾海峡のほとんど全ては台湾の内海にあたる。
国共内戦の最後の戦いはここ金門島で行われた。それまで連戦連敗で押されっぱなしだった国民党軍がようやく一矢をむくい、共産党軍を押し返した。それによって今に至るまで台湾には共産党の統治は及んでいない。
その記念すべき古寧頭戦役と呼ばれる戦いで、根本中将は中国人に名を変え、個人として顧問として戦いを指導したのだという。
その戦いは国共内戦の決着をつけたもので、それ以来、現代に至るまで台湾は独立を維持し続けている。
根本中将の働きがなければ、金門島どころか台湾すら共産党に飲み込まれていた可能性が高い。
それを知っていたからこそ、蒋介石は根本中将に最高の友人にしか送らない花瓶を送ったのだ。
一方、国民党としては台湾統治の正統性を主張するため、対外的には根本中将の存在を明かさずにいた。そのため、今も公的には根本中将が台湾を救った業績は掲げられていない。
本書を読む前後に私は二回、台湾へと行った。読む前に行った際は時間の都合で中正紀念堂の地下の展示室にはいかれずじまいだった。
なので、本書を読んでから八カ月ほどして、中正紀念堂の展示室に行き、その花瓶を見てきた。その花瓶の説明にもその他の蒋介石の業績をたたえる展示のどこにも根本中将の名前は出てこない。
それは、根本中将が台湾に渡る際、私人の資格で、しかも密航して行ったことにも関係している。国と国の間の契約や公的な要請もなく、全くの個人の意思で向かった台湾。だからこそ、記録にも残っていないし、台湾政府としても日本人に力を借りたことを大っぴらにしたくない。
根本中将もあまり自らの業績を吹聴せずにいたため、本書で明かされるまではほぼ歴史から忘れられかかっていた。
本書ではそうした根本中将の業績が著者によって再現される。
構成には工夫が施されており、各章ではそれぞれ違う時代、違う場所を描いているが、著者はきっちり書き分けており、読者が混乱する心配はないはずだ。
本書は以下のような構成となっている。
はじめに
プロローグ
第一章 密航船
第二章 内蒙古「奇跡の脱出」
第三章 わが屍を野に曝さん
第四章 辿り着いた台湾
第五章 蒋介石との対面
第六章 緊迫する金門島
第七章 古寧頭の戦い
第八章 貶められる名誉
第九章 釣竿を担いだ帰国
第十章 武人の死
第十一章 かき消された歴史
第十二章 浮かび上がる真実
第十三章 日本人伝説
エピローグ
おわりに
第十一章では、湯恩伯の功績が台湾の歴史から消された理由が書かれる。湯恩伯が日中戦争や国共内戦でいく度も惨敗を喫し、蒋介石から冷遇されたことも、根本中将の業績が忘れ去られた理由でもあるはずだ。
だが、それからかなりの年月がたち、根本中将の業績がにわかに脚光を浴びる機会があった。
エピローグでは、二〇〇九年春に金門島で催された「古寧頭戦役六十周年記念式典」が描かれる。そこで根本中将を台湾に呼び寄せるために多大な貢献をした人物の遺族が招待され、正式に古寧頭戦役で日本人が果たした役割に謝辞があったという。
「古寧頭戦役六十周年記念式典」の折、金門空港で国防部常務次長から記者のいる中で根本中将を台湾に連れて行くのに多大な貢献を果たした明石元紹氏と吉村勝行氏に対してこのような言葉を掛けたという。
「一九四九年、わが国が一番苦しかった時に、日本の友人である根本様と吉村様二人にしていただいたことを永遠に忘れることはできません。わが国には“雪中に炭を送る”という言葉があります。一番困った時に、お二人は、それをやってくれたのです。中華民国国防部を代表して心より御礼を申し上げ、敬意を表します」
さらに著者はおわりにで、もう一度根本中将を総括する。六十一名の情報提供者へのお礼を含めて。その氏名をみると、中国人と日本人が半分ほどだ。かなりの取材をされたことが理解できる。
今、私は日常的に鶴川駅を使っている。だが、すでに根本邸はない。そもそも駅の周囲には商業ビルが多く、民家自体が少ない。いまやマンションと商業ビルにとって変わられてしまった。
「父は、この家に帰ってくるのは初めてだったので、場所を駅員に聞いたそうです。当時の鶴川駅は木造で改札口も木で出来ていました。電車は二両で、四十分に一本しかありません。うちは駅から六軒目の家で、藁ぶきの屋根が終わって、初めての瓦の家がそうでした。駅員はうちを知っていますから、すぐに教えてくれたそうです。」(75p)
根本氏の家が果たしてどこにあったのか、気になるところだ。
おそらく、根本氏が蒋介石より贈られた花瓶の片方も、鶴川ではないどこかに大切に仕舞われていることだろう。
だが、たとえ鶴川から根本中将をしのぶよすがが失われたとしても、私のような台湾が好きな鶴川の住民として、根本氏のことは忘れずにいたいと思う。つい最近まで根本氏のことを知らなかった不明を詫びつつ。
‘2018/12/5-2018/12/5