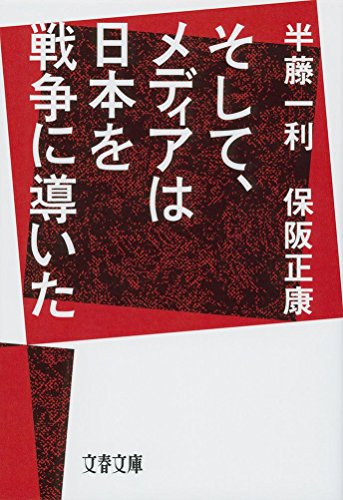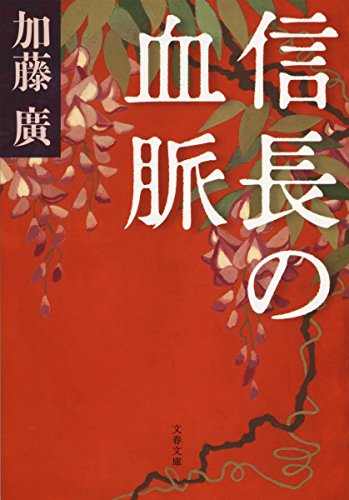

著者の本を読むのは初めて。だが、ふと思い立って読んでみた。これがとても面白かった。
本書はいわゆる短編集だ。大河が滔々と流れるような戦国の世。その大きなうねりの脇で小さく渦巻く人の営み。そんな戦国の激しくも荒くれる歴史のの中で忘れ去られそうなエピソードをすくい上げ、短編として仕立てている。それが本書だ。
一つ一つは歴史の大筋の中では忘れ去られそうなエピソードかもしれない。だが、戦国史に興味を持つ向きには避けては通れない挿話だ。
例えば平手政秀が織田信長をいさめるため切腹したエピソード。 これなど、織田信長が戦国の覇者へ上り詰めるまでの挿話としてよく取り上げられている。私も歴史に興味を持つ以前から豆知識として知っていた。
一編目の「平手政秀の証」は、まさにそのエピソードが描かれている。しかも新たな視点から。今までの私が知っていた解釈とは、「うつけもの」と言われた織田信長を真人間にもどすために傅役の平手政秀が切腹した、という事実。平手政秀が切腹するに至った動機は、信長が父、織田信秀の葬儀で、祭壇に向かって抹香を投げつけたことにあり、その振る舞いに信長の将来を悲観した平手政秀が織田信長の良心に訴えるために切腹に至った、という解釈だ。その前段で、己の娘濃姫との婚姻に際して織田信長に会った斎藤道三が、信長の器量を見抜いた挿話もある。そう。これらはよく知られた話だ。そして、これらのエピソードにから現れて来るのは分裂した信長像。後年、風雲児として辣腕を振るい、戦国史を信長以前と信長以後に分けるほどに存在感を発揮した信長。いったいどちらの信長像が正しいのか。分裂した信長像を整合するため、平手政秀の諌死によって信長が目を覚ました、との解釈するのが今までの定説だ。
ところが著者の手にかかると、より深いエピソードとして話が広がる。上記のようなよく知られたエピソードも登場する。だが、著者が本書で披露した解釈の方がより自然に思えるのは私だけだろうか。斎藤道三の慧眼から始まり、平手政秀の死をへて、信長の変貌とその後の戦国覇者への飛躍。それらの本編によって綺麗にまとまるのだ。これこそ歴史小説の醍醐味と言えよう。
二編目の「伊吹山薬草譚」も戦国時代のキリスト教の布教と既存宗教の軋轢を描いており、これまた興味深い。現代の伊吹山に西洋由来の薬草が自生している謎に目を付けた著者の着想も大したものだが、そこからこのような物語を練り上げた筆力もたいしたものだ。西洋で荒れ狂った魔女狩りの狂気の波とキリスト教の布教による海外渡航など、当時の西洋が直面していた歴史のうねりを日本の歴史に組み込んだ手腕と、世界のスケールを日本に持ち込んだ大胆さ。ただうならされる。
織田信長がキリシタンを庇護する一方で当時の仏教を苛烈に弾圧したことは有名だ。本編でもその一端が描かれる。伊吹山に薬草を育てる農場を作りたいと願い出たキリシタンの司教に許可を与え、もともとその地を薬草の農園として使っていた寺の領地を一方的に焼き払う許しを与える。焼き払われる寺側は黙ってはいない。さまざまな内情を探りつつ、西洋の侵略に抵抗する。それが本編のあらすじだ。国盗りや合戦が日常茶飯事のできごとであった戦国を、西洋と東洋の摩擦からとらえなおす着眼の良さ。そして植物にも熾烈な領土の取り合いがあったことを、戦国時代の出来事の比喩に仕立てる視点の転換の鮮やかさ。ともに興味深く読める。
三編目の「山三郎の死」は、豊臣秀頼の父が誰かを探る物語だ。史実では豊臣秀吉と淀殿の間の子とされている。だが、当時から秀頼の父は秀吉ではないとの風評が立っていたそうだ。そこに目を付けた著者は、歌舞伎の源流として知られる出雲お国の一座の名古屋山三郎が秀頼の父では、との仮説を立てる。私自身、豊臣秀頼にはかねがね興味を持っていた。大坂の陣で死なず、薩摩に逃れたという説の真偽も含めて。
本編で秀頼の父が山三郎であるとの流言の真偽を探るのは片桐且元。山三郎の身辺調査を片桐且元に依頼したのは、淀君の乳母である大蔵卿局。秀頼に豊臣家の将来を託すには、そのようなうわさの火元を確かめ、必要に応じてうわさの出どころを断ち切っておく。そんな動機だ。片桐且元は探索する。そして出雲お国に会う。さらには名古屋山三郎の眉目秀麗な容姿を確認する。舞台の上で演じられる流麗な踊り。本編にはかぶき踊りの源流が随所に登場する。その流麗な描写には一読の価値がある。かぶきの原点を知る上でも本編は興味深い。
淀君が秀頼を懐妊した当時、朝鮮出兵の前線基地である名護屋にいたはずの秀吉。その秀吉が果たして種を付けられたのか。本編の芯であったはずの謎に答えは示されない。読者の想像の赴くままに、というわけだ。だが、一つだけ本編によって明かされることがある。それは戦国の芸能が殺伐とした中に一瞬の光を見いだす芸能であったことだ。そのきらびやかな光は、当時の庶民の慰めにもなり、うわさの出どころにもなった。秀頼が太閤の子ではないとのウワサ。それはきらびやかな芸能と権力者の間に発生してもおかしくないもの。うわさには原因があったのだ。
四編目の「天草挽歌」は、天草の乱が舞台だ。江戸時代も少しずつ戦国のざわめきを忘れはじめた頃。戦国の世を熱く燃やしていた残り火が消えゆき、徳川体制が着々と築かれていた頃。藩主である寺沢家による苛烈な年貢取り立ては、江戸幕府による支配が生み出した歪みの一つだろう。その取り立てが天草の乱の遠因の一つであったことに疑いはない。そこにキリシタンの禁教の問題もからむので、内政も一筋縄では行かない。
本編は、三宅藤兵衛という中間管理職そのものの人物の視点で進む。三宅藤兵衛は寺沢家の禄を食む武士だ。隠れキリシタンをあぶり出すため、踏み絵を使った各藩の対策はよく知られている。それはもちろん、キリシタンの禁制を国是とした江戸幕府の方針に従うためだ。藤兵衛はキリシタンの取り締まりをつかさどる役職にあった。ところが藤兵衛自身がもとキリシタン。転んで教えを放棄した経歴の持ち主だ。その設定が絶妙だ。かつて自分が信じていたキリスト教を取り締まらねばならない。その葛藤と自己矛盾に悩む様。それは任務に精勤する武士の生きざまにさらなる陰影を与える。
寺沢家の政策の拙さが産んだ現場のきしみ。それはとうとう寺沢家の本家が乗り出し、苛烈な取り締まりをさせるまでに至る。さらに年貢の取り立ても苛烈さの度を増してゆく。そして事態はいよいよ島原の乱に突入していく。もともと、著者は本書において明智左馬助(秀満)を取り上げたかったという。そのような解説が著者自身によってなされている。それで左馬助の子と伝えられる三宅重利藤兵衛を主人公としたようだ。過酷な戦国を生き延びた血脈が、キリストを信じることをやめ、キリストを裁く。その流転こそが起伏に満ちた戦国時代を表しており、妙を得ている。
ら
戦国の大河が滔々と流れる脇で、忘れさられようとする挿話。それらを著者はすくい上げ、光を当てる。著者がその作業の中で伝えようとした事。それは、人々にとって、自らの生きざまこそが大河であるとの事だ。歴史の主役ではないけれど、それぞれが自分の歴史の主役。そして自らの役割を悩みながら懸命に生きた事実。それは尊い。その尊さこそ、著者が本書で描きたかったことではないだろうか。
‘2017/10/25-2017/10/26