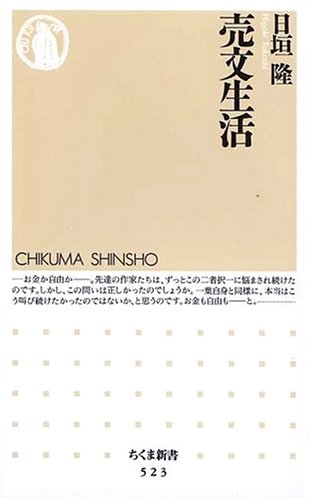あらためまして、合同会社アクアビットの長井です。
弊社の起業までの航海記を書いていきます。以下の文は2018/1/4にアップした当時の文章が喪われたので、一部を修正しています。
上京したてのなにもない私

1999年4月。かばん一つだけで東京に出てきた私。
最低限の服と洗面道具、そして数冊の本。これから住むとはとても思えない格好で、それこそ数日間の小旅行のような軽装備。
当時の私はあらゆるものから身軽でした。持ち物もなく、頼りがいもなく、肩書もしがらみもありません。
移動手段すら、自分の足と公共の機関だけ。それどころか、ノートパソコンや携帯電話はおろか、固定電話を持っていなかったため、インターネットにつなぐすべさえありませんでした。
私と世の中をつなぐのは郵便と公衆電話のみ。
妻がいなければ私は完全に東京でひとりぼっちでした。
今思い出しても、私が当時住んだ相武台前のマンションの部屋には何もありませんでした。東京生活の足掛かりとするにはあまりにも頼りなく、大宇宙の中の砂粒のようにはかない住みか。
それでも、当時の私にとっては初めて構えた自分だけの城です。
当時の私がどういう風にして生活基盤を整えていったのか。
当時、私はメモを残しています。以下の記述はそこに書かれていた内容に沿って思いだしてみたいと思います。
まず、住民票の手続きを済ませ、家の周りを探険しました。
次いで、自転車を買いに、行幸道路を町田まで歩きました。さらに、国道16号沿いに沿って相模原南署で免許の住所移転をし、淵野辺まで歩き、中古の自転車を購入しました。これで移動手段を確保しました。
それから、通信手段については、住んで二、三カ月ほどたってポケベルを契約したような記憶があります。
近くに図書館を見つけたことによって、読書の飢えは早いうちから癒やすことができました。
それだけです。
あとは妻と会うだけの日々。本当に、どうやって毎日を過ごしていたのかほぼ覚えていません。
完全なる孤独と自由の日々

この頃の私はどうやって世間と渡りをつけようとしていたのでしょう。恵まれたコミュニケーション手段に慣れきった今の環境から思い返すと、信じられない思いです。
でも、何もないスタートだったからこそ、かえって新生活の出だしには良かったのかもしれません。
妻以外の知り合いはほぼ居らず、徹底した孤独。それでいて完全なる自由。
この頃の私が享受していた自由は、今や20年近くの年月が過ぎた今、かけらもありません。
この連載を始めた当時(2017年)の数カ月、私はFacebookをあえてシャットアウトしていました。毎日、投稿こそしていましたが、他の方の投稿はほとんど目を通さず。
仕事が忙しくFacebookを見ている時間が惜しかったことも理由ですが、それだけではありません。私は、上京したばかりの当時の私に可能な限り近づこうと試みていたのです。自由な孤独の中に自分を置こうとして。
もちろん、今は家族も養っているし、仕事も抱えているし、パートナー企業や技術者にも指示を出しています。孤独になることなどハナから無理なのです。それは分かっています。
ですが、上京当初の私が置かれていた、しがらみの全くない孤独な環境。それを忘れてはならないと思っています。
多分、この頃の私が味わっていた寄る辺のない浮遊感を再び味わうには、老境の果てまで待たねばならないはず。
職探し

足の確保に続いて、私が取りかかったのは職探しです。
そもそも、私が上京に踏み切ったのは、住所を東京に移さないと東京の出版社に就職もままならなかったからでした。
住民票を東京に移したことで、退路は断ちました。もはや私を阻むものはないはずと、勇躍してほうぼうの出版社に履歴書を送ります。
ところが、出版経験のない私の弱点は、東京に居を移したからといって補えるはずがなかったのです。
そして、東京に出たからといって、出版社の求人に巡り合えるほど、現実は甘くはなかったのです。出版社への門は狭かった。
焦り始めた私は、出版社以外にも履歴書を送り始めます。そうすることで、いくつかの企業からは内定ももらいました。
覚えているのは品川にあった健康ドリンクの会社の営業職と、研修を企画する会社でした。が、あれこれ惑った末、私から断りました。
私は、生活の基盤を整える合間にも、あり余る時間を利用してあちこちを動き回っていました。
例えば土地勘を養うため、自転車であれこれと街を見て回っていました。
町田から江の島まで自転車で往復したことはよく覚えています。
江の島からの帰り、通りすがりの公衆電話から内定を辞退したことは覚えています。上にも書いた研修を企画する会社でした。
私が内定を迷った末に辞退したのも、大成社に入ってしまった時と同じ轍を踏むことは避けたいと思ったからでしょう。
そして、思い切って上京したことで就職活動には手応えを感じられるようになりました。少なくとも内定をいただけるようになったのですから。
かといって、いつまでも会社をえり好みしていると生活費が尽きます。もはや出版社の編集職にこだわっている場合ではないのです。
ここで、私は思い込みを一度捨てました。出版社で仕事をしなければならない、という思い込みを。
この時の私は職探しにあたって、妻や妻の家族には一切頼りませんでした。
将来、結婚しようとプロポーズを了承してもらっていたにも関わらず、職がなかった私。
そんな状況にも関わらず、私は妻に職のあっせんは頼みませんでしたし、妻もお節介を焼こうとしませんでした。
そもそも、当時の妻が勤めていたのが大学病院の矯正科で、私に職をあっせんしようにも、不可能だったことでしょう。
今から思うと、結果的にそういう安易な道に頼らなかったことは、今の私につながっています。多分、ここで私が妻に頼っていたとすれば、今の私はないはずです。
ただ、一つだけ妻が紹介してくれた用事があります。
それは、大田区の雑色にある某歯医者さんを舞台に、経営コンサルタントの先生が歯科のビデオ教材を録画するというので、私が患者役として出演したことです。
たしか、私が上京して数日もしない頃だったように思います。
当時の私に才がほとばしっていれば、この時のご縁を活かし、次の明るい未来を手繰り寄せられたはずです。ひょっとしたら俳優になっていたかも。
少なくとも、今の私であればこうした経験があれば、次のご縁なり仕事なりにつなげる自信があります。
ですが、当時の私にはそういう発想がありません。能力や度胸さえも。
愚直に面接を受け、どこかの組織に属して社会に溶け込むこと。当時の私にはそれしか頭にありませんでした。つまり正攻法です。
このころの私の脳裏には、まだ自営や起業の心はありませんでした。
自分が社会に出て独自の道を開く欲よりも、大都会東京に溶け込もうとすることに必死だったのでしょう。そうしなければ結婚など不可能ですから。
この時、私がいきなり起業などに手を出していたら、すぐさま東京からはじき出され、関西にしっぽを巻いて帰っていたことは間違いありません。
もちろん、妻との結婚もご破算となっていたことでしょう。
無鉄砲な独り身の上京ではありましたが、そういう肝心なところでは道を外さなかったことは、今の私からも誉めてあげてもよいと思います。
妻の住む町田に足しげく通い、結婚式の計画を立てていた私。浮付いていたであろう私にも、わずかながらにも現実的な考えを持っていたことが、今につながっているはずです。
結局、私が選んだのは派遣社員への道でした。職種は出版社やマスコミではありません。スカイパーフェクTV、つまり、スカパーのカスタマーセンターです。
そのスーパーバイザーの仕事が就職情報誌に載っており、私はそれに応募し、採用されました。
考えようによっては、せっかく東京くんだりまで出てきたのに、当時の私は派遣社員の座しかつかめなかった訳です。
しかし、この決断が私に情報処理業界への道を開きました。
次回はこのあたりのことを語りたいと思います。ゆるく永くお願いします。