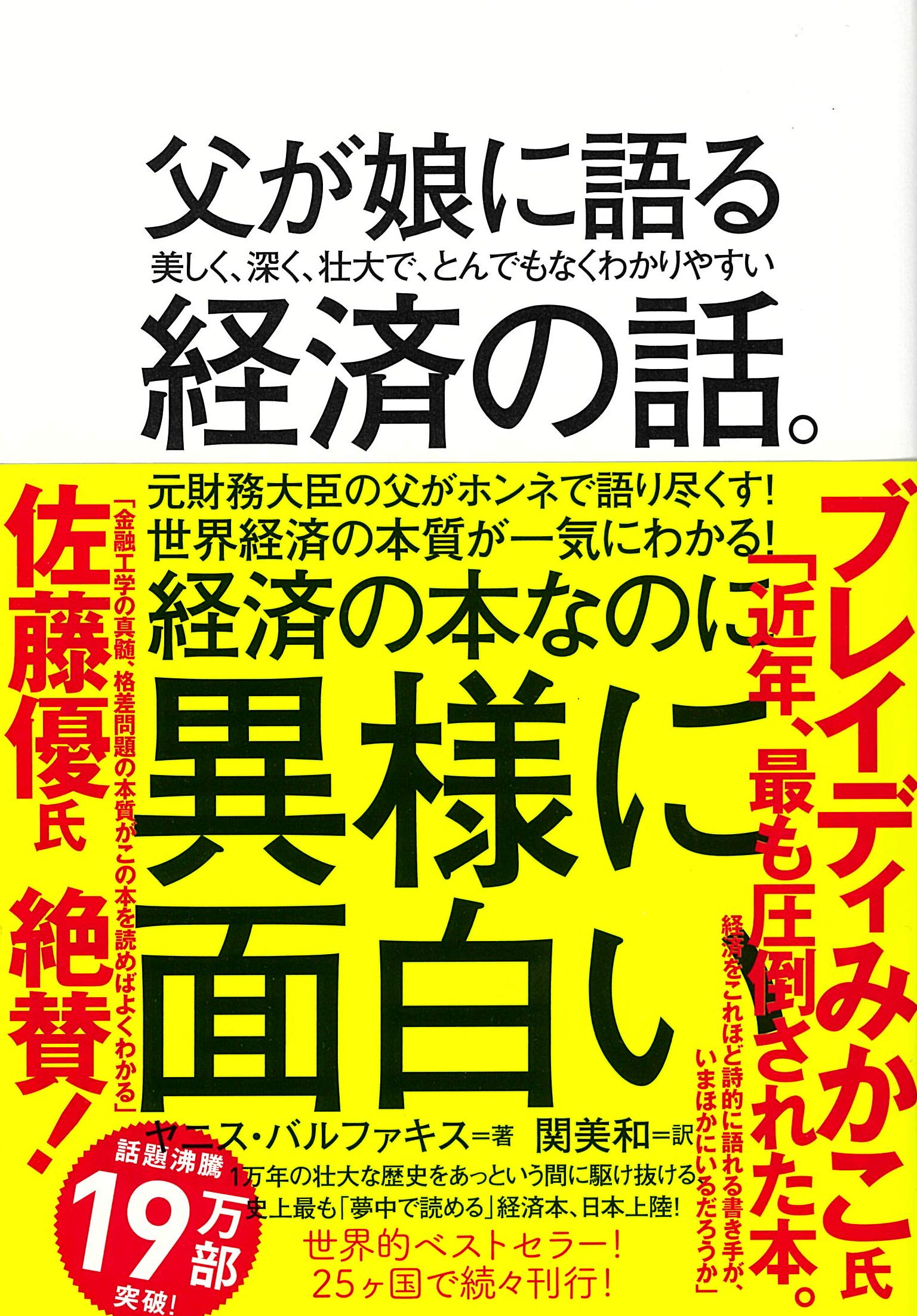
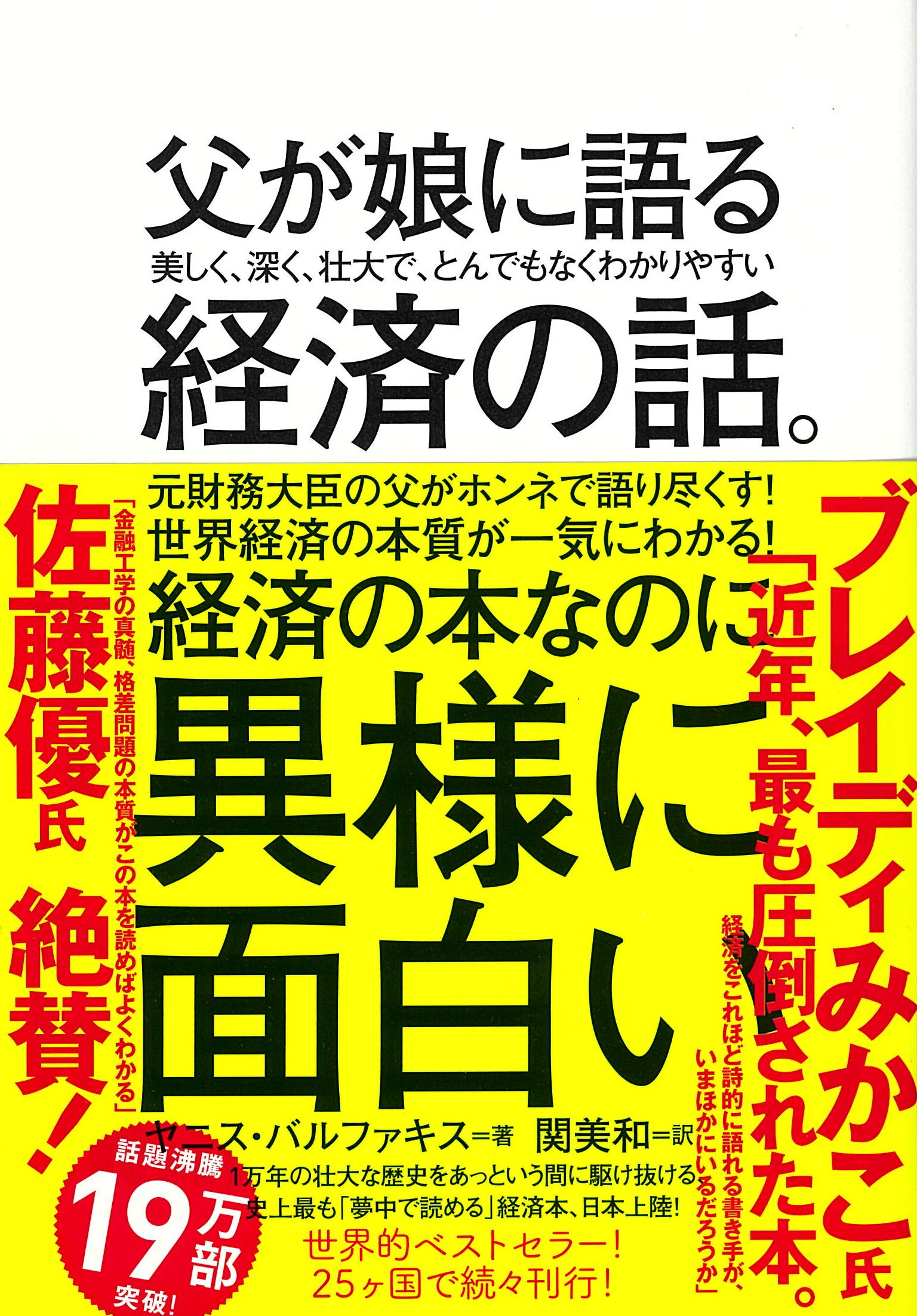
本書は、経済関係の本を読む中で手に取った一冊だ。新刊本で購入した。
タイトルの通り、本書は父から娘に向けて経済を解説すると体裁で記されている。確かに語り口こそ、父から娘へ説いて教えるようになっているが、内容はかなり充実している。まさに深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい。
実は私も、娘に向けてこの本を購入した。私の長女は、イラストレーターの個人事業主として中学生の頃から活動している。
私も経営者とはいえ、経済的にはまだゆとりはない。有能な経営者とは言えないだろう。だが、少なくとも四人の家族を養うだけの金銭はこれまでに稼いできた。
だが、娘はまだこれからだ。個人事業主とはそれほど簡単に稼げるものではない。実際、どこかに常駐しておらず、家で仕事している娘はまだ稼ぎが少ない。
だからこそ、本書のように経済の本を読んで勉強しておいた方が良い。私はそう思った。
今まで経済をろくすっぽ学ばずにやってきた私が、さんざん苦労してきたからだ。
本書の第一章では、なぜ格差が生じるのかについて説明する。
南北問題と言う言葉がある。同じ地球の北半球と南半球で富に格差が発生している現実だ。裕福な北米やヨーロッパ、中国と、貧しい南半球の国々。
なぜ違うのか。それは『銃・病原菌・鉄』でも示されていたが、地理的な問題だ。南北に長いアフリカは、緯度によって季節や気候ががらりと違ってしまう。そのため、作物も簡単に伝播させることが難しい。ところが、東西に伸びたユーラシア大陸では気候の違いがあまり発生しなかった。そのため、一つの文明・文化が勃興すると、さしたる障害もなしに東西に素早く広がった。北アメリカも同じように。
そして、オーストラリアなど、自然が豊かな国では人々はただ自然から食物をいただくだけで生きていけた。身の危険もないため、人々は植物を貯めておく必要も、余剰を意識する必要もなかった。
第二章は市場をテーマにしている。経験価値と交換価値。その二つの価値は長らく経済の両輪だった。
個人の体験は交換が利かない。だから自らの経験や知識を人のために役立てた。個人の経験それ自体に価値があり、対価が支払われる。経験価値だ。
ところが徐々に貨幣経済が発展するとともに、市場で貨幣と商品を交換する商慣習が成り立ってゆく。市場において貨幣を介してモノを交換する。交換価値だ。
何かを生産し、それを流通させるまでには資産が欠かせない。自然の原材料や加工道具、それに生産手段だ。さらにそうした資産を置く場所と空間。さらに、かつては奴隷として抱える労働力も資産に含まれた。そうした資産や不動産や労働力は、交換できる価値として取り扱うことができた。
過去のある時期を境に、人類の経済活動において交換価値は経験価値を凌駕した。
第三章では、交換価値で成り立っていた経済が次の段階に進む様子を取り上げている。利益や借金が経済活動の副産物ではなく、企業にとって目的や手段となる過程。それが次の段階だ。
賃金も地代も原料や道具の値段も、生産をはじめる前からわかっている。将来の収入をそれらにどう配分するかは、あらかじめ決まっているわけだ。事前にわからないのは、起業家自身の取り分だけだ。ここで、分配が生産に先立つようになった。(78ページ)
既存の封建社会のルールに乗らなくてもよい起業家は、借金をして資産を増やし、それをもとに競争するようになった。
第四章では、借金が新たな役割を身につけた理由を説明する。
借金とは、現在の価値と未来に利子がついている価値との交換だ。貸主は貸した金銭が、将来にわたって利子付きで戻ってくること期待する。つまり、将来の価値と今の価値の交換だ。その差額である利子が貸主の利益となる。
今、周りにある企業や国、銀行と取引するのではない。将来の企業、国、銀行と交換する。それが借金のカラクリだ。今、存在する価値の総量以上は借りられない。だが、将来の利子を加えると、今の価値の総量よりも高い金額が借りられる。これが金融の原点であり、ありもしない富がなぜ次々と生まれてくるカラクリだ。
貨幣をさして兌換貨幣と呼ぶ。かつては金を保有している国が、いつでも保有する金と貨幣を交換してもらえる約束と信頼の上で貨幣を発行していた。いわゆる金本位制だ。
その考えを推し進めると、将来も今の経済体制が維持される前提のもと、未来の利子がついた価値と今の価値を交換する金融の仕組みが成り立つ。
第五章では、労働と賃金関係について説明される。今までの説明で、経済の成り立ちが描かれてきた。だが、今やロボットや人工知能が人類の労働力にとって替わろうとしている。それらとどう共存するか。
本書はこの後第六章、第七章、第八章と人類が今直面している問題に経済の観点から切り込んでいく。仮想通貨や環境問題、人類の未来といった問題に。
実は本書は、この後半からがさらに面白い。
今の市場経済に未来はあるのか。経済活動に携わる人の誰もが考えたことがあるのではないだろうか。
一見すると、社会を回すためには今の方法しかないように思える。需要と供給。給与と消費。資本と市場。人の欲求と向上心をかなえ、勝者と敗者を生産しつつ、今の資本主義の世の中は動いている。
だが、その概念に揺らぎが生じたからこそ、SDG’sの概念が提唱されている。持続可能な開発目標。つまり今のやり方のままでは持続が不可能であることを、国連をはじめ誰もが感じている。
その中にうたわれている十七の目標は一見すると真理だ。資源は限られているとの前提のもと、化石燃料を燃やしてあらゆる社会活動が回っている。金融システムもコンピューターが幅を利かせるようになった以上、電力とは切っても切れない。今の経済活動は有限の資源を消費することを前提に動いている。その前提を変えなければ、経済活動や地球に未来はないと。それが著者の懸念だ。
交換価値とは、自然を破壊しても生じる価値であり、人の欲望には限度がない。著者はおそらく、SDG’sが唱える十七の項目ですら生ぬるいと感じているに違いない。
将来に対する信頼が今の金融システムを支えている。その将来が危うくなっている。
利子が戻ってくるはず将来が危ういとなると、借金がリスクとなる。つまり信頼が崩れてしまう。金融システムの前提である錬金術は、将来への信頼が全てだ。
将来の価値と今の価値を交換する。つまり将来を食いつぶしているのが今の経済の本質だ。果たして将来を食いつぶしてよいのだろうか。食いつぶす資格は誰にあるのだろうか。
食いつぶす資格は誰にあるのだろうか。
人間が今まで動かしてきた制度や社会を変えるのはすぐには難しい。だが、この社会を維持していかなければならない。今のままのやり方ではどこかで限界が来る。
そのために著者は本書を用いて、さまざまな提言を行っている。
交換価値のかわりに経験価値が重んじられる社会に。
機械が幅をきかせる未来に、そもそも交換価値は存在しないこと。
機械が生み出した利益をベーシックインカムとして還元すること。
権力は全てを商品化しようとするが、地球を救うには全ての民主化しかないこと。
とても素晴らしい一冊だったと思う。
‘2020/04/01-2020/04/08



