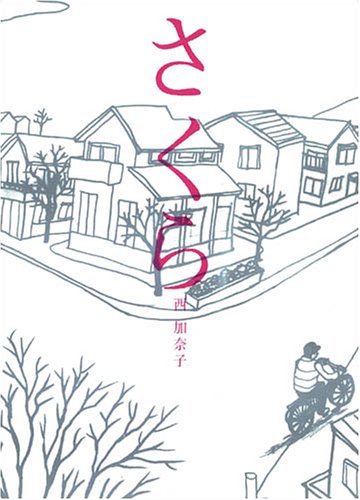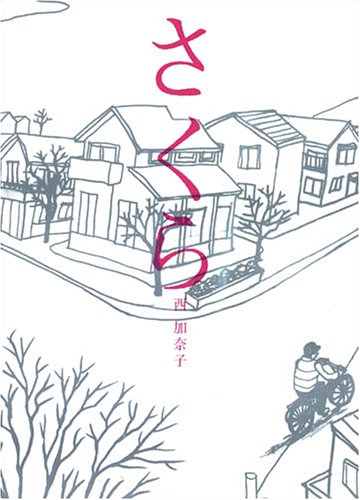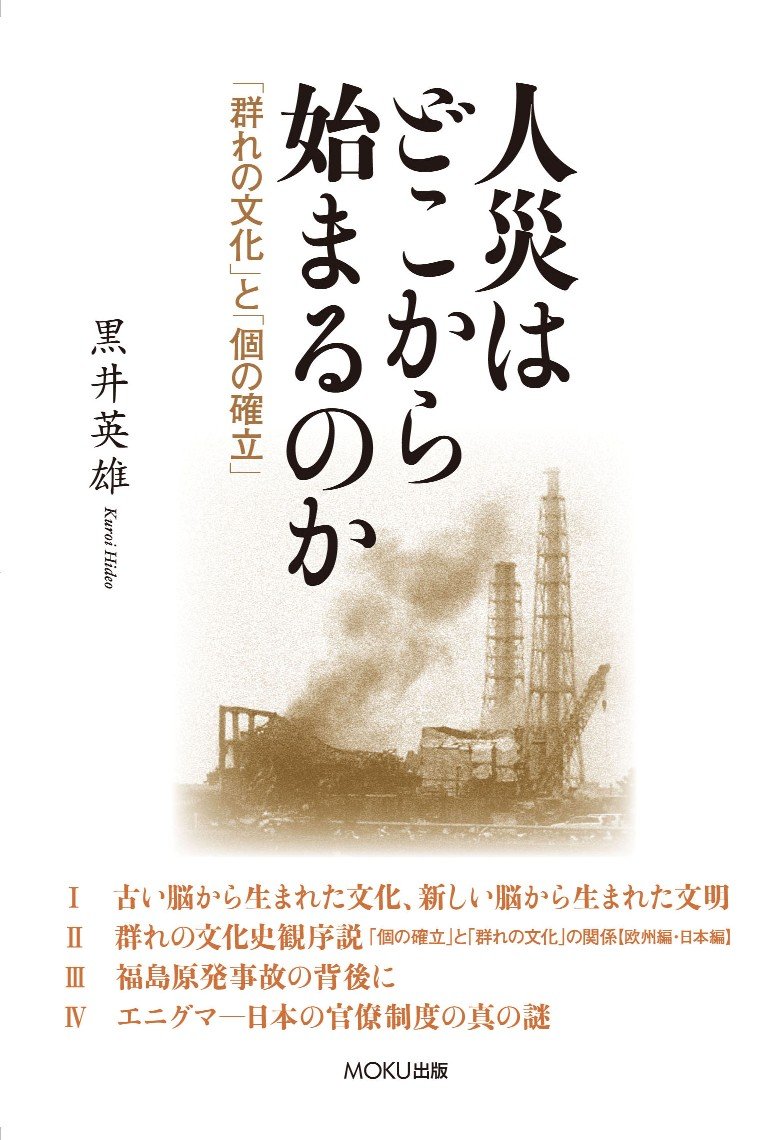
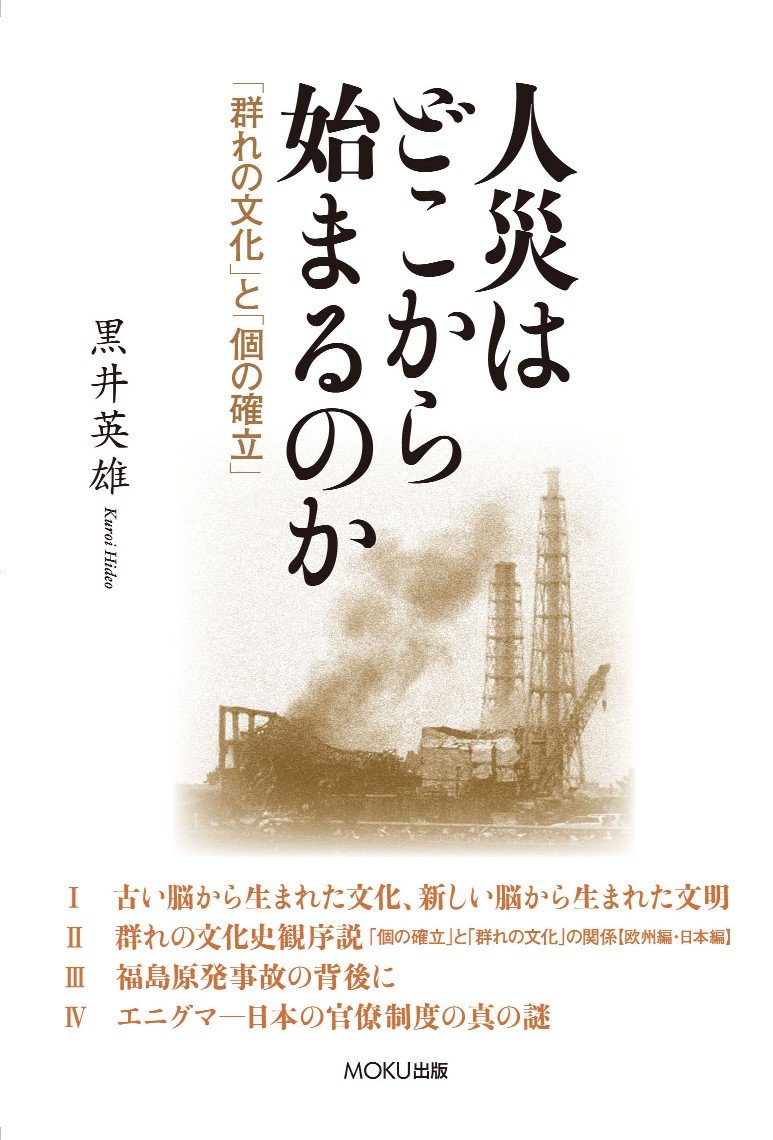
本書は、元日本原子力研究所や日本原燃株式会社といった原子力の第一線で働いていた著者が書いている。
原子力技術者が、東日本大地震が起こした惨禍とそれに伴う福島第一原子力発電所の事故を受け、贖罪の気持ちで書いたものだという。
題材が題材だからか、本書はあまりなじみのない出版社から出されている。
おそらく、本書に書かれている内容は、大手出版社では扱いにくかったのだろう。
だが、本書をそれだけの理由で読まないとしたらもったいない。内容がとても素晴らしかったからだ。
こうした小さな出版社の書籍を読むと校正が行き届いていないなど、質の悪さに出くわす事がたまにある。本書にも二カ所ほど明らかな誤植があった。
私の前に読んだどなたかが、ご丁寧に鉛筆の丸で誤植を囲ってくださっていた。
だが、その他の部分は問題がなかった。文体も端正であり、論旨の進め方や骨格もきっちりしていた。
著述に不慣れな著者にありがちな文体の乱れ、論旨の破綻や我田引水の寄り道も見られない。
しかも本書がすごいのは、きちんとした体裁を備えながら、明快かつ新鮮な論旨を含んでいる事だ。
原子力発電所の事故を語るにあたり、官僚組織の問題を指摘するだけならまだ理解できる。
本書のすごさは、そこから文化や文明の違いだけでなく、事故を起こす人の脳の構造にまで踏み込んだ事にある。
こう書くと論理が飛躍しているように思えるかもしれない。だが、著者が立てた論理には一本の芯が通っている。
著者は福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、人間の脳を含めた構造や文化から説き起こさなければ、過ちはこれからも起こりうると考えたのだろう。
事故が起こる原因を人間の文化や脳の構造にまで広げた本書の論旨は、きちんとまとまっており、新鮮な気付きを私たちに与えてくれる。
本書の主旨はタイトルにもある通り、ムレの文化が組織の危機管理の意識を脆弱にし、責任の所在が曖昧になる事実だ。
日本の組織ではムレの意識が目立っている。それは戦後の経済成長にはプラスとなった。
だが、著者は、日本が高度経済成長を達成できた背景がムレの意識ではないと指摘する。それどころか、日本の成長は技術の向上とその時の国際関係のバランスが有利に働いた結果に過ぎないと喝破する。
日本の高度経済成長に日本のムレ組織の論理はなんら影響を与えなかった。
それは私たちにとって重要な指摘だ。なぜなら、今もなお、過去の成功体験にからめとられているからだ。
著者のような高度成長期に技術者として活躍した方からなされた指摘はとても説得力がある。
その結論までを導くにあたり、著者はまずムレと対立する概念を個におく。
それは西洋の個人主義と近しい。当然だが、個人主義とは「俺が、俺が」の自分勝手とは違う。
そうした文化はどこから生まれるのだろうか。
著者は、文化を古い脳の記憶による無意識的な行動であると説く。レヴィ=ストロースの文化構造論も打ち出し、それぞれの文化にはそれぞれに体系があり、それが伝えられる中で強制力を備えると説明する。
一方で著者はフェルナン・ブローデルの唱えた「文明は文化の総体」を批判的に引用しつつ、新たな考えを提示する。その考えとは、古い脳の所産である文化に比べ、文明は新しい脳である大脳の管轄下にある。要するに、理性の力によって文化を統合したのが文明だと解釈してよいだろう。
続いて著者は西洋の文化の成り立ちを語る。西洋はキリスト教からの影響が長く強く続いた。宗派による争いも絶えず、国家も文化も細かく分かれ、摩擦が絶えなかった西洋。そのような環境は相手の信教の自由を尊重する関係を促し、個人の考えを尊重する文化が醸成された。著者はイタリア・スペイン・フランス・ドイツ・イギリス・アメリカの文化や国民性を順に細かく紹介する。
ついでわが国だ。温暖な島国であり外敵に攻め込まれる経験をしてこなかったわが国では、ムレから弾かれないようにするのが第一義だった。ウチとソトが区別され、外に内の恥を隠蔽する文化。また、現物的であり、過去も未来も現在に持ち込む傾向。
そうした文化を持つ国が明治維新によって西洋の文化に触れた。文化と文化が触れ合った結果を著者はこのように書く。
「欧州という「個の確立」の文化の下で発展した民主主義や科学技術という近代文明の「豊かさ」を享受しています。それを使い続けるならば「個の確立」の文化の下でなければ、大きな危険に遭遇する事は免れません。」(168p)
ここまでで本書は五分の三を費やしている。だが、脳の構造から文化と文明にいたる論の進め方がきっちりしており、この部分だけでも読みごたえがある。
そして本書の残りは、東日本大震災における福島第一原子力発電所の事故と、その事故を防げなかったムレ社会の病巣を指摘する。
ムレに不都合な事実は外に見せない。津波による被害の恐れを外部から指摘されても黙殺し、改善を行わない。それが事故につながった事は周知のとおりだ。
社会の公益よりムレの利益を優先するムレの行動規範を改めない限り、同様の事故はこれからも起こると著者は警鐘を鳴らす。
著者は最後に、ムレ社会が戦後の民主化のチャンスを逃し、なぜ温存されてしまったかについて説き起こす。敗戦によって公務員にも職階制を取り入れる改革の機運が盛り上がったそうだ。職階制とは公務員を特定の職務に専念させ、その職域に熟達してもらう制度で、先進国のほとんどがこの制度を採用しているそうだ。
ところが明治から続く身分制の官僚体制が通ってしまった。GHQの改革にもかかわらず、冷戦体制などで旧来の方法が通ってしまったのだという。
その結果、わが国の官僚はさまざまな部署を体験させ、組織への帰属意識とともに全体の調整者の能力を育てる制度の下で育ってしまってしまった。
著者はそれが福島第一原子力発電所の事故につながったと主張する。そして、今後は職階制への移行を進めていかねばならないと。
ただ、著者は世界から称賛される日本の美点も認めている。それがムレの文化の結果である事も。つまり「ムレの文化」の良さも生かしながら、「個の確立」も成し遂げるべきだと。
著者はこのように書いている。
「これからは、血縁・地縁的集団においては古い脳の「ムレの文化」で行動し、その一方で、感覚に訴えられない広域集団では「個の確立の文化」によって「公」の為に行動する、というように対象によって棲み分けをする状況に慣れていかなければなりません。」(262P)
本書はとても参考になったし、埋もれたままにするには惜しい本だと思う。
はじめにも書かれていた通り、本書は原子力の技術者による罪滅ぼしの一冊だ。著者の年齢を考えると自らの人生を誇らしく語るところ、著者は痛みで総括している。まさに畢生の大作に違いない。
著者の覚悟と気持ちを無駄にしてはならないと思う。
‘2020/01/30-2020/02/01