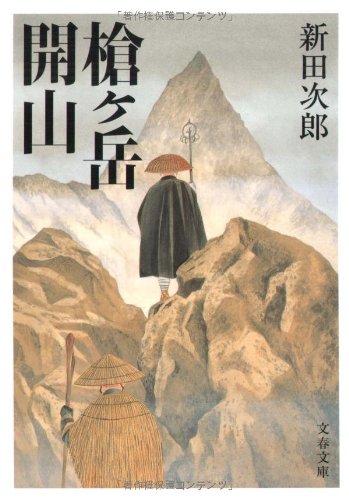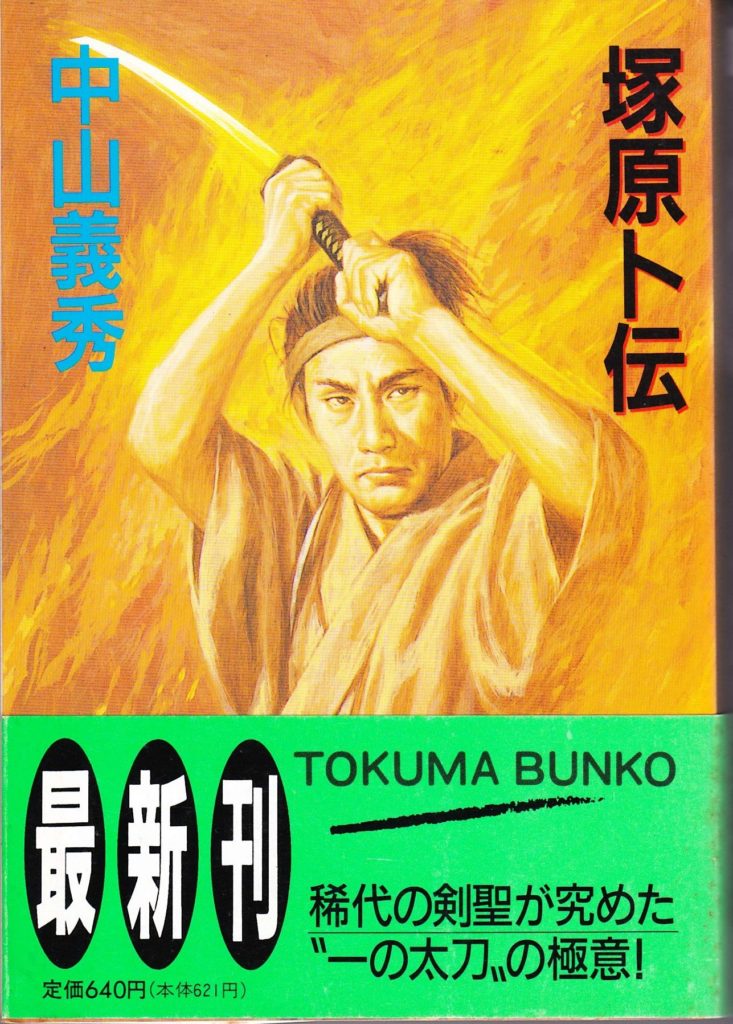
本書は、数年前に入手していた。入手したのは多分神奈川県立文学館でみた大佛次郎展で剣豪小説に興味を持ったからだと思う。わが家の蔵書に加わってから二、三年、本書は積ん読の山の中で出番を待っていた。
なぜこのタイミングで本書を読もうと思ったか。これには説明を加えなければならない。
本書が日の目を浴びたのは、鹿島神宮がきっかけだ。本書の前に読んだ『本当はすごい!東京の歴史』を読み、鹿島神宮の重みに感じ入った。そして、鹿島神宮へ行こうと思い立った。鹿島神宮の周辺で訪れるべき場所を探したところ、目に付いたのが本書の主人公である塚原卜伝だ。当然、墓や生誕地にも訪れたいと思った。となると、塚原卜伝の人となりをもう少し知っておきたい。そこで思い出したのが蔵書の中に埋もれていた本書だ。
本書を読み終えたのは鹿島へ向かう前日。なので、私が鹿島を訪れた時、塚原卜伝の生涯はある程度理解していた。そればかりか、鹿島が武の本拠といってよいことも。
私が鹿島に着いた時、夜はかなり更けていた。さっそく大鳥居から楼門まで歩いてみたが、深閑とした森の奥からは、剣道の稽古と思しき気合いの掛け声が聞こえてくる。鹿島が塚原卜伝を輩出した武の地との本書から得た知見が実感として迫る。鹿島に塚原卜伝あり、を早々に思い知らされた。塚原卜伝を産んだ風土の風がいまだに残されている事も。
翌日、鹿島の周辺を巡った私は、想像した以上に塚原卜伝が鹿島の街で重んじられていることを知った。塚原卜伝のお墓は少し登った高台の崖に面している。そこから見た田園風景がとても心地よかった。お墓の前で手を合わせ、泉下の剣豪にあいさつも済ませた。また、鹿島神宮駅前に立つ銅像にも訪れた。鹿島神宮の境内には剣豪にちなんだ多くの名所があり、そこにも足を運んだ。
鹿島とは日本の東の端にある。そこから世に出た塚原卜伝は、日本の各地を旅と修行の中に歩いた。ちょうど近隣の佐原から出た伊能忠敬のように。藤原氏の祖である藤原鎌足もまた鹿島の出だという。つまり、鹿島とは人を旅立たせる外交の気に満ちているのかもしれない。
塚原卜伝とは、剣の達人であり、流派の創始者でもある。その剣は人を活かす剣ともいわれ、戦わずして勝つことを最善とする。つまり、人を殺めたり、凄惨な争いを避ける剣だ。そればかりでなく、人としての道を説くことに重きが置かれているという。それゆえに今でも鹿島では塚原卜伝が思慕され、顕彰され続けているのかもしれない。
塚原卜伝が生を享けたのは、戦国時代の始まりとも言われる応仁の乱が終わって十数年後だ。その頃はまだ、室町幕府の意向が諸国に行き届いており、諸大名の間で大規模な戦が行われることはなかった。
その後に訪れた桶狭間の戦いから関ヶ原の戦いに至る四十年間。その四十年間は、各国が戦いに明け暮れ、いきをつく暇もなかった。織田信長の動きに日本国が揺り動かされ、その跡を襲った徳川家康によって大勢が定まるまでの時期。国々か富国強兵に努め、雌雄を決する大規模な合戦があちこちで行われた。つまり、大名を頂点とした組織の論理が優先され、個人が自在に自己を研鑽できにくくなった時代だ。
塚原卜伝にしろ、上泉信綱にしろ、宮本武蔵にしろ、当時名前を上げた剣豪たちは、その四十年間の前後に活躍している。逆にいえば、剣豪たちが名を上げられたのは、軍隊という組織の論理に左右されなかったからだといえる。剣豪が剣豪でいられたある意味では幸せな時期。
だから、本書で描かれる卜伝の歩みには組織の論理が希薄だ。殺伐としてはいるが、組織によって行動が左右されない。己の剣を磨き、諸国修行に明け暮れられる。それはまさに私の望む人生観である。読んでいてとても心地よい。
よくよく考えてみると、個人が組織の論理に飲み込まれる前の時期を描いた時代小説は珍しいかもしれない。そうした時期を象徴するのが、本書で描かれる足利将軍家だ。三好軍や細川軍の動向に右往左往し、京を慌ただしく逃げ出し、そして庇護者を見つけてはひそかに舞い戻る。
腰の定まらぬ将軍家に剣の腕を見込まれ、護衛につく卜伝は、将軍家の動きに合わせてあちこちをさすらう。それに合わせて本書の舞台も日本各地を転々とする。
なお、卜伝に関しては、さまざまな伝説が語られている。そうした挿話は本書には登場しない。例えば、宮本武蔵が家に殴り込んできたとき、持っていた鍋の蓋で刃を受け止めたこと。「無手勝流」の由来となった、決闘の場で島に船をつけ、逸って島に降り立った相手を残して悠然と漕ぎ去っていったこと。武者修行と称して総勢数十名のお供のものを引き連れたことなど。最初の挿話はそもそも生年が重なっておらず、本書は取り上げないし、残りの二つも著者は取り上げるまでもないと判断したのだろう。そもそも本書は卜伝の後半生は描いていない。
もちろん、本書は神宮の杜で卜伝が一の太刀を会得する事や、立ち会い試合で一の太刀で池田真龍軒を屠る場面など、武芸者としての卜伝も存分に描かれる。梶原長門との一件も。だが、それと同じぐらい本書には、道を極めんとする卜伝の姿が描かれる。中でも卜伝が詠んだとされる百首の連歌はこの句で締められ興味深い。
学びぬる心にわざの迷いてや
わざの心の又迷うらん(347ページ)
卜伝は諸国修業の末、全てが剣の道に通ずることを悟る。諸国でさまざまな人物と出会う。その中には、己の腕を見込み、頼ってくる若輩もいた。その若輩はのちに川中島合戦で名を轟かせる山本勘助の若き日の姿。また、上泉秀綱との交わりなども描かれる。孤高になりやすい剣の人でありながら、人との縁に恵まれる。それもまた、組織のしがらみの弱い時代のおおらかさ故だろうか。
なかでも、卜伝が若き日に救った玉路が宿す美少女の面影は、とうとう卜伝を剣の魔界から逃れさせた。人の弱さを存分に知り、人の交わりのありがたみを知ったこと。そして、時代が個人の生きる道を用意していたこと。そうした幸運が卜伝を独自の剣の境地に高めたのだろう。
迷いなし。その境地こそ、あらゆる価値観が錯綜する現代に必要なものではないか。私は鹿島への旅でその大切さを知った。
‘2018/07/13-2018/07/14