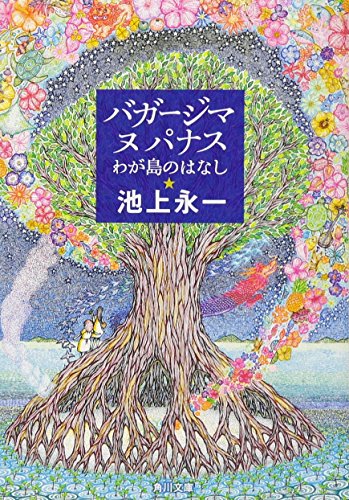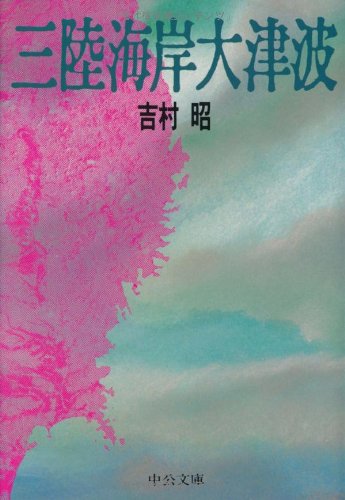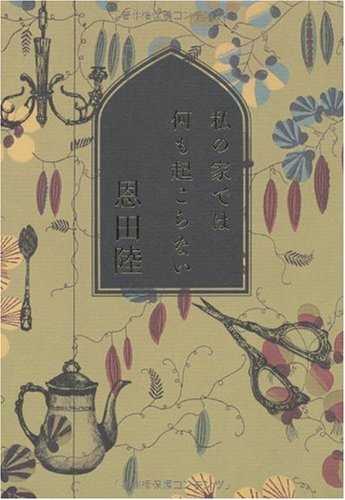
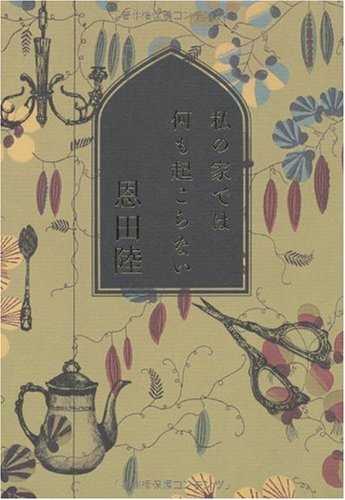
本書は一軒の家についての本だ。ただし、家といってもただの家ではない。幽霊の住む家だ。
それぞれの時代に、さまざまな人物が住んでいた家。陰惨な出来事や代々の奇矯な人物がこの家で怪異なエピソードを紡いできた。そうした住人たちが残したエピソードの数々がこの家にさらなる怪異を呼び込み、さらなる伝説を産み出す。
本書は十編からなっている。各編はこの家を共通項として、互いに連関している。それぞれの編の舞台はばらばらだ。時間の流れに沿っていない。あえてバラバラにしている。バラバラにすることでかえって各エピソードの層は厚みを増す。なぜならそれぞれの物語は互いに関連しあっているから。
もちろん、そこには各エピソードの時間軸を把握した上で自在に物語を紡ぐ著者の腕がある。家に残された住人たちの思念は、無念を残したまま、その場をただよう。住人たちによっては無残な死の結果、人体の一部が残されている。人体に宿る思念が無念さを抱けば抱くほど、家には思念として霊が残る。この家の住人は、不慮の事故や、怖気を振るうような所業によって命を落として来た。そうした人々によるさまざまな思念と、そこから見たこの家の姿が、さまざまな角度でこの家を描き出し、読者へイメージとして伝えられる。
世にある幽霊屋敷とは、まさにこのようなエピソードと、残留した想いが作り上げて行くのかもしれない。不幸が不幸を呼び、思念が滞り、屋敷の中をこごってゆく。あまたある心霊スポットや幽霊屋敷とは、こうやって成り立ってきたに違いない。そう、読者に想像させるだけの力が本書にはある。冒頭の一編で、すでにこの家には好事家が集まってきている。彼らは、家主の都合など微塵も考えず、今までにこも屋敷を舞台として起こったあらゆる伝説や事件が本当だったのか、そして、今も誰も知らぬ怪異が起こっているのではないか、と今の持ち主に根掘り葉掘り尋ねる。迷惑な来訪者として、彼らはこの家の今の持ち主である女流作家の時間を容赦なく奪ってゆく。もちろん、こうした無責任な野次馬が幽霊屋敷の伝承にさらなる想像上の怪異を盛り付けてゆくことは当然のこと。彼らが外で尾ひれをつけて広めてゆくことが、屋敷の不気味さをさらに飾り立ててゆくことも間違いない。
たとえ幽霊屋敷といえど、真に恐るべきなのは屋敷でなければ、その中で怪異を起こすものでもない。恐るべきは今を生きている生者であると著者はいう。
「そう、生者の世界は恐ろしい。どんなことでも起きる。どんな悲惨なことでも、どんな狂気も、それは全て生者たちのもの。
それに比べれば、死者たちはなんと優しいことだろう。過去に生き、レースのカーテンの陰や、階段の下の暗がりにひっそりと佇んでいるだけ。だから、私の家では決して何も起こらない。」(26p)
これこそが本書のテーマだ。怪異も歴史も語るのは死者ではなく生者である。生者こそが現在進行形で歴史を作り上げてゆく主役なのだ。死者は、あくまでも過去の題材に過ぎない。物事を陰惨に塗り替えてゆくのは、生者の役割。ブログや小説やエッセイや記事で、できごとを飾り立て、外部に発信する。だから、一人しか生者のいないこの家では決して何も起こらないのだ。なぜなら語るべき相手がいないから。だからエピソードや今までの成り立ちも今後は語られることはないはず。歴史とは語られてはじめて構成へとつながってゆくのだ。
つまり、本書が描いているのは、歴史の成り立ちなのだ。どうやって歴史は作られていくのか。それは、物語られるから。物語るのは一人によってではない。複数の人がさまざまな視点で物語ることにより、歴史には層が生じてゆく。その層が立体的な時間の流れとして積み重なってゆく。
そして、その瞬間の歴史は瞬間が切り取られた層に過ぎない。だが、それが連続した層で積み重なるにつれ、時間軸が生じる。時間の流れに沿って物語が語られはじめてゆく。過ぎていった時間は、複数の別の時代から語られることで、より地固めがされ、歴史は歴史として層をなし、より確かなものになってゆく。もちろん、場合によってはその時代を生きていない人物が語ることで伝説の色合いが濃くなり、虚と実の境目の曖昧になった歴史が織り上げられてゆく。ひどい場合は捏造に満ちた歴史が後世に伝わってしまうこともあるはずだ。
しょせん、歴史とは他の時代の人物によって語り継がれた伝聞にしか過ぎず、その場では成り立ち得ないものなのだろう。
著者は本書を、丘の上に建つ一軒家のみを舞台とした。つまり、他との関係が薄く、家だけで完結する。そのように舞台をシンプルにしたことで、歴史の成り立ちを語る著者の意図はより鮮明になる。本来ならば歴史とは何億もの人々が代々、語り継いでいく壮大な物語だ。しかしそれを書に著すのは容易ではない。だからこそ、単純な一軒家を舞台とし、そこに怪異の色合いをあたえることで、著者は歴史の成り立ちを語ったのだと思う。幽霊こそが語り部であり、語り部によって歴史は作られる。全ての人は時間の流れの中で歴史に埋もれてゆく。それが耐えられずに、過去からさまよい出るのが幽霊ではないだろうか。
‘2018/07/24-2018/07/25