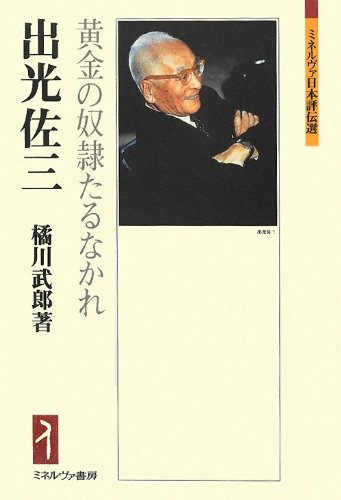本書は、紹介してもらわなければ一生読まずに終わったかもしれない。人体に施す代表的な73の手術をイラスト付きで紹介した本。貸してくださったのはマニュアル作りのプロフェッショナル、情報親方ことPolaris Infotech社の東野さんだ。
なぜマニュアル作りのプロがこの本を勧めてくださったのか。それはマニュアル作りの要諦が本書にこめられているからに違いない。手術とは理論と実践が高度に求められる作業だ。症例を理論と経験から判断し、患部に対して的確に術を施す。どちらかが欠ければ手術は成功しないはずだ。そして、手術が成功するためには、医療を施す側の力だけでなく、手術を受ける側の努力も求められる。患者が自らに施される手術を理解し、事前の準備に最大限の協力を行う。それが手術の効果を高めることは素人の私でもわかる。つまり、患者が手術を理解するためのマニュアルが求められているのだ。本書こそは、そのための一冊だ。
本書が想定する読者は医療に携わる人ではない。私のように医学に縁のない者でもわかるように書かれている。医療の初歩的な知識を持っていない、つまり、専門家だから知っているはず、という暗黙の了解が通用しない。また、私のような一般の読者は体の組織を知らない。名前も知らなければ、位置の関係にも無知だ。手術器具もそう。本書に載っている器具のほとんどは、名称どころか機能や形についても本書を読むまで知らなかったものばかり。各病気の症状についての知識はもちろんだ。
手術をきちんと語ろうと思えばどこまでも専門の記述を盛り込める。だが、本書は医療関係者向けではなく、一般向けに書かれた本だ。そのバランスが難しい。だからこそ、本書は手術を受ける患者にとって有益な1冊なのだ。そしてマニュアルとしても手本となる。なぜなら、マニュアルとは本来、お客様のためにあるべきだからだ。
これは、ソフトウエアのマニュアルを考えてみるとわかりやすい。システムソフトウエアを使うのは一般的にユーザー。ところがそのシステムを作るのはシステムエンジニアやプログラマーといった技術者だ。システムの使用マニュアルは普通、ユーザー向けに提供される。もちろん、技術者向けのマニュアルもある。もっとも内部向けには仕様書と呼ばれるが。家電製品も同じ。製品に同梱されるマニュアルは、それを使う購入者のためのものであり、工場の従業員や設計者が見る仕様書は別にある。
そう考えると、本書の持つ特質がよく理解できる。医師や看護師向けのマニュアルとは一線を画し、本書はこれから不安を抱え、手術を受けるための患者のためのもの、と。
だから本書にはイラストがふんだんに使われる。イラストがなければ患者には全く意味が伝わらない。そして、使われるイラストも患者がシンプルに理解できるべき。厳密さも精細さも不要。患者にとって必要なのは、自分の体のどこが切り刻まれ、どこが切り取られ、どこが貼り直され、どこが縫い合わされるかをわかりやすく教えてくれるイラスト。位置と形状と名称。これらが患者の脳にすんなりと飛び込めば、イラストとしては十分なのだ。本書にふんだんに使われているイラストがその目的に沿って描かれていることは明らかだ。体の線が単純な線で表されている。そして平面的だ。
一方で、実際に施術する側にとってみれば、本書のイラストは全く情報量が足りない。手術前に検討すべきことは複雑だ。レントゲンの画像からどこに病巣があるかを読み取らなければならない
。手術前の事前のブリーフィングではどこを切り取り、どうつなぎ合わせるかの施術内容を打ちあわせる。より詳しいCT/MRI画像を解読するスキルや、実際に切開した患部から即座に判断するスキルを磨くには、本書のイラストでは簡潔すぎることは言うまでもない。
イラストだけではない。記述もそうだ。一概に手術を語ることがどれだけ難しいかは、私のような素人でもわかる。病気と言っても人によって症状も違えば、処方される薬も違う。施術の方法も医師によって変わるだろう。
そして、本書に描かれる疾患の要素や、処置の内容、処方される薬などは、さらに詳しい経験や仕様書をもとに判断されるはず。そのような細かく専門的な記述は本書には不要なのだ。本書には代表的な処置と代表的な処方薬だけが描かれる。それで良いのだ。詳しく描くことで、患者は安心するどころか、逆に混乱し不安となるはずだから。
ただ、本書はいわゆるマニュアルではない。一般的な製品のマニュアルには製造物責任法(PL法)の対応が必要だ。裁判で不利な証拠とされないように、やりすぎとも思えるぐらいの冗長で詳細な記載が求められる。本書はあくまでも手術を解説した本なので、そうした冗長な記述はない。
あくまでも本書は患者の不安を取り除くための本であり、わかりやすく記すことに主眼が置かれている。だからこそ、マニュアルのプロがお勧めする本なのだろう。
本書を読むことで読者は代表的な73の手術を詳細に理解できる。私たちの体はどうなっていて、お互いの器官はどう機能しあっているのか。どのような疾患にはどう対処すべきなのか、体の不調はどう処置すれば適切なのか。それらは人類の叡智の結晶だ。本書はマニュアルの見本としても素晴らしいが、人体を理解するためのエッセンスとしても読める。私たちは普段、生き物であるとの忘れがちな事実。本書はそれを思い出すきっかけにもなる。
本書に載っている施術の多さは、人体がそれだ多くのリスクを負っている事の証だ。73種類の中には、副鼻腔の洗浄や抜歯、骨折や虫垂炎、出産に関する手術といったよくある手術も含まれている。かと思えば、堕胎手術や包茎手術、心臓へのペースメーカー埋め込みや四肢切断、性転換手術といったあまり出会う確率が少ないと思われるものもある。ところが、性別の差を除けばどれもが、私たちの身に起こりうる事態だ。
実際、読者のうちの誰が自分の四肢が切断されることを想定しながら生きているだろう。出産という人間にとって欠かせない営みの詳しい処置を、どれだけの男性が詳しく知っているだろう。普段、私たちが目や耳や口や鼻や皮膚を通して頼っている五感もそう。そうした感覚器官を移植したり取り換えたりする施術がどれだけ微妙でセンシティブなのか、実感している人はどれだけいるだろうか。
私たちが実に微妙な身体のバランスで出来上がっているということを、本書ほど思い知らせてくれる書物はないと思う。
人体図鑑は世にたくさんある。私の実家にも家庭の医学があった。ところが本書に載っているような手術の一連の流れを、網羅的に、かつ、簡潔にわかりやすく伝えてくれる本書はなかなかみない。実は本書は、家庭の医学のように一家に一冊、必ず備えるべき書物なのかもしれない。教えてくださった情報親方に感謝しなければ。
‘2018/08/22-2018/09/03