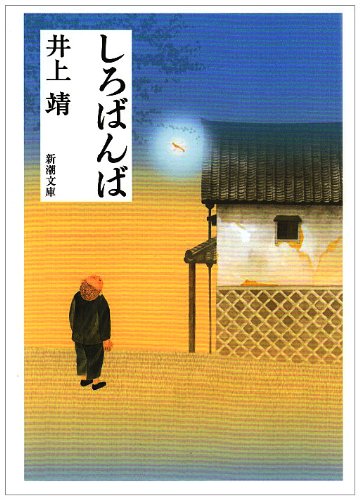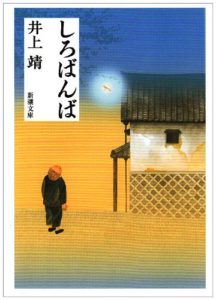著者の書く文章が好きだ。
端正でいて簡潔。新聞記者から小説家になった経歴ゆえ、まず伝わる文章を徹底的に鍛えられたからだろうか。読んでいて安心できる。
そうした、端正な文章が、地上最大の帝国ともいわれるモンゴル帝国を一代で築き上げたチンギス・ハーンをどう描くのか。前々から本書は一度読んでみたいと思っていた。ようやくこの機会に一気に読み終えることができた。
本書の主人公はテムジン(鉄木真)だ。テムジンはモンゴルの一部族を率いるエスガイとその妻ホエルンの間に生まれた。
当時のモンゴルはさまざまな部族が争っており、中国の平原を治めていた金からすれば与し易い相手だった。
たまにモンゴルと金の間で小競り合いが起こる度、部族の首長の誰かが惨たらしく殺されていた。
口承による伝達が主だった当時のモンゴルで、先祖が惨たらしい目にあった悲劇が伝えられる。何度も何度も。話を聞かされる間に、幼いテムジンに金への憎しみを植えつけていった。
もう一つ、テムジンには悩みがあった。
生まれた頃、母ホエルンはメルキト部に拉致された。メルキト部の男たちに犯され、すぐにエスガイに奪還された。そしてテムジンを産んだ。
つまり、テムジンの父はエスガイなのか、それとも他の誰かなのか。誰にもわからない。幼いテムジンがふと知ってしまったこの疑惑に、テムジンは死ぬまで悩み続ける。
本書はエスガイとホエルンを描くことから筆を起こし、テムジンの出生の悩みのみなもとを描いている。
テムジンが幼い頃から聞かされ続けた伝承は他にもある。
「上天より命ありて生まれたる蒼き狼ありき。その妻なる慘白き牝鹿ありき」
で始まる伝承。それは祈祷の形をとっていた。その話を聞かされ続けるうちに、テムジンの胸にはモンゴル部に生まれた誇りが燃え盛っていった。それとともに、蒼き狼の子孫として恥じぬように生きたい、との思いも。
ところが、自らの血にメルキト部の誰ともしれぬ血が混じっているかもしれない。その恐れがテムジンを苛んでゆく。
その恐れこそが、テムジンの飽くなき征服欲の源泉であり、生涯をかけてテムジンを駆り立てた。そのテーマを掘り下げるため、著者はテムジンの心をむしばむ疑いを何度も違う角度から掘り下げる。
エスガイの不慮の死により、モンゴル部はテムジンとエスガイの係累を除いていなくなってしまう。
テムジンの身の回りの肉親だけになってから、少しずつ勢力を盛り返してゆくモンゴル部。必死に勢力を戻そうとするテムジンの奮闘が描かれる。
あらゆる人や組織の一代記に共通することがある。
それは、若年期や創業期の試練を丁寧に描くことだ。最初の頃は試練が続き、歩みも遅い。
それがある一点を超えた途端、急速に発展していく。加速度がつくように。
それは自分自身にスキルが身につき、はじめは苦労していたことがたやすく成し遂げられるようになるため。
もう一つは経験が人を集め、それを活用することでさらなる成長につながるため。
それは私自身の人生を顧みてもわかる。
伝記に費やされる字数も同じだ。苦労して成長の歩みが遅い時期は濃密に描かれるため、速度も遅い。
だが、一度軌道に乗った後は濃度が薄くなり、読む速度も加速する。
本書もその通りの展開をたどっている。
だが、著者は規模が大きくなったモンゴル部を描くにあたり、ある工夫を施している。そのため、立ち上がりの苦労をして以降の本書は、濃度を薄めずに読みごたえを保つことに成功している。
それは長男のジュチは、果たしてテムジンの血を受け継いだ息子か、という疑問だ。
テムジンの妻ボルテも、結婚の前後に他部族に拉致された。それはテムジンの母ホエルンがたどった軌跡と同じ。
自分の血ですら定かではないのに、自らの長男もまた同じ運命にとらわれてしまう。
ジュチは、父が自分に対して他の兄弟とは違う感情を抱いていることを察する。そのため、自分が父の息子であることを証明するため、なるべく困難で試練となる任務を与えてほしいと願う。
その心のうちを承知しながら、あえて息子を遠くに送り出す父。
本書を貫くテーマは、父と息子の関係性だ。それが読者の興味を離さない。
もう一つは、男女の役割のあり方だ。草原に疾駆するモンゴルの男にとって、子育ての間に自由に動けない女はとるに足らない存在でしかなかった。
その考えにテムジンも強く縛られている。それは彼の行動原理でもある。敵の女は全てを犯し、適当にめとわせる。
ところが、メルキト部を破った後に得た忽蘭(クラン)は違った。それは女ではあるが、自分の意思を強く持っていることだ。従順なだけで手応えのないそれまでに知った女性とは違う存在。
忽蘭は戦地であっても側においておかねば死ぬといい、従軍もいとわない。そんな忽蘭はテムジンを引きつけ、数ある愛妾の中でも寵愛を受ける。
だが、忽蘭がテムジンの子を身ごもったことで、二人の関係に変化が生じる。
そうした描写からは、今の感覚でいくら平等を唱えようとも、生物が縛られる制約だけはいかんともしがたい運命が見える。
そうした生物の身体に関する不平等は、力こそが全てで、衝動と本能のままに動く当時のモンゴル帝国では当たり前の考えのだからこそ、鮮やかに浮き上がってくる。
文明に慣れ、蒼き狼でも白き牝鹿でもない現代人にとって、男女平等の考えは当たり前だ。
だが、この文明が崩壊し、末法の世に陥った時、男女のあり方はどう変わってゆくのか。
本書から考えさせられた点の一つだ。
また、本書は文化の混淆もテーマになっている。
本書の終盤では、モンゴル帝国の版図が拡大するにつれ、遠いホラズムとも交流が生じた。そのホラズムの文物に身を包む雄々しきモンゴルの武将たちの姿に違和感を抱いたテムジン、あらためチンギス・ハーンが、自分だけはモンゴルの部族のしきたりに従っていこうと決意する姿が描かれている。
版図が拡大すると、違う文化に触れる。それはまさに文化の混合の姿でもある。
今やその混合が極点に達した現代。現代において急速に混じり合う文化のありようと、モンゴルが武力でなし得た文化の混合のありようを比較すると興味深い。
本書の巻末には著者自身による「『蒼き狼』の周囲」と題した小論が付されている。創作ノートというべき内容である。
その冒頭に小矢部全一郎氏の「成吉思汗は源義経也」が登場する。著者が本書を描くきっかけとなったのは、成吉思汗=源義経説に感化されたというより、そこからチンギス・ハーンの生涯が謎めいていることに興味を持ったためだという。
私が最も再読した二冊のうちの一冊が高木彬光氏の「成吉思汗の秘密」だ。とはいえ、本書には成吉思汗=源義経説が入り込む余地はないと思っていた。そのため、著者が記したこの成り立ちには嬉しく思った。
‘2020/02/14-2020/02/17