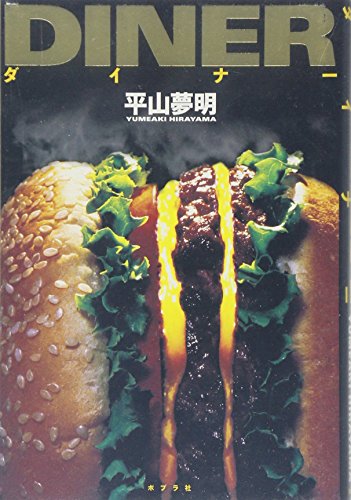二年続けて沖縄に旅した時から早くも四年が過ぎ、コロナの中で逼塞する毎日。
振り返って旅がしたいと思い、本書を手に取った。
沖縄には今まで三回訪れた。
1995年9月は大学の部合宿で20名の同輩や後輩と。那覇港に船から上陸し、名護までタクシー。名護近くのホテルに泊まり、海辺で遊び。翌日はレンタカーで南部へ。おきなわワールドではハブとマングースの戦いを見、ひめゆりの塔の厳粛な雰囲気に衝撃を受けた。国際通りで散々飲み明かした翌日は首里城へ。
若さを謳歌した旅の中、ひめゆりの塔で受けた衝撃の落差がいまだに印象に残っている。
2017年6月のニ度目の訪問は一人旅で訪れた。初日はあいにくの大雨だったが、忠孝酒造で泡盛の製造工程を見学し、沖縄そばの味を求めて数店舗を訪れた。旧海軍司令部壕では太田中将の遺徳をしのび、沖縄県平和祈念資料館では沖縄戦だけでない、戦前の窮乏と戦後の米軍軍政下の沖縄についても学んだ。夜は国際通りの居酒屋で一人で飲んだ。翌日は晴れ渡った知念岬で太平洋の広さに沖縄が島であることを実感し、神域にふさわしい荘厳な斎場御嶽の姿に心から感動した。ひめゆりの塔では資料館をじっくりと鑑賞し、22年前に受けた衝撃を自分の中で消化した。
2018年3月には家族で。知念岬を見せたいと連れて行った後は、アブチラガマへ。完全な暗闇の中、亡くなられた方々の味わった絶望と不条理と無念を追体験した。さらにはひめゆりの塔へ。
翌日は美ら海水族館へ。途中に立ち寄った崎本部緑地公園のビーチの美しさに歓声を上げ、夜は北谷のアメリカンビレッジへ。栃木から沖縄移住した友人のご家族と食事を楽しみ、沖縄への移住についての話を伺った。
最終日は伊計島の大泊ビーチへ。その途中には浜比嘉島のシルミチューとアマミチューの遺跡を。大泊ビーチは素晴らしかった。帰りには伊計島灯台に寄り、さらにキングタコスの味を堪能し、勝連城跡の勇壮な様子に感動した。那覇に戻って国際通りで買い物をして、帰路に就いた。
なぜ本書にじかに関係のなさそうな私の旅を記したか。
それは私の沖縄の旅が、通り一遍の平和とリゾートだけの旅でないことを示したかったからだ。これらの度で私が巡ったコースは、平和とリゾートの二つだけでない、バラエティに富んだ沖縄を知りたいとの望みを表している。
だが、沖縄はまだまだ奥が深い。
沖縄はしればしるほどそこが知れなくなる。とても重層的な島だ。
平和やリゾートを軸にした通り一遍の見方では沖縄は語れないし、語ってはいけないと思う。だが、私ごときが違った沖縄を味わおうとしても、しょせんは旅人。よく知るべきことは多い。
例えば著者のようなプロの手にかかると。
本書は、ノンフィクションライターである著者が表向きのガイドマップ向けに語られる沖縄ではなく、より深く、予想外の切り口から沖縄のさまざまな実相を描いている。
上巻である本書が描くのは、基地の島の実相と、沖縄の経済、そして任侠の世界だ。
Ⅰ 天皇・米軍・おきなわ
これはタイトルからしてすでにタブーに踏み込むような雰囲気が漂っている。
とはいっても、そこまで過激な事は書かれていない。ただ、本章では昭和天皇がとうとう一度も沖縄を訪れなかったことや、沖縄県警が沖縄戦を経て戦後の米軍の軍政下でどのような立場だったか、そうした沖縄が置かれた地位の微妙な部分がなぜ生じたのかに触れている。
本書の冒頭としてはまず触れておくべき点だろう。
Ⅱ 沖縄アンダーグラウンド
これは、本書を読まねば全く知らなかった部分だ。どこの国にもどの地域にもこうしたアンダーグラウンドな部分はある。
沖縄にももちろんそうした勢力はあるのだろう。だが、旅行者としてただ訪れるだけではこうした沖縄の後ろ暗い部分は見えてこない。
こうした部分を取材し、きちんと書物に落とし込めるのが著者のノンフィクション作家としての本領だろう。
むしろ、米軍の軍政下にあったからこそ、そうした光と闇をつなぐ勢力が隙間で棲息することができたのではないだろうか。
戦前から戦後にかけ、沖縄はさまざまな政治と勢力が移り変わった。権力が空白になり、権力が超法規的な状態の中で生き延びるやり方を学び、鍛え上げていった勢力。そこで狡猾な知恵も発達しただろう。これは旅行者やガイドブックにはない本書の肝となる部分だと思う。
沖縄の人々は被害者の地位に決して汲々としていたのではなく、その中でも研げる牙は研いできたのだろう。
Ⅲ 沖縄の怪人・猛女・パワーエリート(その1)
その1とあるのは、下巻でもこのテーマが続くからだ。
沖縄四天王という言葉があるが、戦後の米軍の軍政下でも力を発揮し、成長した経済人が何人もいる。
日本本土にいるとこうした情報は入ってこない。沖縄のアンテナショップに行けば、沖縄の産物は入ってくる。本章にも登場するオリオンビールのように。
だが、その他にも何人もの傑物が戦後の沖縄で力をつけ、日本へ復帰した後もその辣腕をふるった。
立志伝の持ち主は沖縄に何人もいるのだ。
‘2020/08/19-2020/08/23