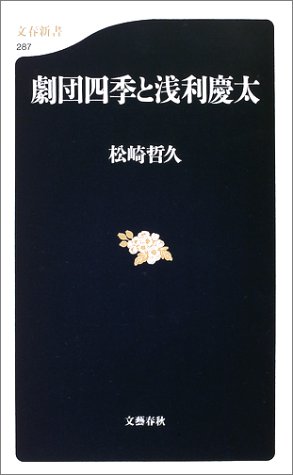年末の30日に家族で四人揃って本作を見た。
うちの家族は、昔から『チャーリーとチョコレート工場』が好きだ。
私も何度も観た。おそらく、4、5回は。
私の経験を踏まえて本作についてのレビューを本稿にまとめた。
絶賛上映中なので、本稿ではまだ観ていない方の興を削がないように配慮する。
配慮するつもりだが、本作の内容について語るので、本稿のつづきは劇場で観てから読んだ方が良いと思う。
本作は『チャーリーとチョコレート工場』の世界観を踏襲し、ウィリー・ウォンカがチョコレート工場を作るまでを描いている。
なお、本作を観た後、家族で1971年に公開された映画『夢のチョコレート工場』も観た。
『夢のチョコレート工場』は原作者のロアルド・ダールが存命中に公開されたため、原作の世界観を踏襲しているのは明らかだ。
『チャーリーとチョコレート工場』は『夢のチョコレート工場』とシナリオや登場人物がほぼ同じ。正統なリメイク版として『チャーリーとチョコレート工場』がある。ただし、リメイクにあたってはいくつかの設定が変更されている。
それを踏まえ、本稿ではジョニー・デップがウィリー・ウォンカを演じた『チャーリーとチョコレート工場』とジーン・ワイルダーがウィリー・ウォンカを演じた『夢のチョコレート工場』の違いにも言及する。
大きく設定が変更されているのはウンパルンパの扱いだ。
『夢のチョコレート工場』では、鮮やかなオレンジ色の顔に緑色の髪がウンパルンパの外見的な特徴として描かれていた。ウンパルンパのテーマを歌いながら踊る姿はとてもコミカル。
「ウンパルンパ ドゥンパティ ドゥ♪」とうたいながら踊るさまはまさに愛すべきキャラクターだ。
ところが、『チャーリーとチョコレート工場』でディープ・ロイが演じたウンパルンパのイメージは一新されている。最新技術を使って約160名の全員が同じ顔で踊るインパクトもさることながら、その踊りと歌に込められたブラックなシニカルさが洗練され、映画のインパクトに華を添えていた。
『夢のチョコレート工場』の素朴なウンパルンパが『チャーリーとチョコレート工場』の洗練されたウンパルンパに変わることで、ブラックな面白さがより強調されていたように思う。
本作のいくつかの設定、特にウンパルンパの外観は『チャーリーとチョコレート工場』より『夢のチョコレート工場』に近い。
つまり、原作者が想定していた世界観により忠実だと思う。
本作でヒュー・グラントが演じるウンパルンパも、登場シーンでウンパルンパのテーマを歌い踊る。鮮やかなオレンジ色の顔に緑色の髪を持つより原作のイメージに近い外見で。
本作に登場するウンパルンパは、ほぼヒュー・グラントによる一人のみだ。
160名のウンパルンパのインパクトには劣るが、ヒュー・グラントがもともと持っているシニカルでブラックなユーモアがうまく活かされていて、それが面白さになっていたと思う。
とても素晴らしいウンパルンパの再解釈だと思う。
ただし、本作にはブラックでシニカルな原作の良さがあまり感じられなかった。ヒュー・グラントが扮するウンパルンパだけがそれを体現していたように思う。
むしろ、ブラックでシニカルなユーモアを体現していたのが、『チャーリーとチョコレート工場』ではウィリー・ウォンカで、ウンパルンパは無表情で歌い踊ってウィリー・ウォンカのブラックな側面を強調していた。本作ではウィリー・ウォンカからブラックでシニカルな部分が姿を消し、その点を受けついだのがウンパルンパだったともいえる。
『夢のチョコレート工場』と『チャーリーとチョコレート工場』には、善と悪といったわかりやすい構図がない。むしろ、主人公のウィリー・ウォンカのつかみどころのなさこそが、作品全体の特色だ。
ウィリー・ウォンカは何を考え、登場人物はどこに連れて行かれるのか。そこにドラマの興味は絞られていた。
ところが、ティモシー・シャラメが演じる本作のウィリー・ウォンカは夢をもち、希望を語り、マジカルな能力とそこから作り出す魔法のチョコを使って人々を魅了する善人として描かれている。
カルテルを組んで街のチョコレート流通を支配し、ウィリー・ウォンカを抹殺しようとする三人組やチョコレートで三人組に籠絡される悪辣警察署長が悪で、それに対するウィリー・ウォンカという構図。そのため、ブラックでシニカルな面白さが善と悪の二元構造によって薄められてしまっており、原作の持つ面白さを体現していたのがウンパルンパのみだったのが残念な点だ。
ただ、本作の悪役陣はどこか憎めない存在として描かれていた。例えば本作では、悪役たちも歌い踊る。
『夢のチョコレート工場』と『チャーリーとチョコレート工場』の違いは、ウンパルンパ以外の登場人物も歌って踊る点だ。
本作は登場人物たちも歌って踊る。その点でも『夢のチョコレート工場』に回帰していたように思う。
悪役たちにもスポットライトを当てていて、特に登場する度に太っていく悪辣警察署長はコミカルの極み。
また、ウィリー・ウォンカを始めとする6人を契約の罠で閉じ込め、洗濯部屋でこき使うミセス・スクラビットとプリーチャーも憎めない悪役として描かれている。
登場人物の肌の色も含め、本作の善と悪も二元的に描かれてはいるものの、総じてなるべく多様性を配慮した作りになっている。
ただし、原作の世界観に忠実なのが本作であるものの、原作に合った肝であるブラックでシニカルな面白さが欠けている以上、その点で私は辛い点をつける。
ついでに言うと、ウィリー・ウォンカが持つマジカルなチョコレート作りの秘密こそが本作でも大きな興味を抱く点だったにもかかわらず、その能力をどこで手に入れたのかが描かれておらず、これも物足りなさを感じた点だ。
ひょっとしたら、ウィリー・ウォンカがそうした能力を身に付けていくいきさつだけでも一本物の映画が作れるのかもしれない。が、できれば本作でもそのあたりがもっと描かれていたらよかったのに、と思った。
ただ、それだと本作について辛く言うだけで終わってしまう。ここで、本作の良さを取り上げたい。
本作はチョコレートと言う誰もが憧れる夢の食材をマジカルに描き、それをミュージカルが持つ音楽の楽しさに乗せたことが魅力になっている。ブラックかつシニカルなユーモアは本作では強調されていないと割り切ったほうがよい。
つまり、原作がどうとか『夢のチョコレート工場』と『チャーリーとチョコレート工場』との違いや受け継ぎ方をあげつらうことは本作を鑑賞する上ではむしろ邪魔だ。
本作は独立した作品として観ることで、楽しい余韻だけを感じた方がよいと思う。
なお、チョコレートがきっと食べたくなるはず。
‘2023/12/30 109シネマズグランベリーパーク