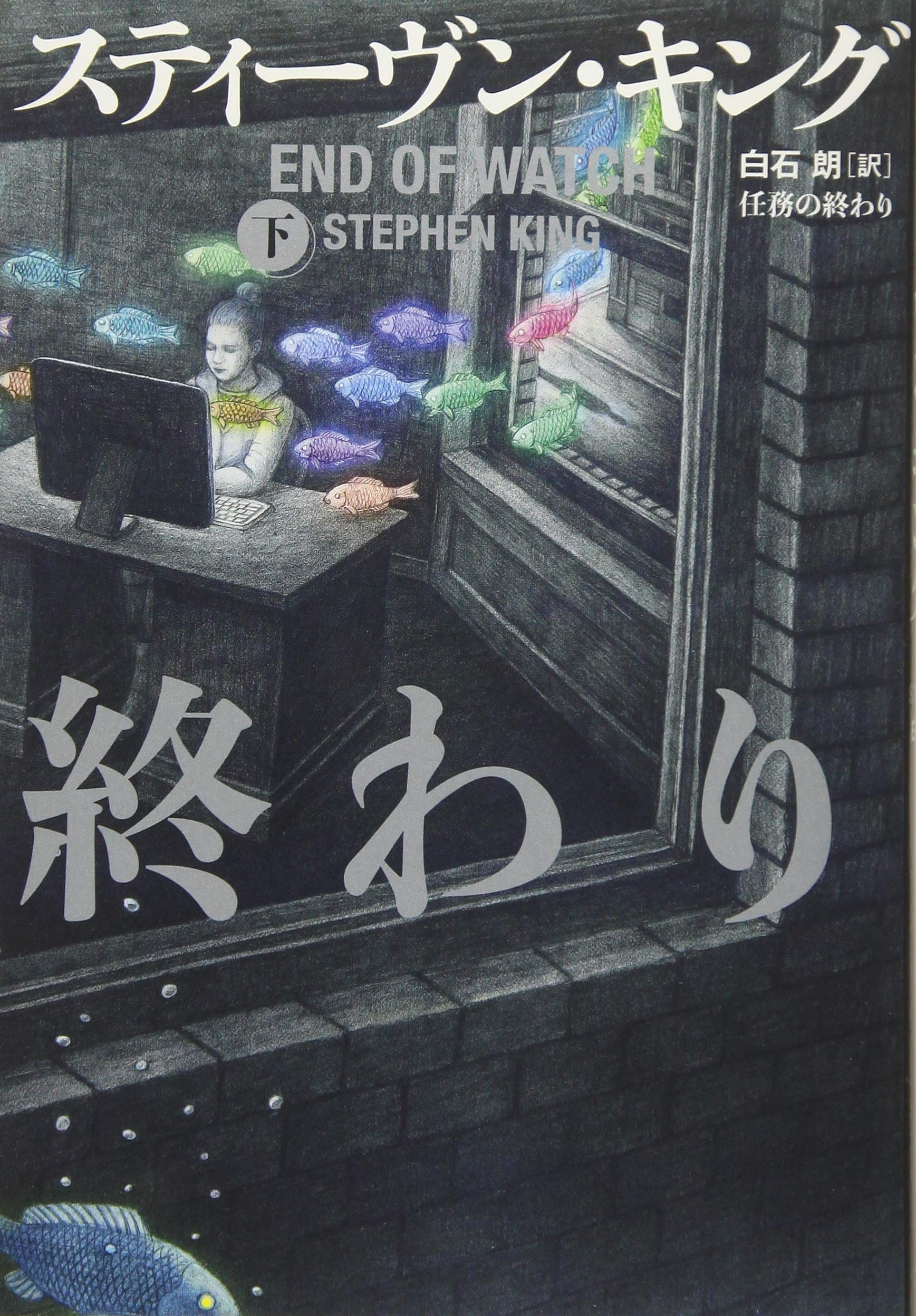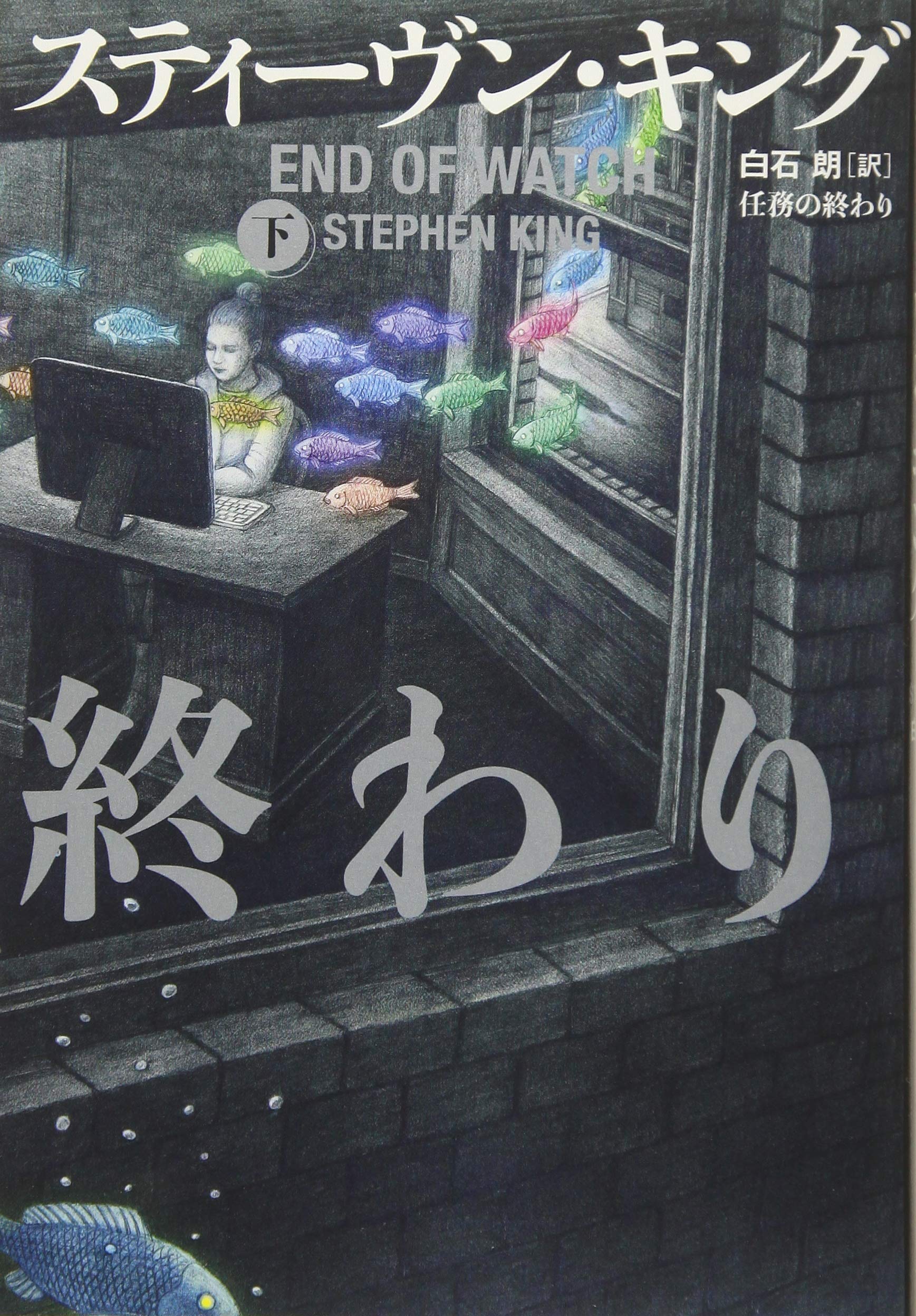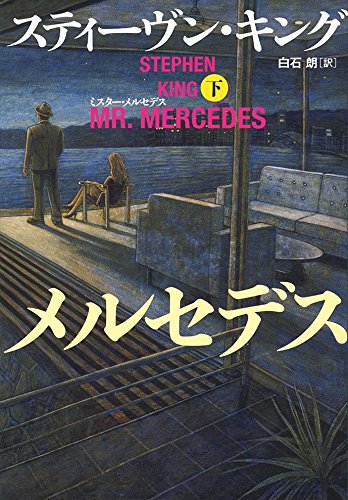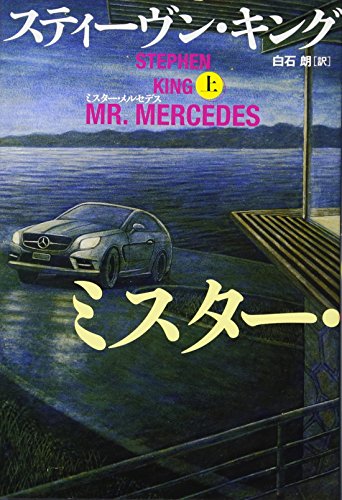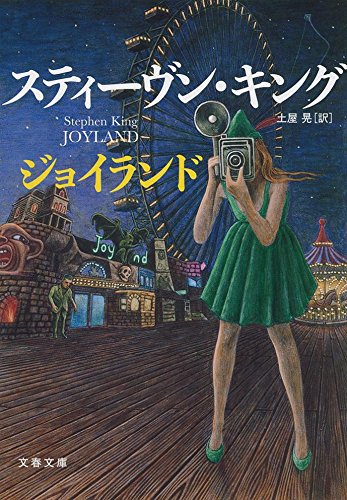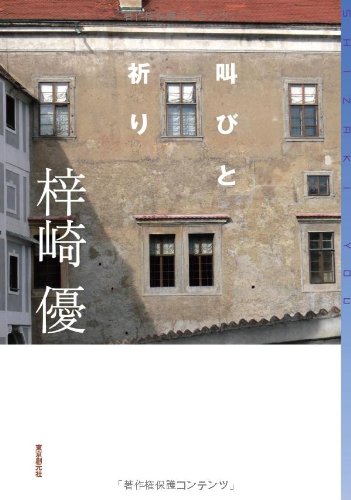
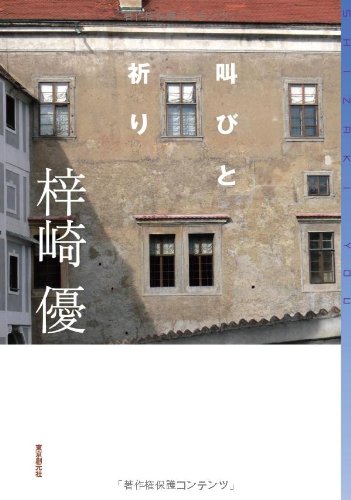
本書は毎年末に恒例のミステリーのランキングで上位に推された。
連作の短編集である本作は、著者の処女作。初めての小説で上々の評価を得た著者の実力は確かだと思う。
実際、本書はとても面白い。ミステリーの骨法をきちんと備えている。
語りの中にときおり詩的な描写が挟まれ、それでありながら、簡潔な文体で統一されている。さらに短編なので一つ一つの物語がすいすいと読める。ミステリーが苦手な方にも勧められる。
何よりも面白いのは、本書に登場するそれぞれの物語の舞台が国際色豊かなことだ。本書に収められた五編のうち、日本が舞台の物語は一つもない。
五編の物語はそれぞれ、サハラ砂漠、中部スペインのレエンクエントロの風車、ウクライナに隣接する南ロシアロシア南部の修道院、アマゾン奥地のジャングル、東南アジアのモルッカ諸島の島、といった特殊な環境を舞台としている。
日本人にはなじみのない環境と文化。その中で起こる謎。斉木が解決するのはそのような事件だ。
斉木は、世界の問題を取り上げる雑誌の記者だ。語学に堪能で、海外の暮らしには不自由を覚えることはない。さらに、物事に対する深い洞察力を持っている。
「砂漠を走る船の道」
本編こそが、著者の名を大きく高めた一編だ。
砂漠をゆくキャラバン。
キャラバンが向かうのは塩を算出する場所。ここで岩塩を切り出し街へと運ぶ。
太陽が目を灼き、砂が肌を痛めつける。砂がすぐに覆い隠してしまうため、過酷な道は道の体をなしていない。
その道を間違いなく行き来し、天気や環境を知悉するには長年の経験が欠かせない。
キャラバンの一行は荷駄を預けるラクダとリーダーと二人の助手、そしてリーダーに懐く若いメチャボ。
だが、帰途に砂嵐に遭遇し、リーダーは死ぬ。その帰り道には二人の助手のうち一人がナイフを刺されて死んでいた。
一体、何が動機なのか。その動機の謎と過酷な環境の組み合わせがとても絶妙。その関連が印象に残る。
結末ではもう一つの謎も明かされる。その意外性にも新たなミステリーの地平を見せられた気がする。
「白い巨人」
この一編は、風車をめぐる歴史の謎が絡む。
レコンキスタ。それはかつて、イベリア半島を支配したイスラム勢力を再びアフリカに追いやる運動だ。本編に登場する風車は、レコンキスタの戦いの中で、敵であるイスラム側の戦況を味方に伝えようとした斥候が追われ、逃げ込んだ場所だ。逃げ込んだ斥候は風車の中にうまく隠れ、レコンキスタの成就に決定的な役割を果たしたという。
本編に登場するサクラが、かつて想いを寄せた女性を見失ってしまったのも同じ風車。人を消す風車の謎を軸に本編は進む。
風車の謎以外にも、もう一つの謎が明かされる結末もお見事。
「凍れるルーシー」
生きているように、こんこんと永遠の眠りにつく遺体。それを不朽の体、つまり不朽体という。
西洋にはそうした不朽体がいくつか報告されているそうだ。
十字架の上で死んだメシアが復活する。言うまでもなくキリスト教の教義の中心にある奇跡だ。そうした現象を教義に据えるキリスト教が文化に深く影響を与えている以上、西洋のあちこちで不朽体のような現象への関心が高いことは理解できる。
本編の舞台である南ロシアの修道院にも、不朽のリザヴェータの聖骸がある。今までは世間に知られていなかったリザヴェータを聖人として認定してもらうよう、修道院長がロシア正教会に申請を出したことがきっかけで事件は動く。修道院には聖骸を熱狂的に崇める修道女がいて、聖人申請がうまく行かないのではと不安に苛まれる。
そんな所に修道院長が死体となって発見されたことで、事態は一気に混迷に向かう。
本編も短編ならではの簡潔でキレのある物語だ。効果的な謎の提示と収束が魅力的だ。
「叫び」
本編の舞台はアマゾンの奥地だ。隔絶された部族を取材したクルーが遭遇する殺人事件。
だが、斉木たちクルーが部族の集落を訪れた時点で、集落には正体が不明の伝染病が猖獗を極めていた。殺人が起こる前からすでに絶滅寸前の部族。
そのような絶望的な状況でありながら殺人が起こる。どうせ死んでしまうのに、なぜ殺人を犯す必要があるのか。その動機はどこにあるのか。
そこには部族が持つ独特な世界観が深くかかわっている。
本書を通じて思うのは、著者は動機を考えるのがとてもうまいことだ。
それは世界各国の社会や文化についての深い造詣があるからに違いない。
文化によって守るべき考えはそれぞれだ。ある文化では当たり前の慣習が、ある文化では忌むべき振る舞いとなる。よく聞く話だ。
それを短い物語の中で読者に簡潔に伝え、文化によってはそのような動機もありなのだ、ということを謎解きと並行して読者に納得させる。
その技は簡単ではない。
「祈り」
こちらは今までの四編とは少し趣が違っている。語り手によって語られるのはゴア・ドア──祈りの洞窟についてだ。
語り手は誰に対して物語を語っているのか。そこでは上に紹介した四編の物語が断片的に触れられる。
語りの中から徐々に露になってくるのは、斉木が不慮の事故で記憶を失ったこと。
世界を股にかけ、最も自由な生き方をしていた斉木。日本人の認識の枠を超え、自由な考え方をモノにしていたはずの斉木に何が起こったのか。
文化にはさまざまな形がありうるし、その中ではさまざまな出来事が起こりうる。
文化の違いに慣れ、事故に強かったはずの斉木にも防げなかった衝撃。それだけの衝撃を斉木はどこでどのように受けたのか。
果たして斉木は復活しうるのか、
本編はミステリーよりも、四編の短編を受けた一つの叙情的な物語の色が濃い。
文化はいろいろとあれど、それらを共有するのも伝え合うのも人、ということだろう。
‘2019/12/8-2019/12/11