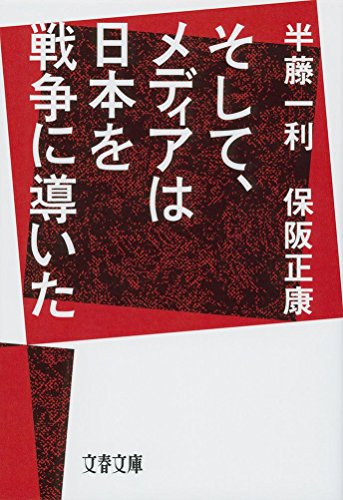川はいい。
川は上流、中流、下流のそれぞれで違った魅力を持つ。上流の滝の荒々しさは見ていて飽きない。急流から一転、せせらぎの可憐さは手に掬わずにはいられないほどだ。中流に架かる橋を行き交う電車やクルマは生活のたくましさな象徴だ。河川敷を走る人々、遊ぶ子供たちは、川に親しむ人々の姿そのものだ。下流に至った川は一転、広々と開ける。そこでは水はただ滔々と流れるのみ。その静けさは永きにわたる行路を終えたものだけが醸し出せるゆとりを感じさせる。
私が川を好きな理由。それは二十年以上、川のすぐ近くに暮らしていたからに違いない。その川とは武庫川。兵庫の西宮市と尼崎市を分かつ川だ。丹波篠山から多彩な姿を見せながら大阪湾へと流れ込む。
川は人々の暮らしに密着している。川の近くに住む人々は川に名前をつける。そしてその名を呼びならわし、先祖から子孫へと名は伝わってゆく。いつしか、川の名前がしっかり幼い子供の心に刻まれる。私が武庫川を今も好きなように。
「川の名前」という本書のタイトルは、私を引き寄せた。それはあまりにも魅力的に。実は本書をハヤカワ文庫で目にした時、私は著者の名前を知らなかった。だが、タイトルは裏切らない。手に取ることにためらいはなかった。
本書に登場する川とは桜川。少年たちの毎日に寄り添い流れている。少年たちは五年生。五年生といえばそれなりに分別も身につき、地元の川に対する愛着が一番増す時期だ。宿題にも仕事にも追いまくられず、ただ無心になって川で遊べる。部活に没頭しなくてよく、受験も考えなくていい。五年生の夏休みとは、楽し身を楽しさとして味わえる最後の日々かもしれない。その夏休みをどう過ごすか。それによって、その人の一生は決まる。そういっても言い過ぎではない気がする。
主人公菊野脩の父は著名な写真家。海外に長期撮影旅行に出かけるのが常だ。これまで脩の夏休みは、父に連れられ海外で冒険をするのが恒例だった。だが五年生となり、自立の心が芽生えた脩は、地元で友人たちと過ごす夏休みを選ぶ。
少年たちの夏休みは、脩が桜川の自然保護区に指定されている池でペンギンを見つけたことから始まる。池に住み着き野生化したペンギン。ペンギンを見つけたことで脩の夏休みの充実は約束される。動物園で見るそれとは違い、たくましく、そして愛おしい。少年たちに魅力的に映らぬはずはない。脩は仲間である亀丸拓哉、河邑浩童を誘い、夏休みの自由研究の題材をペンギン観察にする。
私も子供の頃、武庫川でやんちゃな遊びをしたものだ。ナマズを捕まえてその場で火を起こして食べたこともある。半分は生だったけれど。捕まえた鯉を家に持ち帰り、親に焼き魚にしてもらったのも懐かしい。土手を走る車にぶつかって二週間ほど入院したのは小1の夏休み。他にも私は武庫川でここでは書けないような経験をしている。ただ、私は武庫川ではペンギンは見たことがない。せいぜい鳩を捕まえて食ってる浮浪者や、泳ぐヌートリアを見た程度だ。それよりも川に現れた珍客と言えば、最近ではタマちゃんの記憶が新しい。タマちゃんとは、多摩川や鶴見川や帷子川を騒がせたあのアザラシだ。私は当時、帷子川の出没地点のすぐ近くで働いていたのでよく覚えている。タマちゃんによって、東京の都市部の川にアザラシが現れることが決して荒唐無稽なファンタジーでないことが明らかにされた。つまり、多摩川の支流、野川のさらに支流と設定される桜川にペンギンが住み着くのも荒唐無稽なファンタジーではないのだ。
そしてタマちゃん騒動でもう一つ思い出すことがある。それはマスコミが大挙し、捕獲して海に返そうという騒動が起きたことだ。連日のテレビ報道も記憶に鮮やかだ。本書も同じだ。本書のテーマの一つは、大人たちの思惑に対する子供たちの戦いだ。身勝手で打算と欲にまみれた大人に、小学校五年生の少年たちがどう対応し、その中でどう成長していくのか。それが本書のテーマであり見せ場だ。おそらく本書が生まれるきっかけはタマちゃん騒動だったのではないか。
本書に登場する人物は個性に溢れている。そして魅力的だ。中でも喇叭爺の存在。彼がひときわ目立つ。最初は奇妙な人物として登場する喇叭爺。人々に眉をひそめられる人物として登場する喇叭爺は、物語が進むにつれ少年たちにとっての老賢者であることが明らかになる。老賢者にとどまらず、本書の中で色とりどりの顔を見せる本書のキーマンでもある。
特に、人はそれぞれが属する川の名前を持っている、という教え。それは喇叭爺から少年たちに伝えられる奥義だ。就職先や出身校、役職といった肩書。それらはおいて後から身につけるものに過ぎない。成長してから身を飾る名札ではなく、人は生まれながらにして持つものがある。それこそが生まれ育った地の川の名前なのだ。人はみな、川を通じて海につながり、世界につながる。人は世界で何に属するのか。それは決して肩書ではない。川に属するのだ。それはとても面白い思想だ。そして川の近くに育った私になじみやすい教えでもある。
川に育ち、川に帰る。それは里帰りする鮭の一生にも似ている。幼き日を川で育まれ、青年期に海へ出る。壮年期までを大海原で過ごし、老境に生まれた川へと帰る。それは単なる土着の思想にとどまらず、惑星の生命のめぐりにもつながる大きさがある。喇叭爺の語る人生観はまさに壮大。まさに老賢者と呼ぶにふさわしい。だからこそ、少年たちは川に沿って流れていくのだ。
本書を読んで気づかされた事は多い。川が私たちの人生に密接につながっていること。さらに、子供を導く大人が必要な事。その二つは本書が伝える大切なメッセージだ。あと、五年生にとっての夏休みがどれだけ大切なのか、という重要性についても。本書のような物語を読むと、五年生の時の自分が夏休みに何をしていたか。さっぱり思い出せないことに気づく。少年の頃の時間は長く、大人になってからの時間は短い。そして、長かったはずの過去ほど、圧縮されて短くなり、これからの人生が長く感じられる。これは生きていくために覚えておかなければならない教訓だ。本書のように含蓄のつまった物語は、子どもにも読ませたいと思える一冊だ。
‘2017/01/20-2017/01/22