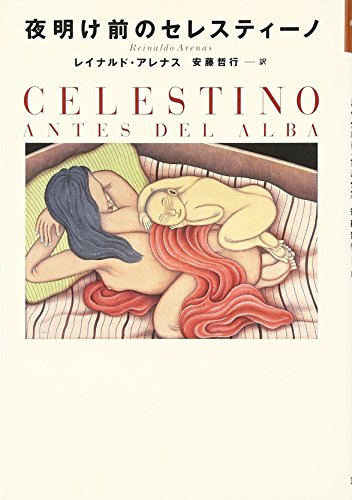本書は、芥川賞を受賞している。図書館に設けられた芥川賞受賞作のコーナーで本書を手に取った。
もちろん、読み始めた頃は著者についても本書の内容についても何も知らなかった。
本書はゲイの話だ。
ゲイとしての生き方と日々の暮らしを何の飾りも誇張もなく描いている。
日中は仕事に精を出し、夜はパートナーと一緒に過ごす。その相手が男から見て女性なのか男性なのか。
それがゲイなのかそうでないかの違いだと思う。
本書は主人公の丸尾くんと光のパートナー関係が軸になっている。
二人で手をつないで歩いていると、小学生からからかわれ、「ホモ」と呼ばれる。
二人の日常は、ごく当たり前の毎日だ。小説にメリハリを加えるような劇的なイベントが起こることもないし、ドラマチックな展開に驚かされることもない。
だから本来、本書は日々の生き方を丁寧に描いた作品に過ぎない。
ところが、描かれているのがゲイのカップルを生態というだけで、本書の内容が新鮮に受け取られる。小説として成り立つ。
それは、ゲイのカップルが普通と異なる関係として見られている証しだと思う。普通のカップルの日常を描くだけであれば、それはドラマにも小説にもなりにくい。
彼らは何も悪いことをしておらず、普通に愛し合って生きているだけなのに、小説として成り立ってしまう。
日常生活に、性的な嗜好など何の関わりもないはず。
そういう私も、性的には異性愛者だ。だから、同性愛の心がどのように作用するのかわからない。
同性愛に関して受け入れられない経験もないし、私が同性愛者に偏見を持つ理由はないと思っている。
だが、丸尾と光のカップルをからかう小学生がいるように、ノーマルではない関係をからかい、愛する者が普通ではないことを貶めようとする偏見は存在する。
光はそうしたからかいに敏感に反応する。だが、丸尾くんはそうしたからかいを右から左に流して受け流し、意に介さない。
もちろん異性愛の関係でもどのように告白するか、どう行動し、どうカミングアウトするかという問題はある。
だが、ゲイの世界にあっては、そのタイミングや告白の時期など、気を遣うことも多いだろう。
一方、芸能界では、ゲイであることをカミングアウトする芸能人も多い。少しずつ世の中は変わりつつある。LGBTの運動は七色の虹のマークとともにおなじみになってきた。
上にも書いた通り、私は異性愛者だ。たぶん、同姓愛の気持ちを理解できることはないだろう。
だが、たとえ私が同性愛者であったとしても、それはあくまでプライベートな世界。誰にも迷惑をかけていないはず。
だから、異性愛者が同性愛者を攻撃するその心根が理解しにくい。単にマイノリティーを、弱い者を攻撃したいだけではないかという思いがある。
だから本書に登場する丸尾と光のカップルを自然に受け入れる人々がとてもまっとうに見える。
本章に登場する二人の応援者は皆女性だ。
それは、丸尾くんの恋愛の対象が男性だからなのか安心できるのか。
例えば、私は結婚して長く立っており、常に指輪をつけっぱなしだ。外したことすらない。だからこそ、女性とも警戒されず飲みにも行けるし、遊びにも行ける。
逆に私が指輪をしていなかったとすれば、女性は私から距離を置くはずだ。それは、性愛の対象となる警戒心が募るからだろう。
それと同様に、丸尾くんから性愛の対象とみなされないことがわかっているから女性は心を開く。
男性であるからこそ、同性愛者は人からの視線にたいして敏感になる。
そうした、生来の警戒心は、異性愛でも同性愛でも変わらない。
そう考えると、指輪のようにさりげなく性的嗜好をアピールするアクセサリーは必要なのかもしれない。
ひょっとすれば、特定の指に指輪をはめていればこの人は同性愛者だとわかるようにする風習。そんな風習がやがて世界的にメジャーになることだって考えられる。
その時われわれは、その個人が異性愛者であろうと同性愛者であろうと一人の人間として関われるような考え方を身につけておかねばならない。
少なくとも本書のような同性愛を描いた小説が、それだけで新規の題材であると評価されるようなことは本来ならばおかしい。
そう考えると、本書はどういう点が評価されたのだろうか。
おそらく、同性愛者の日々を、女性の視点から描いたことにあるのではないだろうか。
男性同士の生態と睦み合う様子を女性の立場から描くことはとても難しいことだと思う。
本書に無理やり解釈したような不自然さはない。それどころか、男性同士の恋愛の姿がとても自然に描かれている。
よく、異性の間に友情は生じないという通説がある。本書は丸尾くんと光のカップルと女性たちの交流を通じ、異性との友情がありえることを訴えている。
結局、性的な嗜好の違いなど、結果として子供ができるかどうかの違いでしかない。
異性のカップルにも子供に恵まれないこともある。
そう考えると、なぜ同性愛者が拒否されるのかは、個人的な問題に過ぎないと思う。
むしろ、それも人間の多様性の一つとして認めてあげるべきだろう。
本書の丸尾くんと光のカップルは気負わずに日々を生きている。
だが、そうした二人を小学生たちはからかう。それは、幼稚な行いに過ぎない。だが、大人からの偏見の影響が多く見られる。
タイトルの『夏の約束』とは丸尾くんと光の二人と、彼らをめぐる女性達のキャンプが実現できるかどうかの約束。
おそらく、遠からずのうちに彼らの約束は果たされるに違いない。
その時、わが国からはようやく一つの縛りが外されたことになる。
‘2019/12/11-2019/12/11