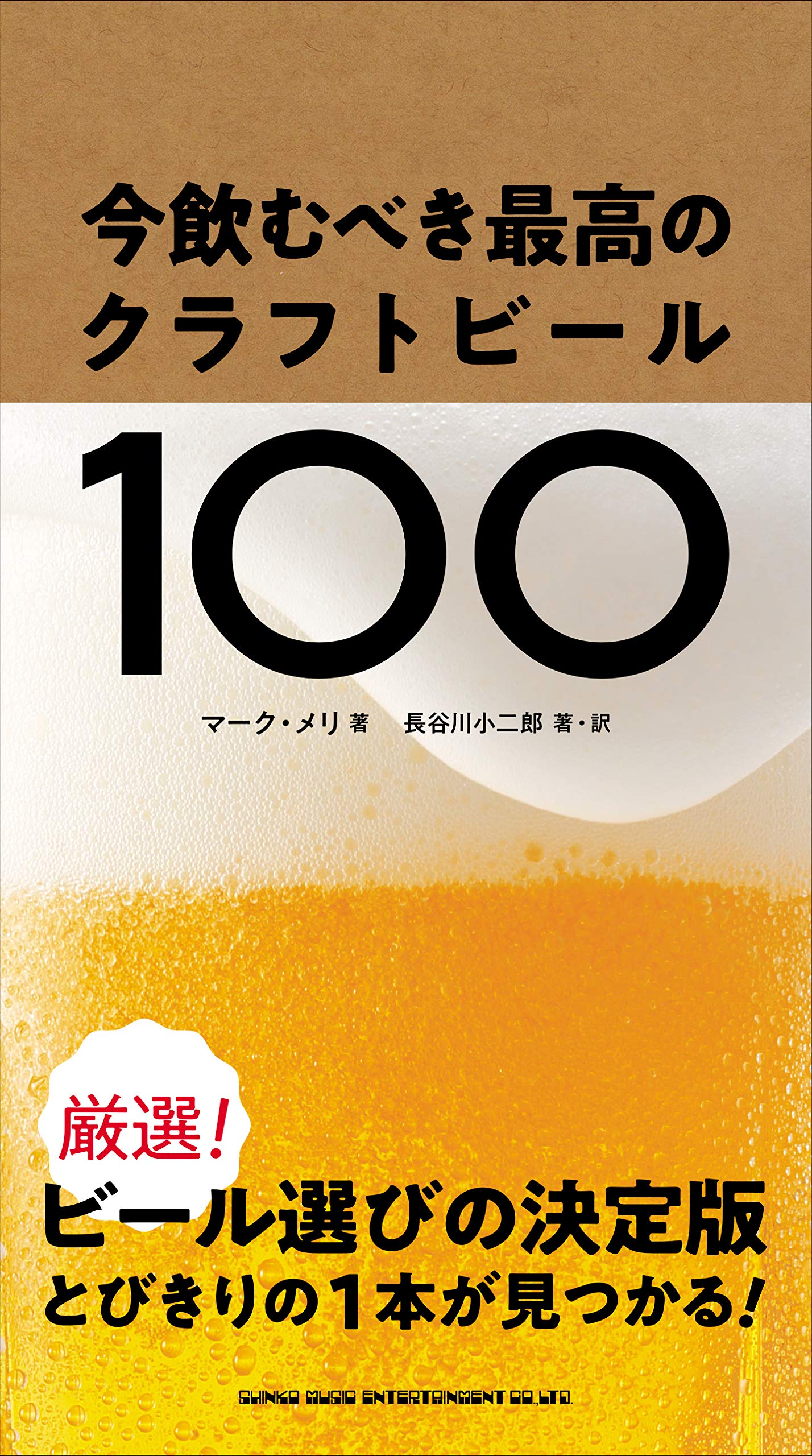
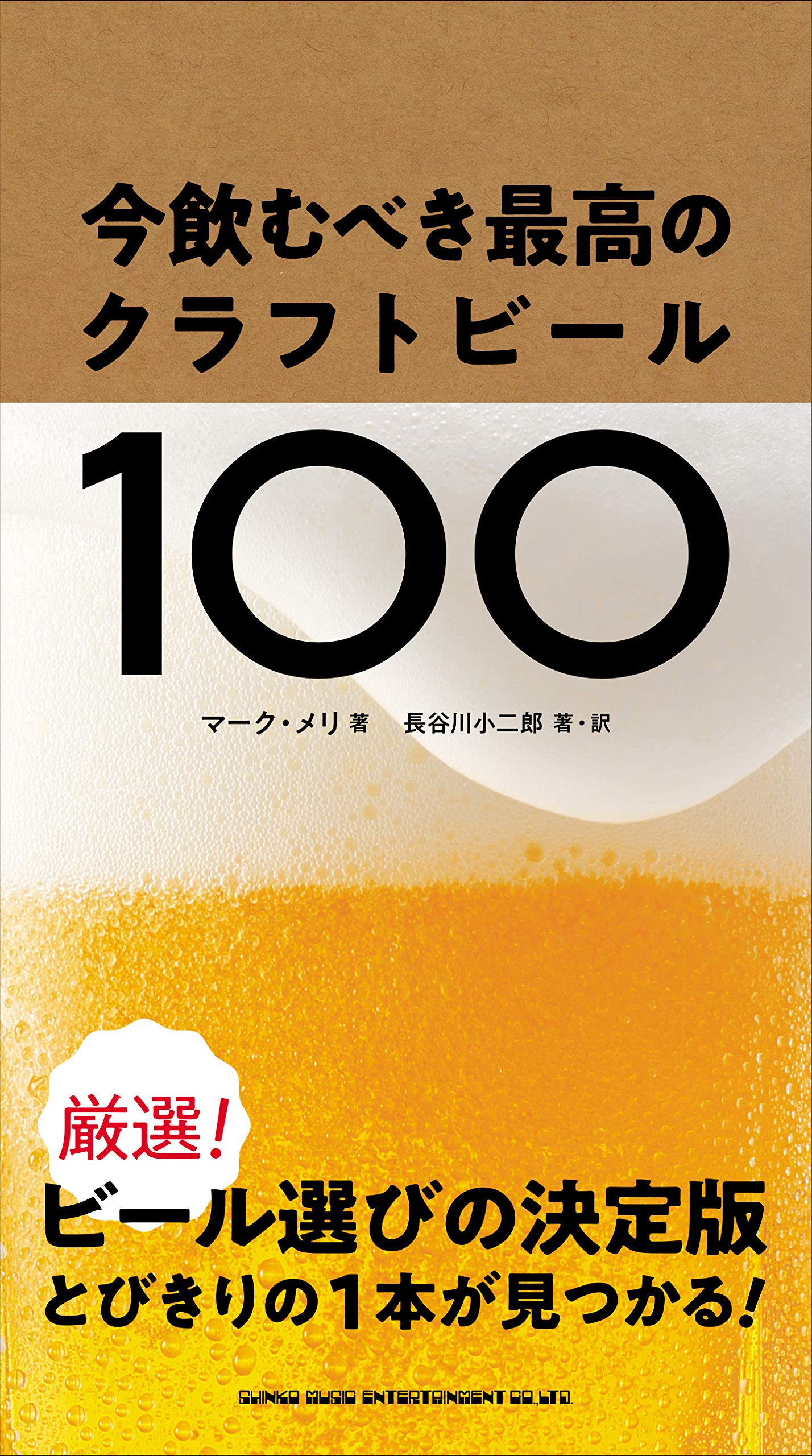
本書の編者であり、山仲間、飲み仲間である小宮さんから本書を献本いただいた。
今、クラフトビールが盛り上がっている。
マイクロブルワリーが続々と生まれ、世界中で多種多様なビールが世の飲兵衛を迷わせている。
この盛り上がりは本当に嬉しい。
一度はブームが去って寒々しい状態だった地ビールの状況を知っているだけに。
かつて、地ビールが初めて解禁された時期、私はまだ20代前半で自由を謳歌する身だった。そのため、あちこちに出かけてはクラフトビールを飲んでいた。
私が上京して忙しくなったのと期を同じくして地ビールのブームは去り、いくつものお店が閉店した。
それがどうだろう。今のクラフトビールの盛り上がりは。かつての地ビールブームのそれを凌駕している。それどころか、ビールの種類は百花斉放。ブルワリーも各地に開店し、外観も内装も工夫が凝らされている。その地域の風土や産物に合わせて。
クラフトビールはすっかり世の中に根付いたように思う。
一過性の盛り上がりに終わっていないことが本当に嬉しい。
今のクラフトビールが盛り上がり始めた頃、私は高校時代からの親友とJR難波近くで催されていたクラフトビールフェスに行き、そこで彼からIPAのおいしさを教わった。IPAのおいしさに衝撃を受けたその日こそ、私がクラフトビールを本当に好きになった日だといえる。
単なる酒飲みとしてだけでなく、ビールの味や文化も含めて愛好するようになり、各地の旅行での楽しみにビール・ツーリズムが加わったのもそのころからだったように思う。
とはいえ、クラフトビールの盛り上がりはまだまだこれからだ。その証しに、コンビニに行っても必ずクラフトビールが買えるわけではない。コンビニのビールの品ぞろえは大手四社の製品が棚のほとんどを占めている。
もちろん、お店によってはクラフトビールが売られている。が、その銘柄はクラフトビール界である程度の知名度を手にしたものだけだ。
世の中には美味しいビールが皆さんに飲まれる時を待っているにもかかわらず、それらをみなさんが知る機会はそう多くない。
そのためには、全国のあちこちで作られているクラフトビールに触れる機会が必要だ。
私が訪れたようなフェスタの形で行われているビール祭りはその良い機会だろう。
そういうフェスを訪れるとさまざまなビールに出会える。そして飲み比べられる。
新型コロナウイルスは四年近く、私たちからそうした機会を奪った。
だが、そういうフェスに訪れなくても、ビールの奥深さを知る手段は用意されている。
例えば、本書のようなガイド本だ。
本書を手にほんの少しの想像を働かせれば、家にいながらにしてビールの多彩な世界に触れられる。
興味を持てば、そのビールをネット通販で取り寄せることさえできる。
旅をせず、諸国で醸されたビールが飲める。今はそういううれしい時代になっている。
本書は、クラフトビール界隈の話題をかっさらった新進気鋭のブルワリーや、クラフトビールの雄とも言うべきブルワリーも取り上げられている。読んでいるだけで楽しくなることは間違いない。
本書のクラフトビールの説明は、写真付きだ。かつ、味の説明やブルワリーの説明も載っている。一銘柄あたり、約三百文字。
簡潔にして必要な内容が押さえられている。
それだけではなく、受賞歴や、アルコール度数、原材料や製造地、製造者の情報も載っている。
しようと思えば、もう少し詳細に説明も書けるだろう。製法のこだわりも載せられるだろう。
だが、本書はそれをしない。
なぜなら本書はハンディで持ち歩けるガイド本だからだ。
本書を片手に旅先でブルワリーをふらりと訪れる。出張するビジネスマンや旅人にとっては、くだくだしい説明はかえってかさばってしまう。本書は手軽に持っていけることを優先し、簡潔な説明にとどめている。
今、サケ・ツーリズムやアルコール・ツーリズムが盛んだ。私も20代頃から蒸留社巡りを楽しみ、ブルワリーも各地の名店を巡ってきた。
地酒や地ウイスキーのように、クラフトビールはその地を訪れる旅人を引きつける。地域おこしの主役のコンテンツになりうる。
実際、私は蒸留所だけが目当ての旅をしたことが何度もある。
私がレアな存在なのではない。同じようにお酒を目的とした旅を楽しむ人は多いはずだ。
なんと言っても、今は多様性の時代なのだから。
ツーリストにとって、ハンディサイズで持ちやすい本書のようなガイドは、ビールが好きな旅人やビジネスマンの助けになると思う。
もちろん、ネットにも似たようなガイドサイトはあるだろう。
だが、残念ながら銘柄単位ではなかったり、場所別や会社別、ブルワリー別になっていなかったり、使い勝手はまちまちだ。
その点、本書は編集方針が明確であり、地域別や会社別ではない。
淡色・中濃色エール
IPA
濃色エール
小麦エール
ラガー
フルーツ、スパイスなど
の六つのカテゴリーに分けてくれていて、好みに応じて好きな銘柄に思いをはせることが可能なのだ。
本書は他にもコラムやクラフトビールの歴史にも触れている。また、全国のビールイベントの紹介も。
その中には私が友人にIPAを教えてもらった大阪のCraft Beer Liveも。
また本書を携えて各地を巡りたいものだ。
2020/12/1-2020/12/1



