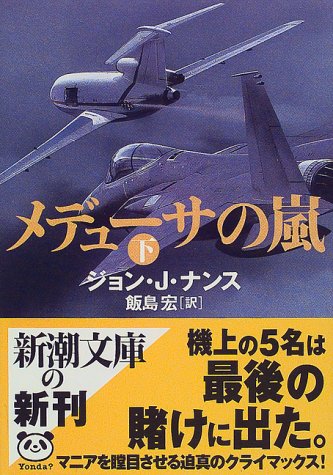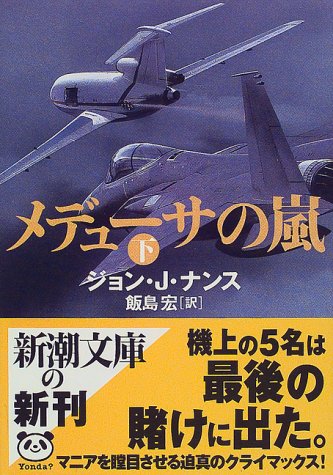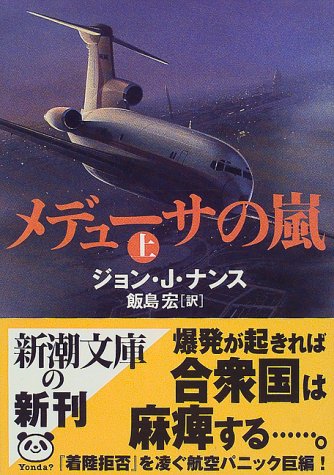本作は見に行こうと決めていたので、一カ月ほど前にAmazon Primeで前作を見直した。中学生の頃はレンタルやテレビ放映で何度も見た前作だが、前に見てからおそらく三十年はたっているはずだ。
前作のサントラはカセットテープでも持っているし(私が初めて買った音楽メディアがバック・トゥ・ザ・フューチャーのサントラのカセットで、その次に購入したのがトップガンのサントラ)、後にCDでも購入した。
TOPGUN ANTHEMは今でも頻繁に聴くし、私にとって前作は重要な作品だ。
だからこそ、本作は見に行こうと決めていたものの、少しだけ不安だった。期待はずれだったらどうしよう。
結論から言うとそれは杞憂だった。
36年のブランクを感じさせず、それでいて、前作を十分に尊重している内容が素晴らしかった。思わず最後は泣いてしまった。
まだ見ていない人が本稿を読むかもしれないので、あまり内容については触れないようにしたい。特に前作と本作で引き継がれた部分や、前作に比べて変わった部分については本稿では注意深く取り扱うつもりだ。
とはいえ、作中に流れる音楽については書いても良い気がする。
例えば冒頭。TOPGUN ANTHEMのイントロが流れ、そこからDANGER ZONEへと転調する部分。このシーンなど、完全に前作を見た人へのサービスだろう。この部分だけで前作の思い出が蘇ることは間違いない。
あとはエンドクレジットだ。本作の最後にはTOPGUN ANTHEMが流れる。だが、スティーブ・スティーブンスの奏でるギターのアレンジに痺れた私としては、本作で流れたTOPGUN ANTHEMのアレンジには新鮮さを感じなかった。残念ながら。
The WhoやDavid Bowieなどの懐かしい曲や前作でも印象に残るシーンで使われていたGreat Balls of Fireの使い方も良かった。流れる音楽に前作の雰囲気が踏襲されていたのは嬉しい。
ただし、前作はバラエティも豊かな80’sの黄金期にふさわしいミュージシャンがそろっていた。だが、本作のサウンドトラックに収められている曲にはまだピンときていない。別にレディ・ガガのアンチではないが、前作に続いて本作のサウンドトラックを買おうと言う気にはまだなっていない。
本作は、何が良かったかというと、加齢をきちんと踏まえてくれていたことだ。
ミッション・インポッシブルのようなアクション満載の映画も楽しいのだが、さすがにトム・クルーズの年齢を考えると無理がある。
本作で描かれたマーヴェリックが縦横無尽に機を操る姿にも年齢的にも無理はあるはず。だが、脚本の上では36年の月日を踏まえた脚本になっていて、前作を飾った面々が年月を重ねる描写が不自然さを感じさせなかった理由だったと思う。
また、ダイバーシティの風潮を踏まえ、トップガンの面々も一新した。人種もさまざまで、女性のパイロットも登場する。そこは前作との違いとしてあげてもよいだろう。
本作に登場するトップガン達の溌剌とした若さに比べると、トム・クルーズの加齢は否めない。だが、それが良かった。加齢しない人間などいるわけがない。歳を取っているのだ。トム・クルーズと言えども。
そこをきちんと描いてくれたため、トム・クルーズがマッハ10の壁を越えても、トップガンたちを訓練で次々とロックオンしても、本作のマーヴェリックから作り物めいた感じは受けなかった。
もう一つ、加齢を描いていて良いと思ったのはラブシーンだ。前作ではベルリンの歌う愛のテーマに合わせ、濃密な情欲が描かれていた。が、本作ではそこはあっさりと描かれていた。この点にも好感を持った。36年たっても相変わらず異性にギラギラするマーヴェリックなど、どう考えても不自然なので。
また、これは加齢には関係ないが、パイロットが人工知能に置き換えられる設定も、時流を映していて良かったと思う。
おそらく、本作にテーマがあるとすれば、生身の人間がハイテクの権化である戦闘機を乗りこなすことの激しさや苦しさ、厳しさを描くことにあるはずだ。なぜAIでなく生身の人間が乗ることに浪漫を感じるのか。それは、人間が感情にも肉体上にも限界があるからだろう。
その上でパイロットたちは限界に挑む。加齢や肉体の限界からは人間は逃れられないが、それを乗り換えて限界に挑まなければならない。そして、次の世代にバトンタッチしていかなければならない。
仲間同士の友情や協力によって不可能を可能にする姿が、本作の支持につながっているはず。
もう一つ、本作から感動を受けるのほ、主演のトム・クルーズ自身の姿勢だ。彼は50歳も半ばを過ぎたのに本作に挑戦している。
本作のパンフレットが売り切れだったので、私も製作情報はあまり知らない。だが、聞くところによると本作には合成の画像は使われていないそうだ。
規定により、俳優は実機を操縦できない。そのため、操縦自体は空軍の本物のパイロットが行っているそうだ。だが、俳優は実機に乗り込み、実際に乗った状態で演技しているそうだ。もちろんトム・クルーズも。
実際に高いGを感じながらの演技は大変だと思う。だが、それがかえって本作に真に迫った描写を与えているのではないだろうか。
IMAXの巨大な画面を前にみる本作は、実に爽快。見て良かったと思う。
本作は新型コロナウイルスによって再三公開延期を余儀なくされたと言う。だが、トム・クルーズは頑としてスクリーン公開を譲らなかったそうだ。それだけ本作に力を注ぎ込み、自信もあったのだろう。
本作のマーヴェリックの姿にうそっぽさがないとすれば、トム・クルーズの演技に年齢の壁を越え、さらなる高みへと努力する姿が感じられるからだろう。
本作は次女と見に行った。当日の朝の五時まで20時間連続で仕事をしていた娘は、社会人になって早々、過酷な現場で頑張っている。
トム・クルーズのファンである次女は、トム・クルーズの超人的な努力を見て、元気をもらったと言っていた。私もその意見に同じだ。
年齢だからと諦めるのではなく、努力してみなければ。49歳の誕生日を迎えた日に見たからこそ、なおさらそれを感じた。
‘2022/6/6 グランドシネマサンシャイン池袋