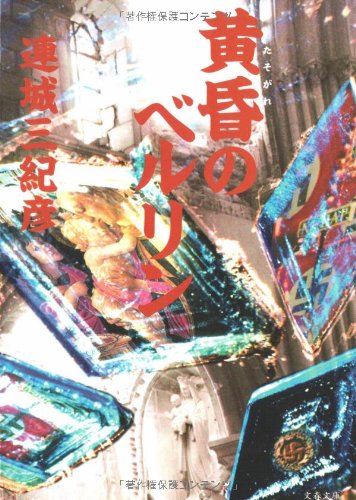本作は、私にとって初めて独りだけで観た舞台だ。独りだけで観劇することになった事情はここでは書かない。ただ、私の妻子は事前に本作をみていた。そして妻子の評価によると本作は芳しくないようだ。むしろ下向きの評価だったと言ってよいくらいの。そんな訳で、私の期待度は薄めだった。正直、事前に妻子が持っていたパンフレットにも目を通さず、あらすじさえ知らずに客席に座ったくらいだ。
そんな消極的な観劇だったにも関わらず、本作は私に強い印象を残した。私の目には本作が、宝塚歌劇団自らが舞台芸術とは何かを振り返り、今後の舞台芸術のあり方を確かめなおそうとする意欲作に映った。
なぜそう思ったか。それは、本作が映画を取り上げているためだ。映画芸術。それは宝塚歌劇そのものである舞台芸術とは近く、それでいて遠い。本作は舞台の側から映画を描いていることが特徴として挙げられる。なにせ冒頭から舞台上に映画館がしつらえられるシーンで始まるのだから。別のシーンでは撮影現場まで登場する。今まで私は舞台の裏側を描く映画を何作も知っている。が、舞台上でここまで映画の内幕を描いているのは本作が初めてだ。
舞台の側からこれほどまでに映画を取り上げる理由。それは、本作の背景を知ることで理解できる。本作の舞台は第二次大戦前のベルリンだ。第一次世界大戦でドイツが課せられた膨大な賠償金。それはドイツ国民を苦しめナチスが台頭する余地を生む。後の1933年に選挙で第一党を獲得するナチスは、アーリア人を至上の人種としユダヤ人やジプシー、ロマを迫害する思想を持っていた。その過程でナチスによるユダヤ人の芸術家や学者を迫害し、大量の亡命者を生んだことも周知の通り。そんな暗い世相にあって、映画はナチスによってさらにゆがめられようとしていた。映画をプロパガンダやイデオロギーや政治の渦に巻き込んではならない。そんな思いをもって娯楽としての映画を追求しようとした男。それが本作の主人公だ。脚本は原田諒氏が担当した宝塚によるオリジナル脚本である。
冒頭、舞台前面に張られたスクリーンにメトロポリスのタイトルがいっぱいに写し出される。私はメトロポリスはまだ見ていない。だが、メトロポリスをモチーフにしたQUEENの「RADIO GA GA」のプロモーションビデオは何度も見ている。なので、メトロポリスの映像がどのような感じかはわかるし、それが当時の人々にとってどう受けいれられたかについても想像がつく。
あらすじを以下に記す。METROPOLISのタイトルが記されたスクリーンの幕が上がると、プレミアに招待された人々が階段状の席に座っている。期待に反して近未来の描写や希望の見えない内容を観客は受け入れられない。人々は前衛過ぎるメトロポリスをけなし、途中退席して行く。メトロポリスを監督したのはフリッツ・ラング監督。この不評はドイツ最大の映画会社UFAの経営を揺るがしかねない問題となる。
そこで、次期作品の監督に名乗りを上げるのが、本作の主人公テオ・ヴェーグマンだ。彼はハリウッド映画に遅れまじと、トーキー映画を作りたいとUFAプロデューサーに訴え、監督の座を勝ち得る。
テオは友人の絵本作家エーリッヒに脚本を依頼する。さらに、当時ショービジネス界の花形であるジョセフィン・ベーカーに出演を依頼するため、楽屋口へと向かう。ベーカーは自らが黒人であることを理由に出演を辞退するが、そのかわりテオはそこで二人の女優と出会う。レニ・リーフェンシュタインとジル・クラインに。テオは、果たして映画を完成させられるのか。
本作は幕開けからテンポよく展開する。そして無理なく出演者を登場させながら、時代背景を描くことも怠らない。ここで見逃してはならないのが、人種差別の問題にきちんと向きあっていることだ。ジョセフィン・ベーカーはアメリカ南部出身の黒人。当時フランスを中心に大人気を博したことで知られる。本作に彼女を登場させ、肌の色を理由に自ら出演を断らせることで、当時、人種差別がまかり通っていた現実を観客に知らしめているのだ。先にも書いたとおり、ナチスの台頭に従って人種差別政策が敷かれる面積は広がって行く。それは、人種差別と芸術迫害への抵抗という本作のテーマを浮き彫りにさせてゆく。
本作が舞台の側から映画を扱ったことは先に書いた。特筆すべきなのは、本作が映画を意識した演出手法を採っていることだ。それはスクリーンの使い方にある。テオが撮った映画でジルが花売り娘として出演するシーンを、スクリーンに一杯に映し出す演出。これはテオの映画の出来栄えと、ジル・クラインの美しさを際立たせる効果がある。だが、この演出は一つ間違えれば、舞台の存在意義を危うくしかねない演出だ。舞台人とは、舞台の上で観客に肉眼で存在を魅せることが使命だ。だが、本作はあえて大写しのスクリーンで二人の姿を見てもらう。この演出は大胆不敵だといえる。そして私はこの演出をとても野心的で意欲的だと評価したい。しいて言うならば私の感覚では、モノクロの映像があまりにも鮮明過ぎたことだ。当時の人々が映画館で楽しんだ映像もフィルムのゴミや傷によって多少荒れていたと思うのだが。わざと傷をつけるのは「すみれコード」的によろしくないのだろうか。
美しい花を売る演技によって、端役に過ぎなかったジル・クラインはヒロインのはずのレニ・リーフェンシュタインを差し置いて一躍スターダムな評価を受ける。さらには、そのシーンに心奪われたゲッベルスに執心されるきっかけにもなる。
プライドを傷付けられたレニは、ジル・クラインがユダヤ人の母を持つこと、つまりユダヤの血が流れていることをゲッベルスに密告する。そしてナチスという権力にすり寄っていく。そんなレニのふるまいをゲッベルスは一蹴する。彼女がユダヤ人であるかどうかを決めるのはナチスであると豪語して。ジル・クラインに執心するあまりに。史実ではゲッベルスはドイツ国外の映画を好んでいたと伝えられている。本作でもハリウッドの名画をコレクションする姿など、新たなゲッベルス像を描いていて印象に残る。
あと、本作で惜しいと感じたことがある。それはレニの描かれ方だ。史実ではレニ・リーフェンシュタインは、ナチスのプロパガンダ映画の監督として脚光を浴びる。ベルリンオリンピックの記録映画「オリンピア」の監督としても名をはせた彼女。戦後は逆にナチス協力者としての汚名に永く苦しんだことも知られている。ところが、本作ではレニがナチスに近いた後の彼女には一切触れていない。例えば、レニが女優から監督業にを目指し、ナチスにすり寄っていく姿。それを描きつつ、そのきっかけがジルに女優として負けたことにある本作の解釈を延ばしていくとかはどうだろうか。そうすれば面白くなったと思うのだが。もちろん、ジル・クラインは架空の人物だろう。でも、レニの登場シーンを増やし、ジルとレニの関係を深く追っていけば、レニの役柄と本作に、さらに味が出たと思うのだが。彼女の出番を密告者で終わらせてしまったのはもったいない気がする。
もったいないのは、そもそもの本作の尺の短さにも言える。本作がレビュー「Bouquet de TAKARAZUKA」と並演だったことも理由なのだろうけど、少し短い。もう少し長く観ていたかったと思わせる。本作の幕切れは、パリへ向けて亡命するテオとジルの姿だ。客車のセットを舞台奥に動かし、降りてきたスクリーン上に寄り添う二人を大写しにすることで幕を閉じる。この流れが、唐突というか少々尻切れトンボのような印象を与えたのではないか。私も少しそう思ったし、多分、冒頭にも書いた妻子が低評価を与えたこともそう思ったからではないか。二人のこれからを観客に想像させるだけで幕を下ろしてしまっているのだ。ところが本作はそれで終わらせるのは惜しい題材だ。上に書いた通りレニとジルのその後を描き、テオに苦難の人を演じさせるストーリーであれば、二幕物として耐えうる内容になったかもしれない。
惜しいと思った点は、他にもある。本作にはドイツ語のセリフがしきりに登場する。「ウィルコメン、ベルリン」「イッヒ! リーベ ディッヒ」「プロスト!」とか。それらのセリフがどことなく観客に届いていない気がしたのだ。もちろん宝塚の客層がどれぐらいドイツ語を理解するのかは知らない。そして、これらのセリフは本筋には関係ない合いの手だといえるかもしれない。そもそも他のドイツを舞台にした日本の舞台でドイツ語は登場するのだろうか。エリザベートは同じドイツ語圏のウィーンが舞台だが、あまりドイツ語のセリフは登場しなかった気がするのだが。
なぜここまで私が本作を推すのか。それは権力に抑圧された映画人の矜持を描いているからだ。 ナチスという権力に抗する映画人。この視点はすなわち、大政翼賛の圧力に苦しんだ宝塚歌劇団自身の歴史を思い起こさせる。戦時中に演じられた軍事色の強い舞台の数々。それらは、宝塚自身の歴史にも苦みをもって刻印されているはず。であれば、そろそろ宝塚歌劇団自身が戦時中の自らの苦難を舞台化してもよいはずだ。なんといっても100年以上の歴史を経た日本屈指の歴史を持つ劇団なのだから。 本作で脚本を担当した原田氏は、いずれその頃の宝塚歌劇の苦難を舞台化することを考えているのではないか。少なくとも本作のシナリオを描くにあたって、戦時中の宝塚を考えていたと思う。私も将来、戦時中の宝塚が舞台化されることを楽しみにしたいと思う。
それにしても舞台全体のシナリオについて多くを語ってしまったが、主演の紅ゆづるさんはよかったと思う。彼女のコミカルな路線は宝塚の歴史に新たな色を加えるのではないか、と以前にみたスカーレット・ピンパーネルのレビューで書いた。ところが、本作はそういったコミカルさをなるべく抑え、シリアスな演技に徹していたように思う。歌も踊りも。本作には俳優さん全体にセリフの噛みもなかったし。あと、サイレントのベテラン俳優で、当初テオには冷たいが、のちに助言を与えるヴィクトール・ライマンの名脇役ぶりにも強い印象を受けた。
先に舞台上に演出された映画的なセットや演出について書いた。ところが、本作には舞台としての演出にも光るシーンがあったのだ。そこは触れておかないと。テオがジルにこんな映画を撮り続けたいと胸の内を述べるシーン。テオの回想を視覚化するように映写機を手入れする若き日のテオが薄暗い舞台奥に登場する。銀橋で語る二人をピンスポットが照らし、舞台にあるのは背後の映写機と二人だけ。このシーンはとてもよかった。私が座った席の位置が良かったのだろうけど、私から見る二人の背後に映写機が重なり一直線に並んだのだ。私が今まで見た舞台の数多いシーンでも印象的な瞬間として挙げてもよいと思う。
あと、宝塚といえば、男役と娘役による疑似キスシーンが定番だ。ところが本作にそういうシーンはほとんど出てこない。上に書いたシーンでもテオはジルに愛を語らない。それどころか本作を通して二人が恋仲であることを思わせるシーンもほとんど出てこない。唯一出てくるとすれば、パリ行きの客車に乗り込もうとするジルの肩をテオの手が包むシーンくらい。でも、それがいいのだ。
宝塚観劇の演目の一つに本作のような恋の気配の薄い硬派な作品があったっていい。ホレタハレタだけが演劇ではない。そんな作品だけでは宝塚歌劇にもいつかはマンネリがくる。また、本作には宝塚の特長であるスターシステムの色も薄い。トップのコンビだけをフィーチャーするのではなく、登場人物それぞれにスポットを当てている。私のように特定の俳優に興味のない観客にとってみると、このような宝塚の演目は逆に新鮮でよいと思う。そういう意味でも本作はこれからの宝塚歌劇の行く先を占う一作ではないだろうか。私は本作を二幕もので観てみたい、と思う。
ちなみに、この後のレビュー「Bouquet de TAKARAZUKA」は、あまり新鮮味が感じられず、眠気が。いや、このレビューというよりは、もともと私がレビューにあまり興味のないこともあるのだが。でも、それではいかんと、途中からはレビューの面白さとはなんなのかを懸命に考えながらみていた。それでもまだ、私にはレビューの魅力がわからないのだが。でも「ベルリン、わが愛」はよかったと思う。本当に。
‘2017/12/20 東京宝塚劇場 開演 13:30~
https://kageki.hankyu.co.jp/revue/2017/berlinwagaai/index.html