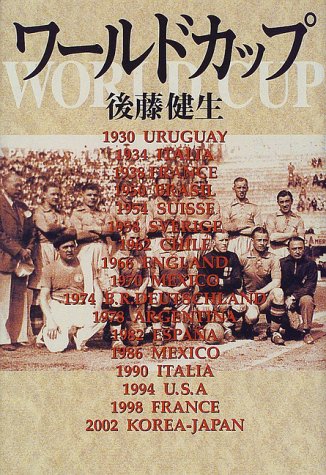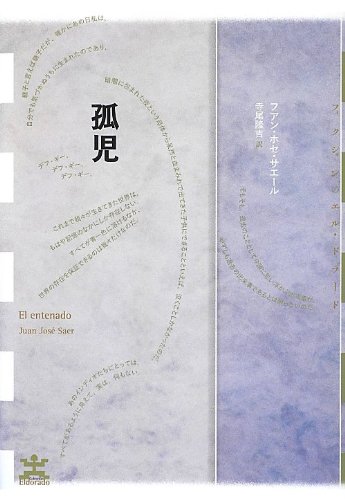本書は年始に書店で購入した。
選書で450ページ弱の厚みは珍しい。見た目からボリュームがある。
分厚い見た目に加え、本書のタイトルも世界史を掲げている。さぞかし、ビジネスの側面から世界史を網羅し、解き明かしてくれているはず。
そう思って読んだが、タイトルから想像した中身は少しだけ違った。
なぜなら、本書が扱う歴史の前半は、大半がローマ帝国史で占められているからだ。
後半では、フロンティアがビジネスと国の発展を加速させた例として、ヴェネツィア、ポルトガル、スペイン、そして大英帝国の例が載っている。
そして、最後の四分の一で現代のビジネスの趨勢が紹介されている。
つまり、本書が取り上げているのは、世界史の中でも一部に過ぎないのだ。
例えば本書には中国やインドは全く登場しない。イスラム世界も。
しかし、中国の各王朝が採った経済政策や鄭和による大航海が中国の歴史を変えた事は周知の事実だ。
さらに、いまの共産党政権が推進する一路一帯政策は、かつてのシルクロードの交易ルートをなぞっているし、モンゴル帝国がそのルートに沿った諸国を蹂躙し、世界史を塗り替えた事は誰もが知っている。
つまり、中華の歴史を語らずに世界史を名乗ることには無理がある。
同様に、イスラムやインドが数々のビジネス上の技術を発明したことも忘れてはならない。ビジネスモデルと世界史を語るにあたって、この両者も欠かすことが出来ない存在だ。
さて、ここまではタイトルと中身の違いをあげつらってきた。
だが、ローマ帝国の存在が世界史の中で圧倒的な地位を占めることもまた事実だ。
その存在感の大きさを示すように、本書は半分以上の紙数を使ってローマ帝国の勃興と繁栄、そして没落を分析している。
その流れにおいてビジネスモデルを確立したことが、ローマ帝国の拡大に大きく寄与した事が間違いない以上、本書の半分以上がローマ帝国の分析に占められていることもうなづける。。
国際政治学者の高坂正堯氏の著書でもローマ帝国については大きく取り上げられていた。
それだけ、ローマ帝国が世界史の上で確立したモデルの存在はあまりにも大きいのだろう。
それは政治、社会発展モデルの金字塔として、永久に人類史の中に残り続けるはず。もちろん、ビジネスモデルと言う側面でも。
ここで言うビジネスモデルとは、国家の成功モデルとほぼ等しい。
国家の運営をビジネスと言う側面で捉えた時、収支のバランスが適切でありながら、持続的な拡大を実現するのが望ましい。
これは私企業でも国家でも変わらない。
ただし、持続的な成長が実現できるのは、まだ未開拓の市場があり、未開拓の地との経済格差が大きい時だ。その条件のもとでは、物がひたすら売れ続け、未開の地からの珍しい産物が入ってくる。つまり経済が回る。
ローマ帝国で言えば、周辺の未開の版図を取り込んだことによって持続的な成長が可能になった。
問題は、ローマ帝国が衰退した理由だ。
著者は、学者の数だけ衰退した理由があると述べている。つまり、歴史的に定説が確立していないと言うことだろう。
著者は、経済学者でもあるからか、衰退の理由を経済に置いている。
良く知られるように、ローマ帝国が滅亡した直接的な原因は、周辺から異民族が侵入したためだ。
だが、異民族の襲来を待つ以前に、ローマは内側から崩壊したと著者は言う。
私もその通りだと思う。
著者はローマ帝国が内側から崩壊していった理由を詳細に分析していく。
その理由の一つとして、政治体制の硬直を挙げている。
結局、考えが守りに入った国家は等しく衰退する。これは歴史的な真理だと思う。もちろん私企業も含めて。
著者は最終的に、ディオクレティアヌス帝が統制経済を導入したことがローマ帝国にとってとどめだったと指摘している。つまり統制による国家の硬直だ。
勃興期のローマが、周辺の民族を次々と取り込み、柔軟に彼らを活かす体制を作り上げながら繁栄の道をひた走ったこととは対照的に。
著者は現代の日本の状況とローマ帝国のそれを比較する。
今の硬直しつつある日本が、海外との関係において新たな関係を構築せざるを得ないこと。それは決して日本の衰退を意味するものではないこと。
硬直が衰退を意味すると言う著者の結論は、私の考えにも全く一致するところだ。
既存のやり方にしがみついていては、衰退するという信念にも完全に同意する。
本書がローマ帝国の後に取り上げるヴェネツィア、ポルトガル、スペイン、大英帝国の勃興も、既存のやり方ではなく、新たなやり方によって富を生んだ。
海洋をわたる技術の発展により、交易から異なる土地へ市場を作り、それが繁栄につながったと見て間違いないだろう。
では、現代のわが国は何をすれば良いのか。
著者は、そのことにも紙数を割いて詳細に分析する。
日本人が海外に出たからず、島の中に閉じこもりたがる理由。
著者はそれを、日本が海洋国家ではなく島国であると言う一文で簡潔に示している。
海洋国家であるための豊富な条件を擁していながら、鎖国が原因の一つと思われる国民性から、守りに入ってしまう。
だからこそ、今こそ日本は真の意味で開国しなければならないと著者は提言している。
そこでヒントとなるのは、次の一文だ。
「この新しい産業社会においては、ローマ帝国から大航海時代までのビジネスモデルは参考になる。しかし、産業革命以降20世紀前半までのビジネスモデルは、参考にならない。むしろ、反面教師として否定すべき点が多いのである。(316ページ)
つまり、第二次大戦以降の高度成長期。もっと言えば明治維新以降の富国強兵政策が取り入れた西洋文明。
これらは全て産業革命以降に確立されたビジネスモデルをもとにしている。著者がいう反面教師であるビジネスモデルだ。
つまり、わが国の発展とは、著者によって反面教師の烙印が押されたビジネスモデルの最後の徒花に過ぎないのだ。
バブル以降の失われた20年とは、明治維新から範としてきた産業革命以降のビジネスモデルを、世界に通じる普遍的な手本と錯覚したことによる誤りがもたらしたものではないだろうか。
著者が本書で記した膨大な分析は、上に引用した一文を導くためのものである。
私たちは誤ったビジネスモデルから脱却しなければならない。そして、この百数十年の発展を、未来にも通用する成功とみなしてはならない。
本書には、ビジネス史でも有名な電話特許を逃した会社や、技術の先進性を見逃して没落した会社がいくつも登場する。
そうした会社の多くは、世の中の変化を拒み、既存のビジネスモデルにしがみ付いたまま沈没していった。末期のローマ帝国のように。
そして今、私たちは明らかな変化の真っ只中にいる。
情報技術が時間と空間の意味を変えつつある時代の中に。
わが国の多くの企業がテレワークの動きをかたくなに拒み、既存の通勤を続けようとしている。
だが、私にとってはそうした姿勢こそが衰退への兆しであるようにみえる。
おそらく五十年後には、いまの会社のあり方はガラリと変わっている事だろう。わが国のあり方も。
その時、参考となるのはまだ見ぬ未来の技術のあり方より、過去に人類が経験してきた歴史のはずだ。
本書の帯にはこう書かれている。
「「歴史」から目を背ける者は、「進歩」から見放される。」
本書を締めくくるのも次の一文だ。
「歴史に対する誠実さを欠く社会は、進歩から見放される社会だ。」(448ページ)
過去の栄光にしがみつくのは良くないが、過去をないがしろにするのはもっと良くない。
過去からは学べることが多い。本書において著者は、溢れるぐらいの熱量と説得力をもってそのことを示している。
歴史には学ぶべき教訓が無限に含まれているのだ。
‘2019/4/27-2019/5/8