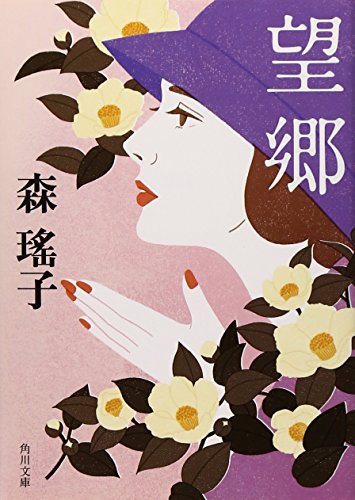私はウイスキーが好きだ。まだ三級しか取っていないが、ウイスキー検定の資格も得た。ウイスキー検定試験といってもなかなか難しい。事前に出題される問題を予習することが求められる。予習の中でウイスキーの歴史をひもといた時、まずでてくるのがウイスキーがはじめて文献に出てきた年だ。
1494年に出された文書にある「王の命令によりアクア・ヴィテ製造用に8ボルのモルトを修道士ジョン・コーに支給する」という文言。それがウイスキーの名前が文献に出てくる最初だという。
ウイスキーを好きになる時、味や香り、豊富な銘柄の豊富さにまず目がいく。続いて、ウイスキーの歴史にも興味が出てくる。それは、ウイスキーが時を要する飲み物であることが影響しているに違いない。出来上がるまでにぜいたくな時間が欠かせない飲み物。それを古人はどうやって発見し、どのように磨き上げてきたのか。わたしのような歴史が好きな人間はともかく、教科書を暗記するような歴史に興味がない方でも、ウイスキーに魅了された途端、ウイスキーの歴史に興味が出てくるはずだ。
だが、ウイスキーの歴史を把握することは案外と難しい。むしろ難解といっても良いぐらいだ。ウイスキーが史書に現れるのは、先に書いた通り1494年のこと。ただし、それ以降とそれ以前のウイスキーの歴史には謎が多い。それは、民が勝手気ままに醸造と蒸留を営み、時には領主の目を盗み、密造とは切っても切れないウイスキーの性格にも関係がある。つまり、ウイスキーの歴史には、体系だった資料は残されていないのだ。
だから、本当に1494年になるまでウイスキーは作られなかったのか、との問いに対する明快な答えは出しにくい。それが、ウイスキーの歴史に興味を持った者が抱く共通の疑問だ。同時にミステリアスな魅力でもある。
著者はその疑問を、ウイスキーの研修で訪れたスコットランドのエジンバラで強くいだく。というか疑問のありかを教わる。名も知らぬ老人。彼は著者に、ウイスキー作りは、ケルト民族の手によって外からスコットランドにもたらされた、と語る。外とはアイルランドのこと。つまり、アイルランドでは1494年よりもっと以前からウイスキーが作られていたはず。著者はそのような仮説を立てる。本書は、その仮説を立証するため、著者は費やした広大な旅と探求の記録だ。
著者はサントリーの社員だ。そして長年、ウイスキー部門に配属されていた。毎日の業務の中で、ウイスキーに対する見識を鍛えられてきた。本書のプロローグには、著者が農学部の学生の頃からゼミの教授にウイスキーをはじめとした蒸留酒について啓蒙されてきたことも記されている。著者はもともと、酒類全般への造詣が深く、酒つくりの起源を調べるための基本知識は備えていたのだろう。その素養があった上に、旅先での老人からの示唆が著者の好奇心を刺激し、著者のウイスキーの起源の謎を解く旅は始まる。
著者が持つお酒に関する教養のベースは、本書の前半で折々に触れられて行く。教授から教えられたこと。ウイスキーに開眼した時のこと。安ワインで悪酔いした学生時代から、後年、高級ワインのおいしさに魅了され、ワインの奥深さにはまっていったこと。ウイスキー作りに携わりたいとサントリーを志望し、入社したことや、そのあと製造畑で歩んだ日々。ウイスキー作りの研修でスコットランドやアイルランドに訪れた事など。そこには苦労もあったはずだが、酒好きにすればうらやましくなる経歴だ。
まずはエジプト。著者はエジプトを訪れる。なぜならエジプトこそがビールを生み出した地だからだ。ビールが生み出された地である以上、蒸留がなされていてもおかしくない。蒸留が行われていた証拠を探し求めて、著者はカイロ博物館を訪れる。そこで著者が見たのは、ビール作りがエジプトで盛んであった証拠である遺物の数々だ。旧約聖書を読んだことがある方は、モーゼの出エジプト記の中で、空からマナという食物が降ってきて、モーゼに着き従う人々の命を救ったエピソードを知っていることだろう。そのマナこそはビールパン。ビールを作るにあたって作られる麦芽を固めたものがマナである。しかし、イスラエルにたどり着いて以降のモーゼ一行に、マナが与えられることはなかった。なぜなら、イスラエルは麦よりもブドウが生い茂る地だったからだ。エジプトで花開いたビール文化はイスラエルでワイン文化になり替わった。
この事実は後年、アラビアで発達した蒸留技術がウイスキー造りとして花開かなかった理由にも符合する。そもそも蒸留技術それ自体は、イスラム文化よりずっと前から存在していたと著者は説く。エジプトでも紀元前2000年にはすでに蒸留技術が存在したことが遺物から類推できるという。しかし、蒸留技術は記録の上では、ミイラや香油作りにのみ使われたことしか記録に残っていないらしい。酒を作るために蒸留が行われた記録は残っていない。このことが著者の情熱にさらなる火をくべる。
一方、キリスト教の一派であるグノーシス派の洗礼では「生命の水・アクアヴィテ」が使われていたという。それはギリシャ、イタリア、フランスで盛んだったワイン製造が蒸留として転用された成果として納得しうる。ワイン蒸留、つまりブランデーだ。それがローマ帝国の崩壊後、今のヨーロッパ全域に蒸留技術が広まるにつれ、酒として飲まれるようになる。そして、ドイツ・イギリスなどブドウが成らない北の国では穀物を基にした蒸留酒として広まっていった。
著者はウイスキー造りの技術が1494年よりずっと以前に生まれていたはず、との仮説を胸に秘め、調査を進める。ついで著者が着目したのが、アイルランドに伝わったキリスト教だ。アイルランドのセント・パトリックスデーは緑一色の装束でよく知られている。その聖パトリックがアイルランドでキリスト教を布教したのは4~5世紀の事。当時のアイルランドには、ローマ帝国の統治がぎりぎり及んでいなかった。ところが、すでにキリスト教が根付いていた。後にキリスト教がローマ帝国全域で国教とされる前から。そればかりか、土着のドルイド教とも融合し、アイルランドでは独自の文化を築いていた。その時に注目すべきは、当時のブリタニアやアイルランドではブドウが育たなかったことだ。ローマ帝国にあった当時のアイルランドやブリタニアでは、ワイン文化が行き渡っていたと思われる。ところが、ワインが飲めるのは、ローマからの供給があったからこそ。ところが、ローマ帝国の分裂と崩壊による混乱で、ワインが供給されなくなった。それと同時に、混乱の中で再び辺境の島へ戻ったブリタリアとアイルランドには、独自のキリスト教が残された。著者はその特殊な環境下で麦を使ったアクアヴィテ、つまりウイスキーの原型が生まれたのではないかと推測する。
このくだりは本書のクライマックスともいうべき部分。ウイスキー通に限らず、西洋史が好きな方は興奮するはず。ところが、アイルランドのあらゆる遺跡から著者の仮説を裏付ける事物は発掘されていない。全ては著者の想像の産物でしかない。それが残念だ。
本書はそれ以降、アイルランドの歴史、アイルランドでウイスキー造りが盛んになっていたいきさつや、スコットランドでもウイスキー造りが盛んになっていった歴史が描かれる。その中で、著者はアイルランドでなぜウイスキーが衰退したのかについても触れる。アイルランドでの製法にスコッチ・ウイスキーでなされたような革新が生まれなかったこともそう。アイリッシュ・ウイスキーにとって最大の市場だったアメリカで禁酒法が施行されたことなど、理由はいろいろとある。だが、ここ近年はアイルランドにも次々と蒸留所が復活しているという。これはウイスキーブームに感謝すべき点だろう。
本書で著者が試みた探索の旅は、明確な証拠という一点だけが足りない。だが、著者の立てた仮説には歴史のロマンがある。謎めいたウイスキーの起源を解き明かすに足る説得力もある。
何よりも本書からは、ウイスキーのみならず、酒文化そのものへの壮大なロマンが感じられる。酒文化とともに人々は歴史を作り上げ、人々の移動につれ、酒文化は多様な魅力を加えてきた。それは、酒好きにとって、何よりも喜ばしい事実だ。
‘2018/7/29-2018/08/13