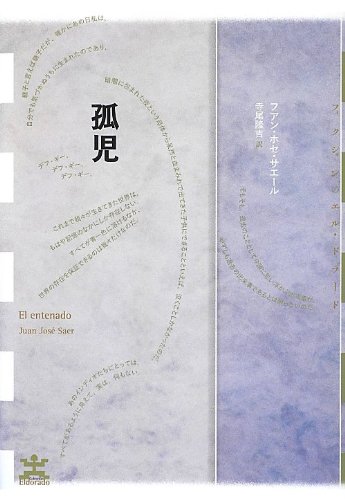
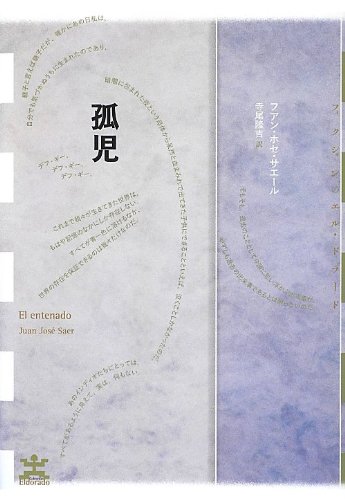
本書にはヒトの営みが描かれている。「ヒト」と書いたのは、もちろん動物としてのヒトのこと。
原初の人類を色濃く残す16世紀の南米インディオたち。南米全域がポルトガルとスペインによって征服され、キリスト教による「教化」が及ぶ前の頃。本書はその頃を舞台としている。
孤児として生まれた主人公は、燃える希望を胸に船乗りとなる。そして新大陸インドへと向かう船団の一員となる。船団長は寡黙な人物で、何を考えているのかわからない。何日も何週間も空と太陽のみの景色が続いた後、船団はどこかの陸地に着く。
そこで船団長は感に耐えない様子で、「大地とはこの・・・」と言葉を漏らした直後、矢を射られて絶命する。現地のインディオたちに襲われ、殺される上陸部隊。主人公だけはなぜか殺されない。そして生け捕りにされインディオの集落に連れて行かれる。「デフ・ギー! デフ・ギー! デフ・ギー!」と謎の言葉でインディオたちに呼び掛けられながら。
はインディオの集落に連れて行かれ、インディオたちの大騒ぎを見聞きする。それはいわば祭りの根源にも似た場 。殺した船乗りたちを解体し、うまそうに食べる。そして興奮のまま老若男女を問わず乱交する。自分たちで醸した酒を飲み、ベロベロになるまで酔っ払う。そこで狂乱の中、命を落とす者もいれば前後不覚になって転がる者もいる。あらゆる人間らしさは省みられず、ケモノとしての本能を解き放つ。ただ本能の赴くままに。そこにあるのは全ての文明から最もかけ離れた祭りだ。
インディオたちによる、西洋世界の道徳とはかけ離れた振る舞い。それをただ主人公は傍観している。事態を把握できぬまま、目の前で繰り広げられる狂宴を前にする。そして、記憶に刻む。主人公の観察は、料理人たちがらんちき騒ぎに一切参加せず、粛々と人体をさばき、煮込み、器に盛り、酒を注ぐ姿を見ている。西洋の価値観から対極にあり、あらゆる倫理に反し、あらゆる悪徳の限りを尽くすインディオ達。そしてその騒ぎを冷静に執り行う料理人たち。
捕まってから宴が終わるまで、主人公はずっとインディオたちの好奇心の対象となる。そしてインディオたちはなぜか主人公に声を掛け、存在を覚えてもらおうとする。デフ・ギー! デフ・ギー! デフ・ギー!何の意味かわからないインディオの言葉で呼びかけながら。なぜインディオ達は主人公に向けて自分のことをアピールするのか。
しかも、宴が終わり、落ち着いたインディオたちはこれ以上なく慎みに満ちた人々に一変する。タブーな言葉やしぐさ、話題を徹底して避け、集団の倫理を重んずる人々に。そして冬が過ぎ、日が高くなる季節になるとそわそわし出し、また異国からやってきた船団を狩りに出かけるのだ。
主人公はその繰り返しを十年間見聞きする。自分が何のために囚われているのかわからぬままに。主人公が囚われの身になっている間、一人だけ囚われてきたイベリア半島の出身者がいる。彼はある日、大量の贈り物とともに船に乗せられ海へ送り出されていく。インディオたちの意図はさっぱりわからない。
そしてある日、主人公はインディオ達から解放される。十年間をインディオたちの元で過ごしたのちに。イベリア半島の出身者と同じく、贈り物のどっさり乗った船とともに送り出され、海へと川を下る。そして主人公は同胞の船に拾われ、故国へと帰還する。十年の囚われの日々は、主人公から故国の言葉を奪った。なので、言葉を忘れた生還者として人々の好奇の目にさらされる。故国では親切な神父の元で教会で長年過ごし、読み書きを習う。神父の死をきっかけに街へ出た主人公は、演劇一座に加わる。そこで主人公の経験を脚色した劇で大当たりを引く。そんな主人公は老い、今は悠々自適の身だ。本書は終始、老いた主人公が自らの生涯を振り返る体裁で書かれている。
そしてなお、主人公は自らに問うている。インディオたちの存在とは何だったのか。彼らはどういう生活律のもとで生きていたのか。彼らにとって世界とは何だったのか。西洋の文化を基準にインディオをみると、全てがあまりにもかけ離れている。
しかし、主人公は長年の思索をへて、彼らの世界観がどのような原理から成り立っているかに思い至る。その原理とは
、不確かな世界の輪郭を定めるために、全てのインディオに役割が与えられているということだ。人肉を解体し調理する料理人が終始冷静だったように。そして冷静だった彼らも、翌年は料理人の役割を免ぜられると、狂態を見せる側に回る。主人公もそう。デフ・ギーとは多様な意味を持つ言葉だが、主人公に向けられた役割とは彼らの世界の記録者ではないか。彼らの世界を外界に向けて発信する。それによってインディオ達の世界の輪郭は定まる。なぜなら世界観とは外側からの客観的な視点が必要だからだ。外界からの記憶こそが主人公に課せられた役目であり、さらには本書自体の存在意義なのだ。
インディオたちは毎年決まった周期を生きる。人肉を食べ、乱交を重ね、酒乱になり、慎み深くなる。それも全ては世界を維持するため。世界は同胞たちで成り立つ。だからこそ人肉は食わねばならない。そして性欲は共有し発散されなければならないのだ。それら営みの全ては、外部に向け、表現され発信されてはじめて意味を持つ。それが成されてはじめて、彼らの営みはヒトではなく、人、インディオとして扱われるからだ。もちろんそれは、なぜサルが社会と意識を身につけ、ヒトになれたのかという人類進化の秘密にほかならない。
訳者あとがきによれば、実際に主人公のように10年以上インディオに囚われた人物がいたらしい。だが、その題材をもとに、世界観がどうやって発生するか、というテーマにまで高めた本書は文学として完成している。見事な作品展開だと思った。
‘2017/07/19-2017/07/24


