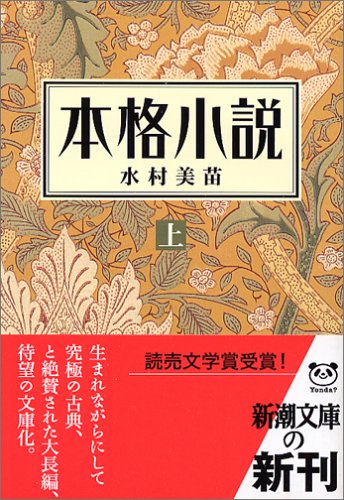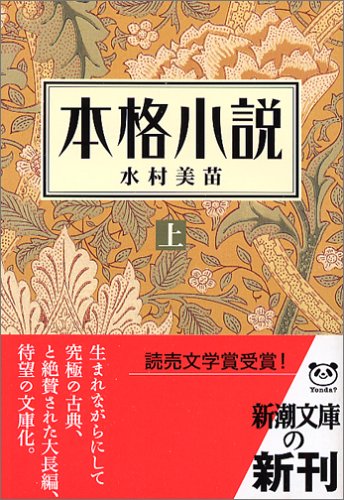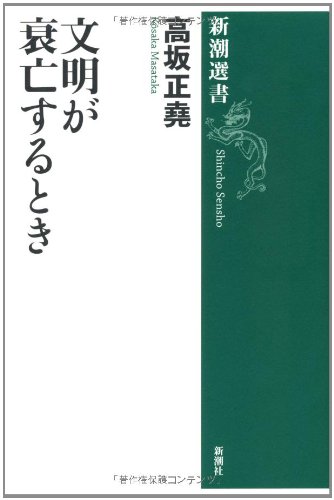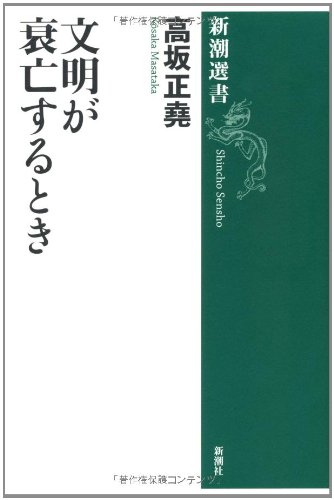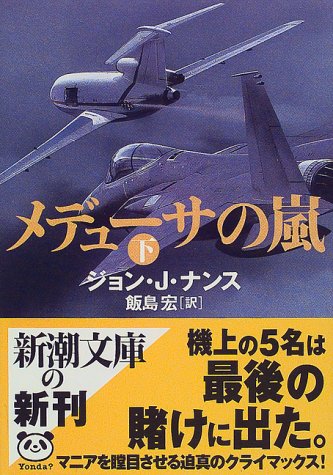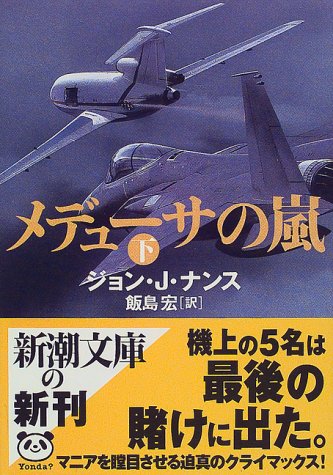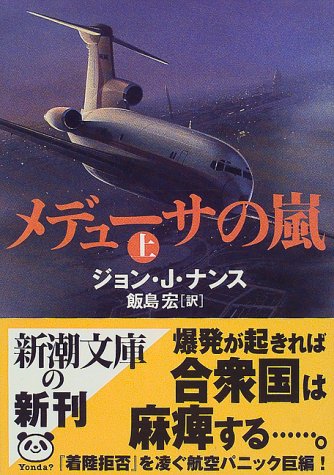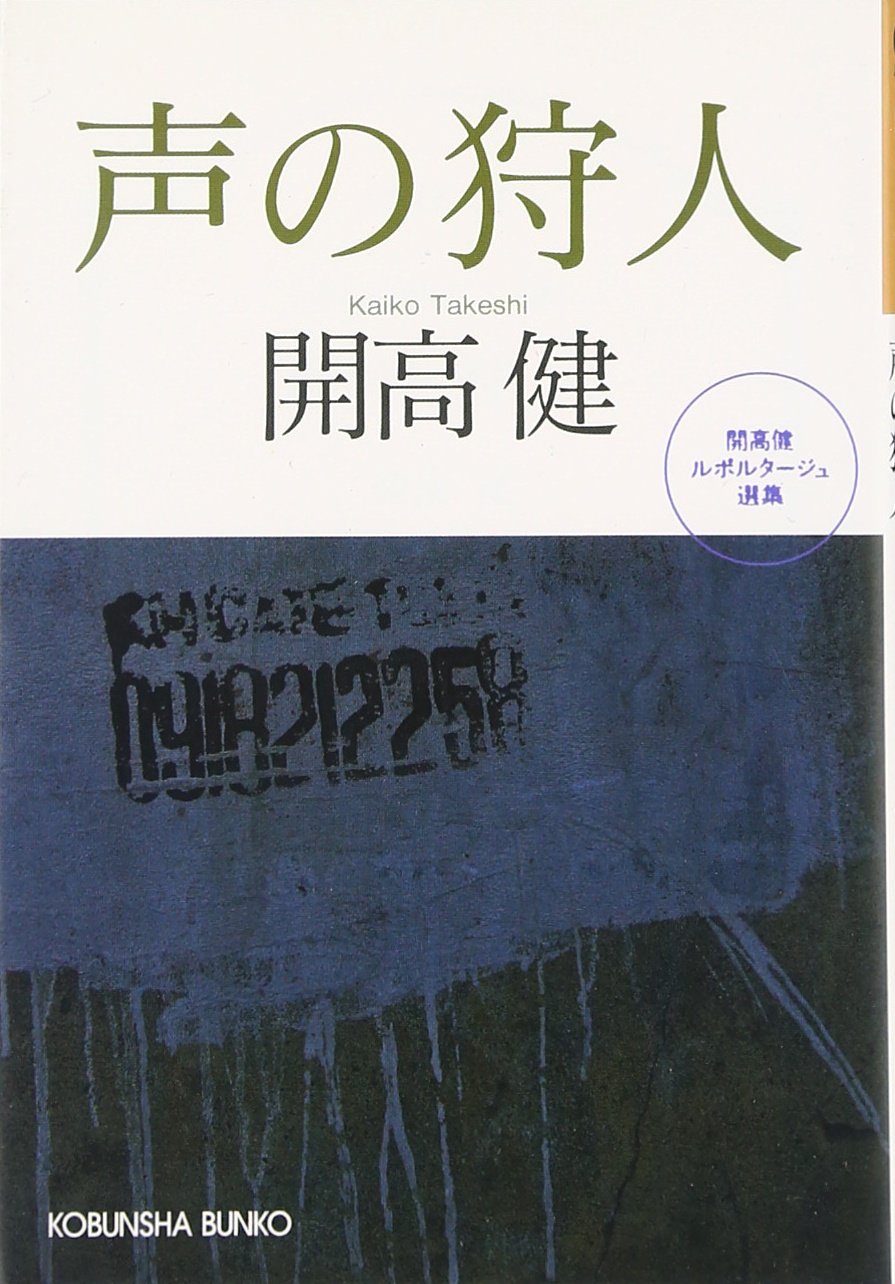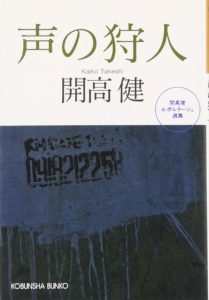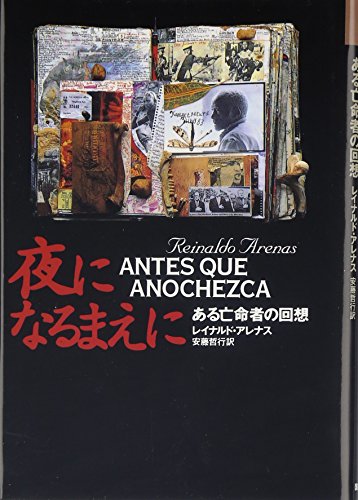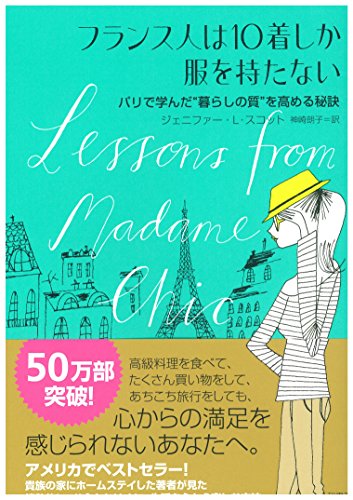若い時には理想主義にふけっていた私。利潤の追求は間違っている、とかたくなに信じていた。人々が利潤を独占せず、広く人々に共有できれば、世の名はもっと良くなる。半ば本気でそんなことを考えていた。
経営者になった今、さすがに利潤を無視するわけにはいかない。それは利潤が利潤を呼び、いつまでも成長することが経済のあり方だから、と無邪気に信じているからではない。有限の資源しかない地球でそんなことは不可能だ。利潤を追い求める営みを認めるのは、私の中に飢えへの恐怖があるからでもない。
今、私は経営者として順調に売り上げを上げ続けている。だが、それは私が健康だからできること。何かの理由で仕事ができなくなったとたん、収入は途絶える。そうなったら飢えの恐怖が私の心身をむしばむに違いない。その恐れは常に心のどこかに居座っている。私の心身に異常が生じた時、どこからともなく助けが得られる。などと虫のいいことは考えていない。よしんば助けが得られたとしても、それは最低限の生活を送るための資金がせいぜいだろう。だから私は、利潤を追い求めるだけが人生ではない、という理想は捨てていないが、経済の論理は無視できないと思っている。
そこで、ベーシック・インカムだ。生きていくのに必要な金額が国から支給される。しかも無条件に。助成金や補助金のような複雑な申請はいらない。ただ、もらえる。魅力でしかない制度だ。
だが、経営者になった今、私はこの制度に無条件に賛成できないでいる。それは、私が経営者になった事で、勤しんだ努力だけ見返りがあるやりがいを知ってしまったからだ。勤め人だった頃のように失敗や逆境を周囲のせいにする必要はない。失敗は全て己のせい。逆に努力や頑張りが見返りとして帰ってくる。全ての因果が明確なのだ。見返りがあるということは人を前向きにする。それは人間に備わった本能からの欲求だ。楽になりたいとか、利潤が欲しいという理由ではなく、自分の生き方を自分で管理できる喜び。
だから、私はベーシック・インカムの思想にある「無条件に」という言葉には引っかかりを感じる。「無条件に」という言葉には、努力や責任が一切無視されている。もちろん、弱い立場の方に対してベーシック・インカムが適用されることは否定しない。私がもし、体を壊して仕事ができなくなった時、ベーシック・インカムから無条件に給付を受けられればどれだけ助かるか。それを考えた時、弱い方へのセーフティとしてのベーシック・インカムは必要だと思う。だが、それでは今の福祉制度と変わらなくなってしまう。
私が抱えるベーシック・インカムへの矛盾した思い。その疑問を解決するには勉強しなければ。本書はそうした動機で手に取った。
本書は全6章からなっている。ベーシック・インカムの理念や仕組みだけでなく、古くから検討されてきたベーシック・インカムの歴史が紹介されている。民主主義の勃興に時期を合わせるようにベーシック・インカムは提唱されてきた。その歴史は意外と古い。今までの人類の歴史で、幾人もの哲学者や経済学者、また、マーティン・ルーサー・キングの様な著名な運動家がベーシック・インカムの考えを提唱してきた。ベーシック・インカムはにわかに現れた概念ではないのだ。私は本書を読むまでベーシック・インカムの長い歴史を全く知らなかった。
第1章 働かざる者、食うべからずー福祉国家の理念と現実
この章ではベーシック・インカムの要諦が語られる。著者はその定義をアイルランド政府がベーシック・インカム白書の中で示した定義から引用する。
・個人に対して、どのような状況におかれているかに関わりなく無条件に給付される。
・ベーシック・インカム給付は課税されず、それ以外の所得は全て課税される。
・給付水準は、尊厳をもって生きること、生活上の真の選択を行使することを保障するものであることが望ましい。その水準は貧困線と同じかそれ以上として表すことができるかもしれないし、「適切な」生活保護基準と同等、あるいは平均賃金の何割、といった表現となるかもしれない。
より詳しい特徴として、本書はさらに同白書の内容から引用する。
(1)現物(サービスやクーポン)ではなく金銭で給付される。それゆえ、いつどのように使うかに制約はない。
(2)人生のある時点で一括で給付されるのではなく、毎月ないし毎週といった定期的な支払いの形をとる。
(3)公的に管理される資源のなかから、国家または他の政治的共同体(地方自治体など)によって支払われる。
(4)世帯や世帯主にではなく、個々人に支払われる。
(5)資力調査なしに支払われる。それゆえ一連の行政管理やそれに掛かる費用、現存する労働へのインセンティブを阻害する要因がなくなる。
(6)稼働能力調査なしに支払われる。それゆえ雇用の柔軟性や個人の選択を最大化し、また社会的に有益でありながら低賃金の仕事に人々がつくインセンティブを高める。
この章では他にもベーシック・インカムのメリットが紹介される。その中で、社会保険や公的扶助の現状もおおまかに紹介される。そうした制度が対象とする貧困層に対し、国家はどう認識し、どう対処してきたのか。それは国が行うべき機能の一つと挙げられている。だが、かつて貧困層とは国から完全に見捨てられた層だった。
貧困層とは、雇用されず、生計が成り立たない人々をさす。国としてみれば完全雇用が達成されれば社会保障は不要。だが、現実にはそうはいかない。しかも日本の場合、生活保護対象世帯のうち、実際に保護を受けているのは二割程度だという。これは捕捉率というそうだが、先進国の中でも日本の捕捉率は際立って低いそうだ。
そもそも生活保護とは、貧困者を選別する制度につながる。他にも公的な社会システムはある。そのうち、生活保護制度だけが対象を選別するそうだ。選別という行為は、為政者にとって避けたい。ならば、誰に対しても等しく適用されるベーシック・インカムの制度のほうが政策にも取り入れやすい。そうした観点を著者は説く。
日本ではそのため、完全雇用に近づけるようなワーク・フェアの施策がとられていると著者は指摘する。完全雇用が達成できれば、民間に福祉を完全に委ねられる。そのような発想だろう。だが、諸外国のワーク・フェアと比べ、日本のワーク・フェアには公の補助が欠けているという。
第2章 家事労働に賃金を!ー女たちのベーシック・インカム
本章では、アメリカやイタリア、イギリスで繰り広げられたここ数十年のベーシック・インカムの運動をおさらいする。女性がベーシック・インカムを主張する場合、通常の値上げ運動とは性格が異なる。というのも、通常の値上げ運動は失業時や低所得者の救済を主な目的とする。だが、そうした運動には女性の家事労働に視点が向いていない。そもそも女性が家事労働に従事する場合、それ自体に報酬が支払われることはない。一般的な家庭では、夫たる男性が外で稼ぎ、収入を持ち帰る。妻たる女性は、それを受け取り、家庭のために使う。つまり、夫から受け取る金額の中に、家事労働の報酬も暗黙のうちに含まれている。そのような解釈だ。
だが、報酬を暗黙でなく、家事労働それ自体に報酬を与えよ、というのが彼女たちの主張だ。だが、家事労働の労力など測れるはずもない。なので、女性に対するベーシック・インカムを要求するのが、本章で取り上げる運動の趣旨だ。
アメリカでの運動にはマーティン・ルーサー・キング牧師が関わっていた。そこには公民権運動の一環としての性格もあったのだろう。当時、黒人の女性は弱い立場にあった。それを救済するための手段の一つとして検討されたのがベーシック・インカムだった。イタリアではその運動がもう少し趣を変え、家事労働自体が他の賃金労働と等しく労働だ、という主張がなされた。ただ、ここで誤解してはならないのが、主婦業への賃金を求める運動ではなかったということだ。
イギリスでは要求者組合という形をとり、弱者への福祉も含めた運動に広がってゆく。その中で、受給資格をめぐる議論もより深まっていったという。例えばベーシック・インカムを受ける資格がある女性は、一人暮らしなのか、男性と同居しているか、結婚しているか、など。要は生計を男性に援助してもらっているかどうかによって、ベーシック・インカムの受給資格は変動する。
第3章 生きていることは労働だー現代思想のなかのベーシック・インカム
本章では、アメリカやイギリスでは女性によるベーシック・インカムの運動が衰退したが、イタリアでは発展して長く続いた理由を考察する。そこには賃労働の拒否、そして家事労働の拒否、という二重の拒否があった。ベーシック・インカムはその主張の解決策でもあった。それは、労働の価値化をどう捉えるか、という次の考察につながってゆく。労働とは通常、何か基となるものから付加価値を生み出す営みを指す。生み出された付加価値のうち、労賃が労働者に支払われるというのが古典的な経済の考えだ。そして、今までは家事労働には付加価値が発生しないと考えられていた。発生したとしてもそれは家庭内で消費されてしまうと。もし家事労働に付加価値が発生するとすれば、それは夫である労働者が外で付加価値を生み出すための労働であり、子供という次代の労働力を社会に生み出すための労働であり、それ自体に価値を見いだす考えがなかった。
本章では、行きていること自体が労働という観念が紹介される。生きているだけで労働と認められるなら、その労働には賃金が支払わねばならない。それこそがベーシック・インカムという論法だ。その考えは斬新にも思えるし、突飛にも思える。もちろん、その考えが認められれば、ベーシック・インカムの論理はこれ以上なく確かなものだろう。なにしろ、仕事内容や性別、資産に応じた額の増減を考えずに済むからだ。
日本でも青い芝の会という障害者の権利向上を求める集まりがあるそうだ。青い芝の会では、障害者は生きている、すなわち労働だとの考えに基づいているという。著者はそれもベーシック・インカムに近いと考えているようだ。
後に触れるように原資をどうするか、という問題を脇に置くとすれば、私もこうした考えをベーシック・インカムの一つとみなすことに賛成したい。
間奏 「全ての人に本当の自由を」ー哲学者たちのベーシック・インカム
ここでは哲学者たちがベーシック・インカムをどう考えてきたかについて触れられる。ベーシック・インカムは社会主義や無政府主義に比べ、人類にとって適正な制度であるというバートランド・ラッセルの説や、真の自由を人類が得るためには、必要だとするフィリップ・ヴァン=パレイスの考えが紹介される。苦痛からの逃れる意味での自由ではなく、より真の意味での自由。ベーシック・インカムが給付された場合、生存のために働く必要はなくなる。だが、それでも働きたい人が働く自由も保証されるべき。そうした選択の幅が拡充されるのがベーシック・インカムの根本思想だという。
第4章 土地や過去の遺産は誰のものか?ー歴史のなかのベーシック・インカム
ベーシック・インカムの考え方は、社会制度が封建主義から次の民主主義に移ってしばらくしてから生まれた。それは同時に経済制度が資本主義に変わったとみなしても良い。要するに近代の社会制度が生まれ、ベーシック・インカムの考え方も芽生えた。本書はそれらの紹介を順に進めてゆく。現代の資本主義国家では、土地の私有が認められている。だが、資本主義が勃興した当初、土地は共有という考えがまだ支配的だった。つまり誰にでも土地の権利があり、その土地から収入を得られる権利があったということだ。その考えを敷延すると、まさにベーシック・インカムの考え方そのものとなる。無条件で収入を得る権利というベーシック・インカムの考え方が、土地の扱いという観点で資本主義の発生時からあったことを著者は指摘する。
その考えは、経済学の中でも代々受け継がれてきたという。弱者を救済するための社会制度という性格は同じだが、保険や保護を社会が担うのではなく、無条件に給付するベーシック・インカムのほうが、制度として有効だとの考えも一定数で唱えられていたそうだ。それは、社会主義が見事に失敗した今でも変わらない。
著者はここで、経済制度の分析にまで踏み込んでいない。だが、現行の資本主義の制度の中でも、土地が共有である考えは受け継がれていて、ベーシック・インカムの根拠となる考えは有効であるとの立場のようだ。それはもちろん、人は生きているだけで労働だからベーシック・インカムの権利がある、という考えにも照応する。
第5章 人は働かなくなるか?ー経済学のなかのベーシック・インカム
ここが今の私には関心の高い点だ。
今の社会福祉は、労働を前提としている。だが、社会からは明らかに人間が必要な労働量が減ってきている。それは、技術革新の恩恵にあずかるところが大きい。つまり、労働がないのに報酬を払わねばならない未来が近づいている。もしそうなったら、労働を基に付加価値をつける営利組織はたちまち立ちいかなくなる。だからこそ国や団体による報酬の支給が必要というわけだ。こうした課題を経済学者は今までさんざん議論してきた。
本書に紹介されるのは、どちらかというとベーシック・インカムに賛成の立場の論考だ。だから反対の意見はあまり登場しない。それを差し置いても、今の社会制度で福祉を継続するためには、保険や保護に頼るのは困難になりつつある。そのような意見が優勢になりつつあると著者は指摘する。
ただ、本書の全体を通し、説得力のあるベーシック・インカムの財源が登場しない。これは考えものだ。たぶん現実問題として、財源の不足こそがベーシック・インカムが普及しない最大の理由だと思うからだ。私としては、ベーシック・インカムの普及には技術の力が欠かせないと思っている。資本からではなく、技術の力で全く違う資源からベーシック・インカムとして支給する何かを生み出す。それが実現するまで、私はベーシック・インカムの実現は難しいと思う。
もう一つ、日本においてそれほどベーシック・インカムの議論が熱中しないのは、わが国には自治体による道路、水道、ガス、電気といったインフラが整備されているからだ。現時点で民営化されているとはいえ、こうしたインフラはもともと国家による国民へのサービスだった。だから現状で十分なサービスを享受できているわが国民にさらにベーシック・インカムの恩恵を施す必要はあるのか、という疑問が生じる。
インフラも整っておらず、実際に生活を送るには収入が欠かせない国の場合、ベーシック・インカムの必要性はある。ただ、生活必需品をそれほど労せずに享受できるわが国では、ベーシック・インカムの普及についての議論が深まらない。もちろん、より多様性のあるサービスを受けられる選択の幅があっても良いと思う。だからこそサービスではなく財で等しく受給できるベーシック・インカムは、国民がサービスを自由に選ぶために必要なのかもしれない。原資の安定供給を技術の進化に頼らねばならない現状は変わらないにせよ。
今、年金制度の崩壊が叫ばれている。年金は、その支給の資金を原資をもとに投資した利子でまかない、支給額を安定確保するために努力していると聞く。つまり、既存の旧来の拡大成長を前提とした経済論理に年金制度は完全に組み込まれている。有限の地球に無限の拡大成長は考えにくいとすれば、それをベースに考えられた福祉にどれほどの期待が持てるのだろう。
もちろん、福祉サービスとベーシック・インカムは別ということは理解している。ただ、本章でも提示されているように、何らかの社会的な貢献活動の代償は制度として設けられているべきだと思う。つまり、働いてこそ代償は受け取れる、という考えだ。
第6章 〈南〉・〈緑〉・プレカリティーベーシック・インカム運動の現在
だからこそ、本章で取り上げられる現在のベーシック・インカムを分析する視野が必要だと思う。章のタイトルにある<南>とは既存の資本主義の熟練国ではなく、新興の国々を指す。要はいまだ発展途上にある国々の事だ。<緑>というのは緑の党のような、持続が可能な社会を目指す人々を言う。
ここで著者はエーリッヒ・フロムを登場させる。フロムもまたベーシック・インカムの提唱者だったそうだ。彼は著書『自由からの逃走』で著名だ。その中で彼が唱えたのは自由を持て余した人々がナチスを生んだという理論だ。だが、それとは別に、ベーシック・インカムこそが人々をより自由にするとの考えも持っていたらしい。そして、彼は財ではなく生活必需品の提供でならばベーシック・インカムが成り立つのではないか、と考えていたそうだ。上にも書いたとおり、私はすでに物資が充実している日本では、生活必需品の提供というベーシック・インカムは成り立たないと思う。著者も同じ考えをもっているようだ。
プレカリティという言葉の意味は本章には出てこない。調べたところ、不安定とか予測できないという意味のようだ。第二章で登場した各国のベーシック・インカム運動のその後が本章では紹介される。どうすれば人々がひとしく恩恵を受けられるのか。それはかつての私がまさに目指そうとした社会でもある。そのような社会の実現が経営者としての立場では難しいことも理解している。まさに今の経済制度では現実は不安定で将来は予測できない。だが、これからも理想の実現に向けた努力は注視していきたいと思っている。
本書は各章ごとにまとめが設けられたり、巻末でもあらためてベーシック・インカムのQ&Aの場が設けられたり、各章のあとにはコラムが設けられたり、なるべく読者への理解を進めるような工夫がちりばめられている。何が人類にとって最適な福祉なのか、本書は一つの参考資料となるはずだ。私も自分の理想がどこにあるのか、さらなる勉強を重ねたいと思う。
‘2018/10/17-2018/10/23