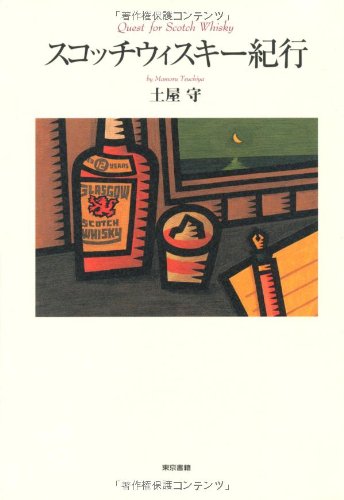
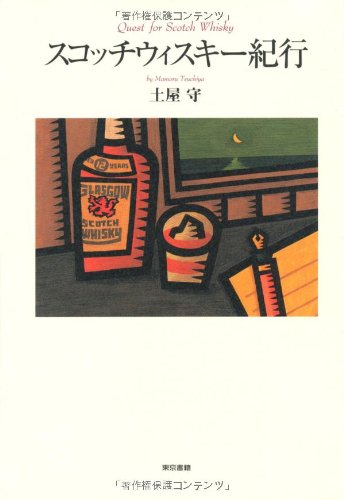
私がウイスキーの魅力にはまってから、長い年月が過ぎた。
そのきっかけとなった日の事は今でも覚えている。1995年8月5日から6日にかけてだ。
当時、広島に赴任中だった大学の先輩の自宅で飲ませてもらった響17年。この時に味わった衝撃から私は飲んべえに化けた。
その前日は原爆ドームの前でテントを張った。響に耽溺した翌朝は、原爆投下から50年を迎えた瞬間をダイ・インで体感した。
そうした体験も相まって、ウイスキーの魅力に開眼した思い出は私の中に鮮烈に残っている。
以来、20数年。ウイスキーの魅力に開眼してからの私は、ウイスキーを始めとした酒文化の全般に興味を持つようになった。
ウイスキーを学ぼうとした当時の私のバイブルとなった本がある。
その本こそ、本書の著者である土屋守氏が著した『モルトウイスキー大全』と『シングルモルトウイスキー大全』だ。
著者の土屋氏には、今までに二回お会いしたことがある。
初めてお会いしたのは、妻と訪れた埼玉のウイスキー・フェアだった。ブースには人がまばらで、一緒にツーショット写真を撮っていただく幸運にあずかれた。懐かしい思い出だ。
二度目はWhisky Festival in Tokyoの混雑した会場の中で友人と一緒の写真に入っていただいた。
忙しいさなかに、大変申し訳なかったと思っている。
もちろん土屋氏は私のことなど覚えていないはず。
本書は、世界のウイスキーライターの五人に選ばれた著者がウイスキーの魅力を語っている。
本書はTHE Whisky Worldの連載をベースにしているそうだ。THE Whisky Worldとは、土屋氏が主催するウイスキー文化研究所(古くはスコッチ文化研究所)が発行していた雑誌だ。
その研究所が出版する酒に関する雑誌は、WHISKY Galoreとして名を一新した後も毎号を購入している。さらに書籍も多くを購入してきた。
そのどれもが、情報量の豊富さと酒文化に対する深い愛情と造詣に満ちており、私を魅了してやまない。多分、これからも買い続けるだろう。
本書はスコッチの本場を訪れた記録でもある。
冒頭に各地域や蒸留所の写真がカラーで載っている。
その素朴かつ荒涼とした大地のうねり。その光景は、私の眼にとても魅力的に映る。
荒涼とした景色に魅せられる私。
だからこそ、そこから生まれるウイスキーにハマったのかもしれない。
よく知られているように、スコッチウイスキーという名前だが、複数の地域によって特徴がある。
アイラ、スペイサイド、ハイランド、ローランド、その他ヘブリディーズ諸島やオークニー諸島のアイランズウイスキー。
今のウイスキーの世界的な盛況は、スコッチの本場にも次々と新たな蒸溜所を生んでいる。
そのため、本書に登場する蒸留所の情報は少しだけ古びている。10年前のウイスキーの情報は、目まぐるしく活気のあるウイスキー業界ではすでに情報としては古びている。毎年のように新たな蒸留所が稼働をはじめ、クラフト・ディスティラリーを含めるとその数はもはや数えられない。
だからといって、本書に価値がないと思うのは間違いだ。
本書は世界的なウイスキーブームに沸く少し前の情報が載っているため、むしろ信頼できると思う。
今や、あらゆる蒸留所が近代化に向けて投資を進めている。その一方で、古いやり方を守り続ける蒸留所も本書にはたくさん紹介されている。
先にも書いたとおり、著者はウイスキー文化研究所と言う研究所を主催している。そのため著者が著わす文章や情報からは、スコッチウイスキーに関してだけでなく、スコットランドを包む文化についての知識も得られる。
特に本書の第二部「ウィスキーと人間」では、スコットランドの歴史を語る上で欠かせない人物が何人も取り上げられている。
その一人は長崎のグラバー園でもお馴染みのトーマス・ブレイク・グラバーだ。マッサンこと竹鶴正孝氏の名前も登場する。また、ウイスキーの歴史を語る上で欠かせないイーニアス・コフィーであったり、アンドリュー・アッシャーといった人々も漏れなく載っている。また、意外なところではサー・ウィンストン・チャーチルにも紙数が割かれている。
それぞれがスコットランドもしくはウイスキーの歴史の生き証人である。
ウイスキーとは、時間を重ねるごとにますますうま味を蓄える酒。それはすなわち、歴史の重みを人一倍含む酒だ。その歴史を知る上で、ウイスキーに関する偉人を知っておいたほうがいいことは間違いない。
第三部は「ウィスキーをめぐる物語と謎」と題されている。
例えば、日本人が初めて飲んだウイスキーのこと。また、ウイスキーキャットにまつわる物語について。かと思えば、ポットスチルと蒸留の関係を語る。そうかと思えば、謎に包まれたロッホ・ユー蒸溜所も登場する。また、グレン・モーレンジの瓶に記されている紋章の持ち主、ピクト族も登場する。また、ロード・オブ・ジ・アイルズの島々の歴史や文化にも触れている。
第三部を読んでいると、ウイスキーをめぐる物語の何が私を惹きつけるのかがわかる。
それは、ケルト民族の謎に包まれた歴史だ。
ケルト民族が現代に残したロマンは多い。ウイスキー、ドルイド教、ケルト十字、ストーンヘンジ。
それらはおそらく目に見えない形で、現代の遠く離れた日本にも影響を与えているはずだ。
それらが謎めいていればいるほど、そして私たちを魅了すればするほど、ケルト民族に対する興味が湧いてくる。
スコットランドを訪れ、ウイスキーを愛でることは、すなわちケルト民族の魂を今に受け継ぐことに他ならない。
西洋の歴史を語る上で、ローマ帝国とキリスト教は欠かせない。
だが、その波に飲まれてしまい、歴史から消えた民族たちが独自の輝きを放っていたことを忘れてはならない。
消えてしまった民族の中でも、筆頭に挙げられるのがケルト民族であり、その痕跡を知ることは、自分たちのルーツを探る上で参考になる。
そうした意味でも本書は、ケルト民族を振り返るガイドブックになりうるはずだ。
今の科学は世界を狭くした。
だが、狭くなった世界は、人々を集約された情報と発達した文明で囲み、人々を都市に押し込めている。自由になったはずが、息苦しくなっているように思う人々もいるだろう。
中央へ、集権へ。そんな昨今を過ごす私たちからみれば、辺境の地にあって、かくも豊かな文明を生み出したケルト民族の姿は、同じ辺境に住む日本人からみても、何か相通ずるものを感じる。
両者が日本酒やウイスキーといった銘酒を生み出した民族であることも、なにやら共通の理由がありそうだ。
今の私たちは、世界中の酒文化を楽しめる。それは間違いなく幸運なことだ。
そして、ウイスキーは今も進化し続けている。
進化するウイスキーの豊かな状況はスコッチだけにとどまらない。バーボン、アイリッシュ、カナディアン、ジャパニーズも同様。
だからこそ、著者の活躍する範囲は多い。
折に触れて読んでいる著者のブログからも著者の忙しさが感じられる。
本書の情報だけに満足せず、著者のブログやWHISKY Galoreといった雑誌を読みながら、より知識を深めていきたいと思う。
‘2019/5/8-2019/5/9


